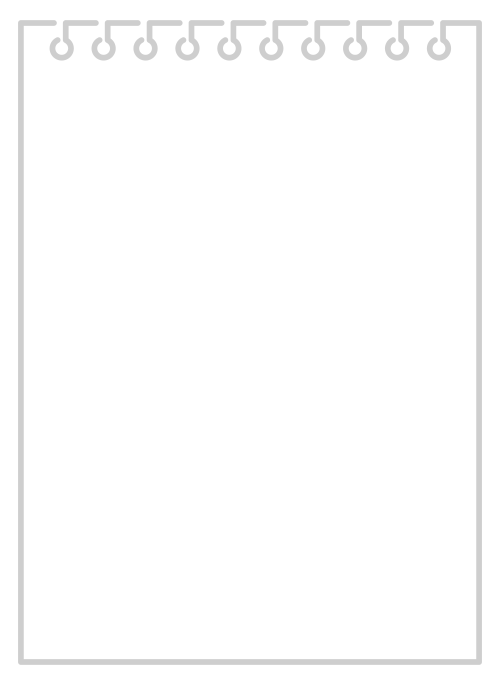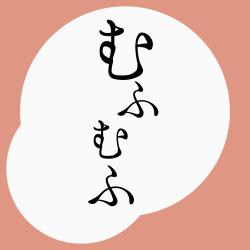シール作りは細々としていて、イリヤは時間を忘れて熱中した。
異臭はすっかりおさまって、その代わり華やかな甘い香りが漂い始めた。
ジオは作業を続けるイリヤのそばに、「ここに置きますね」とぶっきらぼうに言いつつカップを差し出した。
「これ……」
カップを手にして香りを嗅ぐイリヤを見て、ジオは「お茶です」と言う。これが本物だと言わんばかりに突きつけるのはかなり嫌味ったらしかったが、イリヤには効果がない。
「すごい! おいしい!」
素直に喜ばれて、ジオは調子が狂ってしまう。「こんなことで騒がないでください」と言う声音にはこれまでほどの刺々しさはこもっていなかった。
ジオはイリヤの向かいに腰掛け、シール作りに加わった。黙々と作業するうち、いつの間にかイリヤは寝てしまったらしい。
目が覚めたとき、机に突っ伏した自分の背中には毛布がかけられていて。
ジオにお礼を言うと、彼は変な顔をした。「どうしたの?」と訊ねると、ジオは「なんでもありません」とだけ答えた。愛想笑いをしようとしたとは言えなかったのだ。