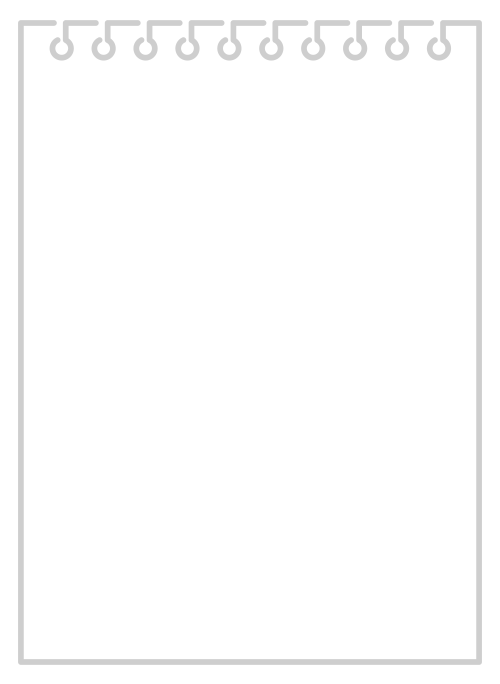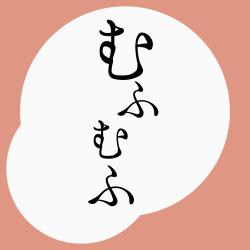誰かと付き合うなら僕に紹介してね、絶対だから、絶対。
突然ジオにそう言われて、イリヤは頭が真っ白になった。
僕はイリヤと交際する相手はどんな人間でも、いや人間以外でも、君を大切にできる立派なやつしか認めないから。
「どうしたんですか? 急に」
「どうもしないよ」ジオは朝食のトーストを牛乳で流し込む。「言っておこうと思っただけ」
ジオ以外の誰とそんなことになると言うのだろう。
人の気も知らないでーーと、イリヤは主人相手に少々苛立ってしまう。
「それに、イリヤももう大人だからね」
「大人だからとか関係ないですよ」
そう。関係ないのだ。子供の頃からジオが好きだったのだから。
「急に変なこと言わないでくださいって」
「ーーそろそろさ」
ムッとして言ったイリヤの言葉を、ジオは遮った。
「考えてもいいんだよ、将来のこと」
「話が見えないんですが」
「だから、」ジオは皿の上に指先のパン屑を落とす。「もう僕の下僕はやめてもいいってこと」
つまり、どういうことなのか。
いつかの妄想を思い出してしまう。下僕ではなく妻に。いや、まさかいきなりそんなはずはない。はずはなおと思いながらも、イリヤの頬は赤らむ。
しかし妄想が妄想でしかないことは、すぐに明らかになった。ジオはこう続けた。
「この家を出て、自立するんだ」
それはイリヤにとってあまりに急な提案で、彼女は食べかけのトーストを落としてしまった。