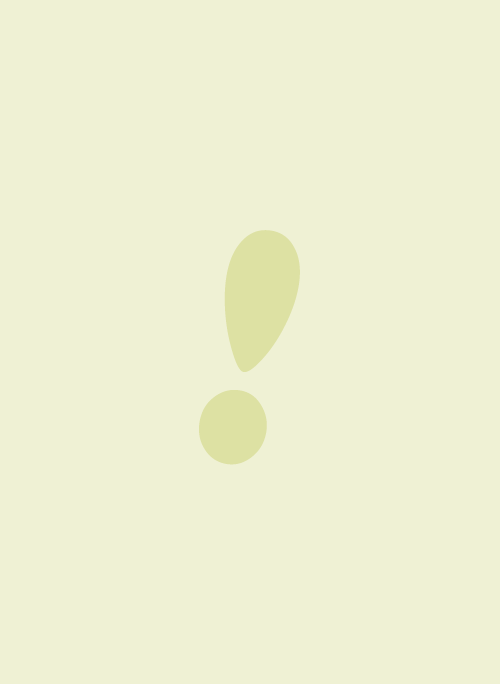「…じゃ、ここに居ていい?もっと猫たちとも遊びたいし」
「どうぞどうぞ。…なぁ、腹へらね?なんか食い行こ」
「うん」
「朝も行きたかったんだけどおまえ起きないんだもん、何も食ってねぇんだよ」
「私の顔で遊ばずに行けばよかったじゃん」
「いや、舞子の顔の方が飯より面白かったからなー」
「もぉ!」
私達は昼食を摂り、街をブラブラした。
「久しぶりにこの街を歩くと知らないお店が結構あるね」
「俺も久々歩いた。ほとんど車かバイクだもんな」
「あ、自慢してる?」
「新鮮だっつってんの」
その時、子猫を抱いた少年が通り過ぎた。
気になって、私達はあとをついて行ってみた。
しばらく歩いたビルの間の路地に入り、少年は子猫をおろして、そのまま帰ろうとした。
「やだよ、ぼくをすてないで」
少年は子猫の方を振り向き、キョロキョロしていた。
健藏さんがかわいらしい高い声で子猫の代弁をしたのだ。
「なんでその子おいてくの?」
「なんだ、おじさんか。…こいつ‘ぼく’じゃないし」
「おじ…、おにいさんは!猫を捨てるなんて許さないぞ」
「どうぞどうぞ。…なぁ、腹へらね?なんか食い行こ」
「うん」
「朝も行きたかったんだけどおまえ起きないんだもん、何も食ってねぇんだよ」
「私の顔で遊ばずに行けばよかったじゃん」
「いや、舞子の顔の方が飯より面白かったからなー」
「もぉ!」
私達は昼食を摂り、街をブラブラした。
「久しぶりにこの街を歩くと知らないお店が結構あるね」
「俺も久々歩いた。ほとんど車かバイクだもんな」
「あ、自慢してる?」
「新鮮だっつってんの」
その時、子猫を抱いた少年が通り過ぎた。
気になって、私達はあとをついて行ってみた。
しばらく歩いたビルの間の路地に入り、少年は子猫をおろして、そのまま帰ろうとした。
「やだよ、ぼくをすてないで」
少年は子猫の方を振り向き、キョロキョロしていた。
健藏さんがかわいらしい高い声で子猫の代弁をしたのだ。
「なんでその子おいてくの?」
「なんだ、おじさんか。…こいつ‘ぼく’じゃないし」
「おじ…、おにいさんは!猫を捨てるなんて許さないぞ」