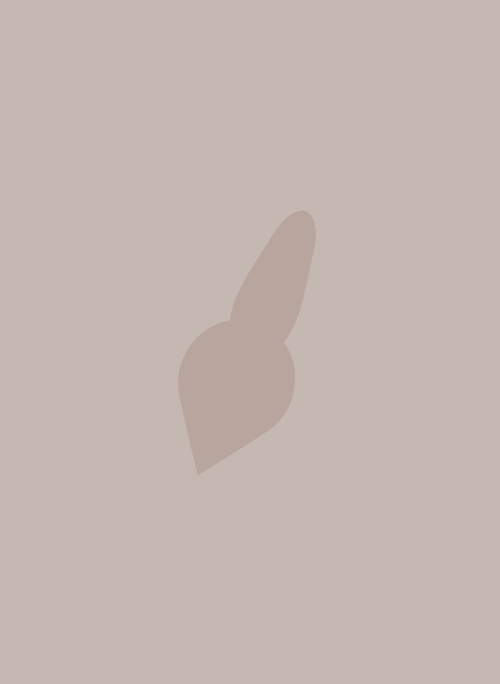《エピローグ》
緊急事態宣言が延長になったのは、5日前のことだ。数回来たことのある、羽田空港のカフェで、陽菜はある人を待っていた。
世界中で感染症が流行し、当然海外へ行くことが困難になっていた。それどころか、地方から東京へ行くことすら自粛すべきときであった。
しかし陽菜は東京経由で明日の便に乗り、ドイツに向かうことになっていた。ある人と、ある人に会うために。
コツコツとハイヒールの鳴る音がする。
「美玲先輩」陽菜は久しぶりの名前を口にした。
「陽菜ー!!!」その大人の女性は、色っぽい見かけや香りに反した動きで、陽菜に抱きつこうとする、
「せ、先輩、ソーシャルディスタンス……」
〜
「陽菜もアラサーかぁ。うししし」美玲は笑った。
「そうなんですよ。実感なくて」
「手続き終わった?」
「はい、なんとか」
「2週間かー」
「はい」
パートナーがドイツにいるということで2週間の滞在が許される。陽菜はその申請を出発ギリギリでなんとか終わらせたのだった。
「わざわざ会いに来てくれて、ありがと」
美玲は華に拍車がかかっていた。それもそのはず、美玲は今や国立オペラ劇場のプリマドンナなのだ。
「幸人くんは今日はどうしたんですか?」
「見てもらってる」実はプリマドンナになっただけではなく、美玲は母にもなっていた。幸人というのは美玲の赤ちゃんの名前だ。
「歌とお母さん両立してるの、本当すごいです」
「えへへ」美玲は素朴な笑みを浮かべた。
〜
「わたしアリス♪」美玲は突然歌い始めた。
「不思議のアリス♪」何のことかわかっている陽菜も楽しそうに歌を続けた。
「懐かしいね」
陽菜は3年生のとき、日本語のオペラ『不思議の国のアリス』で主役アリスに抜擢された。オペラでは、セリフの代わりに歌を歌って演技もする。
セットも全て学生の手作りで、段ボールで作った芋虫が横切る中、登場し、歌いながらくるくると踊って、さらにつまづいてこけそうになる演技をしなければならなかった。
わたしアリス 不思議のアリス
みんなわたしのこと不思議ーっていうの
おねえさん たいくつな本ばかり
そうしてうさぎ役が歌いながら登場する。
最終的に陽菜は大きくなって(大きくなる演技で)束になったトランプ役の同級生たちを踏んづけなければならない。
陽菜は恥ずかしいやら変なプライドやら何やらで、最初はうまく演技ができなかった。
「あたしあの時、陽菜にめちゃくちゃ葉っぱかけたよね」
「そうでしたね」美玲は毎日毎日、陽菜ー!ガッツだ!自分捨てるんだー!と陽菜に言い続けた。
陽菜はあのオペラの経験で、完全に吹っ切れた。公演のあと、美玲におめでとうと言われた時には、陽菜の中で何かが完全に弾け飛んでいた。
〜
「先生のレッスンは行ってる?」
「はい、行ってます」
「そっか」陽菜の今の境遇は、ベストというわけではなかった。学部を卒業後、大学院に進学せず、働いていた。家が中流家庭で、奨学金を貰えず、かといって大学院の学費を出すこともできず、見事な中流パラドックスにはまってしまった。
歌を諦めたわけではない。コンクールも細々と受けているし、個人レッスンは毎週続けていた。しかし働きながら歌うことは本当に大変だった。
恋愛の方も、お金を貯めて鐘に会いに行っていたが、今は感染症の流行でそれすら難しくなった。スカイプで話す遠距離恋愛だった。
それでも陽菜は、美玲の数々の言葉を胸に、どんなことがあっても心は幸せでいると決めていた。
〜
「あ、これ恋の水路行った時のですね」陽菜はスマホに残っていた写真を見ながら嬉しそうに言う。
「デートスポットなのに4人で行ったんだよね」美玲は笑った。そこは美しい場所で、石畳のしかれた、紅葉の並木路が続いてゆく水路だった。
「そうそう。あのあと焼肉行って、鐘さんからドイツの大学院行くことにしたって聞いて……」陽菜は言った。
「陽菜も知らなかったよね。やっぱ……やなやつ」と美玲が言う。陽菜は苦笑した。
「鐘さんのこと空港まで送ったときのこともすっごく覚えてます」
「あの日も、羽田空港だったね」美玲は言う。
〜
陽菜、美玲、冬真は空港で鐘を見送った。
「向こうに行っても、元気でね!」美玲は言った。
「うん。美玲も頑張りすぎないようにね」
「頑張ってないよ!」美玲は答えた。
「お世話になりました。お身体に気をつけて」冬真が言った。
「うん。わざわざ来てくれて本当にありがとうね」
「鐘さん」と陽菜。
「陽菜」鐘は優しい笑みを浮かべながら、陽菜の名前を読んだ。美玲と冬真に、わりい、ちょっと陽菜と2人で話しててもいい?と了承を得る。
「陽菜?ちょっとじっとしててね」そう言って鐘は、陽菜の耳に手を伸ばした。さらさらした髪が鐘の手の甲に落ちる。
「鐘さん……これ、イヤリング?」
「うん。陽菜。四つ葉のクローバーの葉には意味があって、ひとつは前向くこと、ひとつは信じること、ひとつは幸せ、もうひとつは……」
「鐘さんです」陽菜は言った。
「え?」
「もうひとつは、鐘さんです」陽菜は涙を浮かべながら微笑んだ。
〜
美玲のスマホが鳴った。
「あ、パパ?うん。何か買って帰ろうか?え?陽菜?」美玲は陽菜にスマホを渡し、陽菜はそれを受け取る。陽菜はその“パパ”を知っていた。
「冬真先輩、お久しぶりです」
〜
8時間のフライトと列車の旅は、陽菜にたくさんの考える時間を用意した。
背の高い駅舎を抜けると、王様が住んでいたお城が見えた。逆光で夕日に照らされている。
そこに1人の男性のシルエットが見える。
彼は陽菜の人生のかけがえのない人だった。
緊急事態宣言が延長になったのは、5日前のことだ。数回来たことのある、羽田空港のカフェで、陽菜はある人を待っていた。
世界中で感染症が流行し、当然海外へ行くことが困難になっていた。それどころか、地方から東京へ行くことすら自粛すべきときであった。
しかし陽菜は東京経由で明日の便に乗り、ドイツに向かうことになっていた。ある人と、ある人に会うために。
コツコツとハイヒールの鳴る音がする。
「美玲先輩」陽菜は久しぶりの名前を口にした。
「陽菜ー!!!」その大人の女性は、色っぽい見かけや香りに反した動きで、陽菜に抱きつこうとする、
「せ、先輩、ソーシャルディスタンス……」
〜
「陽菜もアラサーかぁ。うししし」美玲は笑った。
「そうなんですよ。実感なくて」
「手続き終わった?」
「はい、なんとか」
「2週間かー」
「はい」
パートナーがドイツにいるということで2週間の滞在が許される。陽菜はその申請を出発ギリギリでなんとか終わらせたのだった。
「わざわざ会いに来てくれて、ありがと」
美玲は華に拍車がかかっていた。それもそのはず、美玲は今や国立オペラ劇場のプリマドンナなのだ。
「幸人くんは今日はどうしたんですか?」
「見てもらってる」実はプリマドンナになっただけではなく、美玲は母にもなっていた。幸人というのは美玲の赤ちゃんの名前だ。
「歌とお母さん両立してるの、本当すごいです」
「えへへ」美玲は素朴な笑みを浮かべた。
〜
「わたしアリス♪」美玲は突然歌い始めた。
「不思議のアリス♪」何のことかわかっている陽菜も楽しそうに歌を続けた。
「懐かしいね」
陽菜は3年生のとき、日本語のオペラ『不思議の国のアリス』で主役アリスに抜擢された。オペラでは、セリフの代わりに歌を歌って演技もする。
セットも全て学生の手作りで、段ボールで作った芋虫が横切る中、登場し、歌いながらくるくると踊って、さらにつまづいてこけそうになる演技をしなければならなかった。
わたしアリス 不思議のアリス
みんなわたしのこと不思議ーっていうの
おねえさん たいくつな本ばかり
そうしてうさぎ役が歌いながら登場する。
最終的に陽菜は大きくなって(大きくなる演技で)束になったトランプ役の同級生たちを踏んづけなければならない。
陽菜は恥ずかしいやら変なプライドやら何やらで、最初はうまく演技ができなかった。
「あたしあの時、陽菜にめちゃくちゃ葉っぱかけたよね」
「そうでしたね」美玲は毎日毎日、陽菜ー!ガッツだ!自分捨てるんだー!と陽菜に言い続けた。
陽菜はあのオペラの経験で、完全に吹っ切れた。公演のあと、美玲におめでとうと言われた時には、陽菜の中で何かが完全に弾け飛んでいた。
〜
「先生のレッスンは行ってる?」
「はい、行ってます」
「そっか」陽菜の今の境遇は、ベストというわけではなかった。学部を卒業後、大学院に進学せず、働いていた。家が中流家庭で、奨学金を貰えず、かといって大学院の学費を出すこともできず、見事な中流パラドックスにはまってしまった。
歌を諦めたわけではない。コンクールも細々と受けているし、個人レッスンは毎週続けていた。しかし働きながら歌うことは本当に大変だった。
恋愛の方も、お金を貯めて鐘に会いに行っていたが、今は感染症の流行でそれすら難しくなった。スカイプで話す遠距離恋愛だった。
それでも陽菜は、美玲の数々の言葉を胸に、どんなことがあっても心は幸せでいると決めていた。
〜
「あ、これ恋の水路行った時のですね」陽菜はスマホに残っていた写真を見ながら嬉しそうに言う。
「デートスポットなのに4人で行ったんだよね」美玲は笑った。そこは美しい場所で、石畳のしかれた、紅葉の並木路が続いてゆく水路だった。
「そうそう。あのあと焼肉行って、鐘さんからドイツの大学院行くことにしたって聞いて……」陽菜は言った。
「陽菜も知らなかったよね。やっぱ……やなやつ」と美玲が言う。陽菜は苦笑した。
「鐘さんのこと空港まで送ったときのこともすっごく覚えてます」
「あの日も、羽田空港だったね」美玲は言う。
〜
陽菜、美玲、冬真は空港で鐘を見送った。
「向こうに行っても、元気でね!」美玲は言った。
「うん。美玲も頑張りすぎないようにね」
「頑張ってないよ!」美玲は答えた。
「お世話になりました。お身体に気をつけて」冬真が言った。
「うん。わざわざ来てくれて本当にありがとうね」
「鐘さん」と陽菜。
「陽菜」鐘は優しい笑みを浮かべながら、陽菜の名前を読んだ。美玲と冬真に、わりい、ちょっと陽菜と2人で話しててもいい?と了承を得る。
「陽菜?ちょっとじっとしててね」そう言って鐘は、陽菜の耳に手を伸ばした。さらさらした髪が鐘の手の甲に落ちる。
「鐘さん……これ、イヤリング?」
「うん。陽菜。四つ葉のクローバーの葉には意味があって、ひとつは前向くこと、ひとつは信じること、ひとつは幸せ、もうひとつは……」
「鐘さんです」陽菜は言った。
「え?」
「もうひとつは、鐘さんです」陽菜は涙を浮かべながら微笑んだ。
〜
美玲のスマホが鳴った。
「あ、パパ?うん。何か買って帰ろうか?え?陽菜?」美玲は陽菜にスマホを渡し、陽菜はそれを受け取る。陽菜はその“パパ”を知っていた。
「冬真先輩、お久しぶりです」
〜
8時間のフライトと列車の旅は、陽菜にたくさんの考える時間を用意した。
背の高い駅舎を抜けると、王様が住んでいたお城が見えた。逆光で夕日に照らされている。
そこに1人の男性のシルエットが見える。
彼は陽菜の人生のかけがえのない人だった。