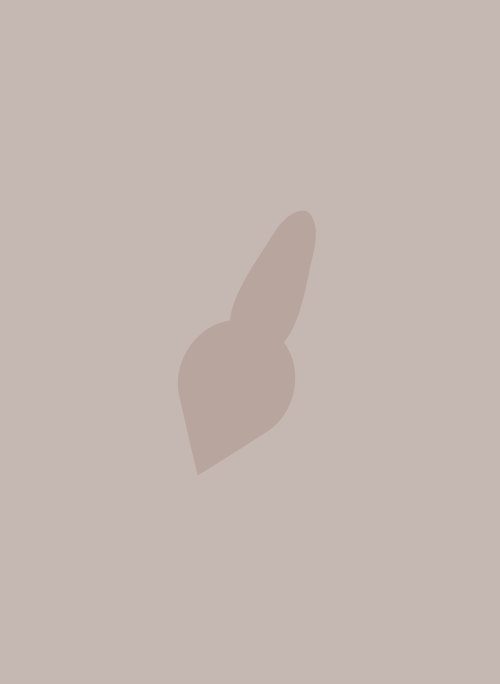Clover《旅立ちの章》
音楽棟の廊下を、通り過ぎてゆく。いくつもの練習室が並んでおり、いくつもの音たちがうねりとなり聞こえてくる。各自が練習している音だ。ヴァイオリンやピアノの音。歌声も聞こえる。廊下にはトロンボーンやクラリネットの練習をしている人の姿が見える。何度も何度も繰り返されるパッセージ。
Frondi tenere……e belle.
《優しく美しき枝葉》とイタリア語で誰かが歌い始めた。この曲を練習するということは一年生の子だろう。オンブラ・マイ・フ。懐かしい木陰。有名な曲だ。陽菜は予約しておいた練習室に入り、いつものように、四つ葉のクローバーの栞に祈った。そして深呼吸を何回かして、音階を歌い始める。陽菜はもう、劣等生でもなければ、一人ぼっちでもなかった。
東京で行われる、コンクールの全国大会までの期間は、1ヶ月ほどであったが、本当にあっという間だった。鐘先輩と新幹線で東京に行く。演奏は幸いなことに午後からだった。
「(いよいよ明日)」陽菜はカバンの中身を確認する。受験票、ドレス、靴、イヤリング、楽譜、ストッキング、髪のスプレー、鏡、録音機、折り畳み傘、財布、手帳、栞。母からの激励の電話をもらい、鐘先輩と最後の打ち合わせのメッセージを交換して、体操をして、アロマをたいて眠りにつく。
〜
新幹線の乗り場で、陽菜はお気に入りの黄色い花のワンピースを着て、準備万端で待っている。
「おはよう!よく眠れた?」鐘がやってきて声をかけた。
「おはようございます、鐘先輩!ちゃんと眠れました!」陽菜は答えた。
新幹線に乗り、隣り合ってシートに座る。陽菜にとって東京は初めてだったし、なにより鐘と一緒で、ドキドキしていた。鐘は陽菜に、いろいろなことを話し、質問をなげかけてくれるのだが、陽菜は、はいとか、ええとか、答えるのに精一杯だった。
「あ、お弁当買ってあります」富士山を車窓から眺めた後、陽菜がそう言った。
「お、ありがとう!食べようか」と鐘。
「あれ?同じお弁当……のはずなのに」
「陽菜の弁当梅干し入ってないんじゃない?あげる」と鐘は陽菜のごはんに梅干しを載せる。そして、よしよし、と頭を撫でた。
「え……」妹みたいに思われているのだろうか。陽菜は何とも言えない気持ちになった。
東京はあいにくの大雨だった。2人は折り畳みの傘をそれぞれさして会場に向かった。建設途中のスカイツリーの見える会場だったがそれどころでなく、着いた頃には、スカートも靴もびしょ濡れだった。
「陽菜、大丈夫?」
「大丈夫です!」と陽菜はとりあえず答えた。2人は例によってそれぞれの控室へと向かった。幸いなことに、スーツケースの中のドレスと靴は大丈夫だった。陽菜はドレスに着替え、準備をし、いつものように栞のお祈りをしようと思い、カバンの中を探した。
「(あれ……?ない)」カバンの中身を全てひっくり返したり、手帳のページを確認したが、栞がなかった。それでも、陽菜の心は全ての感謝の気持ちとともに落ち着いていた。悲しくもならなかった。陽菜にとって、翔のことが、過去になったことに気がついた。
「(翔くん、ありがとう。行ってくるね)」
〜
舞台袖で鐘が待っている。
「意気込みは?」鐘が聞いた。
「この曲を聞かせたい人がいるんです。聞いてないかもしれないし、届かないかもしれないけど、それでも……です」
「聞いてるよ、きっと」
シュトラウスの万霊節。ヨーロッパでは亡くなった人の魂が帰ってくると言われる日がある。その日に花を飾り、亡くなった人のことを思い出し、過ぎ去った日を歌う。
陽菜は回想した。
「この歌はどういうイメージ?」鐘は合わせで陽菜に尋ねた。
「亡くなった人のことを思い出してるから……すごく悲しい感じに歌いたいです」
「ん」鐘は言った。
「この曲は悲しいだけの曲?」
陽菜は思い直した。翔が亡くなったとき、もう生きていけないと思った。しかしそれでも生きなければならなかった。だから、陽菜は、翔が亡くなったことを知らされて、泣けなかった。だがあのとき、泣いてもよかったんだと思えた……全ては月日が経ち、穏やかな思い出になるのだから。
「ごめんなさい。直前に本当に非常識なんですけど、いつもと違うように歌ってもいいですか?」陽菜は目の中に星を宿し、尋ねた。
「いいよ。合わせる」鐘は答えた。2人は舞台に上がった。
優しい前奏のメロディーが、鐘の指から、ピアノへ、そして会場全体に響き渡る。その伴奏に陽菜は乗っかるだけだ。
《テーブルに花たちを飾って
あの時みたいに愛を語ろう
手を握らせて
人がどう思おうと気にしない
あの5月の日のように
またあなたといたい》
陽菜は自分の状況とあまりにも曲がシンクロしていることや、翔にそっくりなピアニストとの出会いが、不思議でならなかった。
コンクールは闘いではあるが、もうそんなことはどうでとよく、お世話になった人たちや、2人の“ショウ”への感謝でいっぱいだった。
胸がいっぱいで、溢れ出たものを、聴衆に届けるように歌えた、気がした。
〜
「東京まで一緒に来てくださって、音楽的にもいっぱい助けてもらって、ありがとうございました」陽菜は言った。東京のお肉の美味しいバルと評判の店で、2人はディナーをとっていた。
「こちらこそ楽しかったよ。結果今日じゃないんだね。珍しい。いつわかるの?」鐘は尋ねた。
「明日ホームページに掲載されます」
「そっか。楽しみだね!」
「でも今日はバタバタでした。まさかの梅干し入ってなくて鐘先輩にもらってしまうところから始まり……」
「うん。ふふふ」鐘は笑った。
「雨でびしょびしょになって。先輩もびしょびしょなのに、私のことばかり気遣ってくださって」
「そりゃあ今日の主役ですもん」と鐘。
「そして……そして、大事なお守りにしてた四つ葉のクローバーの栞をなくしてしまったんです。大切な人から貰った大事な栞だったんですけど。小さなアクシデントが続いて……そうして先行き不安な感じで舞台に上がったけど、でも、なんとかなって、よかったです」
「そうだね。ん?大切な人?」聞いても大丈夫?と目で伺いながら、鐘は言った。
「高校の時、ちょっと、好きだった人で……私の名前、四つ葉のクローバーのことだよ、って、言ってくれて……栞くれたん、ですけど、でも」陽菜は言葉をひとつずつ紡ぐように言った。表情が曇る。
「うん……俺、何聞いても驚かないけど、無理して言わなくていいよ」鐘は陽菜の暗い過去に、やっと触れたことに、やっとだ、と思い、冷静に言葉を選ぶ。
「いえ、いいです。折角の打ち上げですし」
「そう」鐘は勘が良かった。片思いをして振られたのか?それとも、いや、まさかな。
「栞をなくしたのに、私悲しくなかったんです。私って冷たいなって」陽菜は両手を膝の上で握る。私は何を言っているんだろう。
「うーん。ふふ。今日はプチ不安な事が起きる日だったんだけど、栞が身代わりになってくれたのかもね。その栞が陽菜を東京まで連れてきて、大雨の中逞しく歩かせて、舞台に立たせたんだな」鐘は言葉を選ぶのを断念して、いつもの調子で続けた。
「(そして、あなたにも引き合わせた。鐘さん……)」陽菜は心の声をていねいに自分の中にしまった。
「不思議話かー。陽菜?俺はさ、実はもう25なんだ。美玲と同期だけど、歳は2つ離れてる。大学受験のときも浪人したし、学部でもダブってなぁ。いや、ちゃらんぽらんだったわけじゃねえよ。こう見えても真面目だったんだ。いや、まじめくさって、暗くて、ピアノもイマイチで」鐘はつづけた。陽菜は不思議そうに鐘の顔を覗き込む。
「5年前。陽菜と同じ2年生だった。大学は違うけど。ほら、教育学部。車にはねられてさ、休学したんだ。けっこうリハビリ大変でな。ピアノ弾けないかと思った。そう、指の体操いちからやり直しだ」
「……」陽菜はどう返して良いかわからぬまま、耳を傾ける。
「事故の後俺は一周しちゃったみたいでさ。性格も味の好みも、話し方から歩き方から全てが変わった。元々甘いのとか炭酸とか飲めなかったんだけど、病院の自販機のクリームソーダにハマってな」
「(翔くんみたい)」陽菜は思った。
「当然ピアノも変わって、気づいたら大学院生で、“音色がきれいな鐘さん”だとか言われるようになった。自分で言うのもなんだけどさ」鐘はそうして微笑んだ。
「それって……5年前……?それは、2011年のことですか?」
「うん。秋にな」鐘は言った。
「俺一回死んだのかもな。事故の後から、俺は音楽を求めてきたけど、ずっと誰かを探してた気がする……って、くっさー!」鐘が真面目な話の最後におちゃらけるので、陽菜はいつもの調子を取り戻して、笑った。
「陽菜、その大事な人と何があったかわからないけど、もし、その人のことが過去になったのなら……いや、それまで俺、待つよ」
「はい」陽菜は思わず、先に返事してしまった。鐘は笑った。
「付き合ってください」
〜
「ひーな!奨励賞、おめでとう。」いつもの食堂。日常が戻ってくる。美玲先輩は陽菜にお祝いを述べた。
「ありがとうございます。先輩のおかげです」陽菜は答える。
「ううん?陽菜が頑張ったからだよ!」美玲は隙のある笑顔でそう言った。目も口も横に伸ばされ、少女のような笑顔だ。陽菜は美玲のこんな顔を初めて見た。
「で、どうだった?鐘との東京は?」
「あ、あの……」
「全部知ってるよー。おめでとう、かける、に!」そう、美玲は陽菜が鐘と付き合い始めたことを、知っていた。美玲は続けた。
「陽菜、聞いてくれる?あたしね……鐘のこと……すっごい、好きだったんだ……」小さく震える美玲のその言葉に、陽菜はどう答えればいいのか、わからない。
「でもね、計算もあったんだよね。あたしね、高校の頃、モンスターって、呼ばれてた。なんでも歌えるから。ってか、あたし性格悪いし。それでね、あるとき自分の人生が怖くなったんだよね。あたしはこれからも歌うモンスターと呼ばれるのかな?って」
「そうなんですね……」
「歌は好きだけど、あたしの幸せって、なんだろって思った。そこに鐘がいた」
「そうだったんですか……」
「でも、あたし、行けるとこまで行くことにしたよ。陽菜の演奏、すごかった。あたしたち、結局のところ歌ってないと生きていけないよね。歌わなくても生活はできるけど、生活することと生きることは全然違うし。それが、歌い手という生き物なんだよね」
「なんていうか……やっぱり美玲先輩って、すごいです」
「そう?陽菜?だから陽菜も、頑張って。歌もだけど、なにより、ちゃんと幸せになることに貪欲になって?」
「幸せに貪欲に……」
「あたしは歌う覚悟をしたよ。陽菜は、明るく生きる覚悟をするの。振り返らないで、幸せのために生きるんだよ」
「はい……わかりました……!」陽菜が答えると、美玲はまた、隙だらけの笑顔を取り戻した。
そこに冬真と鐘がやってきた。2人は2限同じ授業を取っている。冬真は、柄にもなくにやにやしている。それもそのはず、この秋大学院を合格したからだった。
「冬真!合格おめでと!」美玲は言った。
「ありがとうございます」冬真は終始、口角がぷるぷるしている。
「ほんとほんと。おめでとー」鐘も続けた。
「鐘!陽菜と付き合ったんでしょ!知ってるよー。やなやつやなやつ」美玲も冬真に続いてキャラが崩壊してきた。
「うん、俺やなやつだよね、本当」鐘は少し悲しそうな困った顔でそう言った。
陽菜はひとまず安堵した。美玲先輩と鐘先輩、普通に話せてる?のかな。4人の仲が壊れなくて、よかった。
抱えていない者などいない。だが陽菜たちの人生は、いつだって音楽とともにあり、忘れられない曲とともに流れて進んでいくのであった。
音楽棟の廊下を、通り過ぎてゆく。いくつもの練習室が並んでおり、いくつもの音たちがうねりとなり聞こえてくる。各自が練習している音だ。ヴァイオリンやピアノの音。歌声も聞こえる。廊下にはトロンボーンやクラリネットの練習をしている人の姿が見える。何度も何度も繰り返されるパッセージ。
Frondi tenere……e belle.
《優しく美しき枝葉》とイタリア語で誰かが歌い始めた。この曲を練習するということは一年生の子だろう。オンブラ・マイ・フ。懐かしい木陰。有名な曲だ。陽菜は予約しておいた練習室に入り、いつものように、四つ葉のクローバーの栞に祈った。そして深呼吸を何回かして、音階を歌い始める。陽菜はもう、劣等生でもなければ、一人ぼっちでもなかった。
東京で行われる、コンクールの全国大会までの期間は、1ヶ月ほどであったが、本当にあっという間だった。鐘先輩と新幹線で東京に行く。演奏は幸いなことに午後からだった。
「(いよいよ明日)」陽菜はカバンの中身を確認する。受験票、ドレス、靴、イヤリング、楽譜、ストッキング、髪のスプレー、鏡、録音機、折り畳み傘、財布、手帳、栞。母からの激励の電話をもらい、鐘先輩と最後の打ち合わせのメッセージを交換して、体操をして、アロマをたいて眠りにつく。
〜
新幹線の乗り場で、陽菜はお気に入りの黄色い花のワンピースを着て、準備万端で待っている。
「おはよう!よく眠れた?」鐘がやってきて声をかけた。
「おはようございます、鐘先輩!ちゃんと眠れました!」陽菜は答えた。
新幹線に乗り、隣り合ってシートに座る。陽菜にとって東京は初めてだったし、なにより鐘と一緒で、ドキドキしていた。鐘は陽菜に、いろいろなことを話し、質問をなげかけてくれるのだが、陽菜は、はいとか、ええとか、答えるのに精一杯だった。
「あ、お弁当買ってあります」富士山を車窓から眺めた後、陽菜がそう言った。
「お、ありがとう!食べようか」と鐘。
「あれ?同じお弁当……のはずなのに」
「陽菜の弁当梅干し入ってないんじゃない?あげる」と鐘は陽菜のごはんに梅干しを載せる。そして、よしよし、と頭を撫でた。
「え……」妹みたいに思われているのだろうか。陽菜は何とも言えない気持ちになった。
東京はあいにくの大雨だった。2人は折り畳みの傘をそれぞれさして会場に向かった。建設途中のスカイツリーの見える会場だったがそれどころでなく、着いた頃には、スカートも靴もびしょ濡れだった。
「陽菜、大丈夫?」
「大丈夫です!」と陽菜はとりあえず答えた。2人は例によってそれぞれの控室へと向かった。幸いなことに、スーツケースの中のドレスと靴は大丈夫だった。陽菜はドレスに着替え、準備をし、いつものように栞のお祈りをしようと思い、カバンの中を探した。
「(あれ……?ない)」カバンの中身を全てひっくり返したり、手帳のページを確認したが、栞がなかった。それでも、陽菜の心は全ての感謝の気持ちとともに落ち着いていた。悲しくもならなかった。陽菜にとって、翔のことが、過去になったことに気がついた。
「(翔くん、ありがとう。行ってくるね)」
〜
舞台袖で鐘が待っている。
「意気込みは?」鐘が聞いた。
「この曲を聞かせたい人がいるんです。聞いてないかもしれないし、届かないかもしれないけど、それでも……です」
「聞いてるよ、きっと」
シュトラウスの万霊節。ヨーロッパでは亡くなった人の魂が帰ってくると言われる日がある。その日に花を飾り、亡くなった人のことを思い出し、過ぎ去った日を歌う。
陽菜は回想した。
「この歌はどういうイメージ?」鐘は合わせで陽菜に尋ねた。
「亡くなった人のことを思い出してるから……すごく悲しい感じに歌いたいです」
「ん」鐘は言った。
「この曲は悲しいだけの曲?」
陽菜は思い直した。翔が亡くなったとき、もう生きていけないと思った。しかしそれでも生きなければならなかった。だから、陽菜は、翔が亡くなったことを知らされて、泣けなかった。だがあのとき、泣いてもよかったんだと思えた……全ては月日が経ち、穏やかな思い出になるのだから。
「ごめんなさい。直前に本当に非常識なんですけど、いつもと違うように歌ってもいいですか?」陽菜は目の中に星を宿し、尋ねた。
「いいよ。合わせる」鐘は答えた。2人は舞台に上がった。
優しい前奏のメロディーが、鐘の指から、ピアノへ、そして会場全体に響き渡る。その伴奏に陽菜は乗っかるだけだ。
《テーブルに花たちを飾って
あの時みたいに愛を語ろう
手を握らせて
人がどう思おうと気にしない
あの5月の日のように
またあなたといたい》
陽菜は自分の状況とあまりにも曲がシンクロしていることや、翔にそっくりなピアニストとの出会いが、不思議でならなかった。
コンクールは闘いではあるが、もうそんなことはどうでとよく、お世話になった人たちや、2人の“ショウ”への感謝でいっぱいだった。
胸がいっぱいで、溢れ出たものを、聴衆に届けるように歌えた、気がした。
〜
「東京まで一緒に来てくださって、音楽的にもいっぱい助けてもらって、ありがとうございました」陽菜は言った。東京のお肉の美味しいバルと評判の店で、2人はディナーをとっていた。
「こちらこそ楽しかったよ。結果今日じゃないんだね。珍しい。いつわかるの?」鐘は尋ねた。
「明日ホームページに掲載されます」
「そっか。楽しみだね!」
「でも今日はバタバタでした。まさかの梅干し入ってなくて鐘先輩にもらってしまうところから始まり……」
「うん。ふふふ」鐘は笑った。
「雨でびしょびしょになって。先輩もびしょびしょなのに、私のことばかり気遣ってくださって」
「そりゃあ今日の主役ですもん」と鐘。
「そして……そして、大事なお守りにしてた四つ葉のクローバーの栞をなくしてしまったんです。大切な人から貰った大事な栞だったんですけど。小さなアクシデントが続いて……そうして先行き不安な感じで舞台に上がったけど、でも、なんとかなって、よかったです」
「そうだね。ん?大切な人?」聞いても大丈夫?と目で伺いながら、鐘は言った。
「高校の時、ちょっと、好きだった人で……私の名前、四つ葉のクローバーのことだよ、って、言ってくれて……栞くれたん、ですけど、でも」陽菜は言葉をひとつずつ紡ぐように言った。表情が曇る。
「うん……俺、何聞いても驚かないけど、無理して言わなくていいよ」鐘は陽菜の暗い過去に、やっと触れたことに、やっとだ、と思い、冷静に言葉を選ぶ。
「いえ、いいです。折角の打ち上げですし」
「そう」鐘は勘が良かった。片思いをして振られたのか?それとも、いや、まさかな。
「栞をなくしたのに、私悲しくなかったんです。私って冷たいなって」陽菜は両手を膝の上で握る。私は何を言っているんだろう。
「うーん。ふふ。今日はプチ不安な事が起きる日だったんだけど、栞が身代わりになってくれたのかもね。その栞が陽菜を東京まで連れてきて、大雨の中逞しく歩かせて、舞台に立たせたんだな」鐘は言葉を選ぶのを断念して、いつもの調子で続けた。
「(そして、あなたにも引き合わせた。鐘さん……)」陽菜は心の声をていねいに自分の中にしまった。
「不思議話かー。陽菜?俺はさ、実はもう25なんだ。美玲と同期だけど、歳は2つ離れてる。大学受験のときも浪人したし、学部でもダブってなぁ。いや、ちゃらんぽらんだったわけじゃねえよ。こう見えても真面目だったんだ。いや、まじめくさって、暗くて、ピアノもイマイチで」鐘はつづけた。陽菜は不思議そうに鐘の顔を覗き込む。
「5年前。陽菜と同じ2年生だった。大学は違うけど。ほら、教育学部。車にはねられてさ、休学したんだ。けっこうリハビリ大変でな。ピアノ弾けないかと思った。そう、指の体操いちからやり直しだ」
「……」陽菜はどう返して良いかわからぬまま、耳を傾ける。
「事故の後俺は一周しちゃったみたいでさ。性格も味の好みも、話し方から歩き方から全てが変わった。元々甘いのとか炭酸とか飲めなかったんだけど、病院の自販機のクリームソーダにハマってな」
「(翔くんみたい)」陽菜は思った。
「当然ピアノも変わって、気づいたら大学院生で、“音色がきれいな鐘さん”だとか言われるようになった。自分で言うのもなんだけどさ」鐘はそうして微笑んだ。
「それって……5年前……?それは、2011年のことですか?」
「うん。秋にな」鐘は言った。
「俺一回死んだのかもな。事故の後から、俺は音楽を求めてきたけど、ずっと誰かを探してた気がする……って、くっさー!」鐘が真面目な話の最後におちゃらけるので、陽菜はいつもの調子を取り戻して、笑った。
「陽菜、その大事な人と何があったかわからないけど、もし、その人のことが過去になったのなら……いや、それまで俺、待つよ」
「はい」陽菜は思わず、先に返事してしまった。鐘は笑った。
「付き合ってください」
〜
「ひーな!奨励賞、おめでとう。」いつもの食堂。日常が戻ってくる。美玲先輩は陽菜にお祝いを述べた。
「ありがとうございます。先輩のおかげです」陽菜は答える。
「ううん?陽菜が頑張ったからだよ!」美玲は隙のある笑顔でそう言った。目も口も横に伸ばされ、少女のような笑顔だ。陽菜は美玲のこんな顔を初めて見た。
「で、どうだった?鐘との東京は?」
「あ、あの……」
「全部知ってるよー。おめでとう、かける、に!」そう、美玲は陽菜が鐘と付き合い始めたことを、知っていた。美玲は続けた。
「陽菜、聞いてくれる?あたしね……鐘のこと……すっごい、好きだったんだ……」小さく震える美玲のその言葉に、陽菜はどう答えればいいのか、わからない。
「でもね、計算もあったんだよね。あたしね、高校の頃、モンスターって、呼ばれてた。なんでも歌えるから。ってか、あたし性格悪いし。それでね、あるとき自分の人生が怖くなったんだよね。あたしはこれからも歌うモンスターと呼ばれるのかな?って」
「そうなんですね……」
「歌は好きだけど、あたしの幸せって、なんだろって思った。そこに鐘がいた」
「そうだったんですか……」
「でも、あたし、行けるとこまで行くことにしたよ。陽菜の演奏、すごかった。あたしたち、結局のところ歌ってないと生きていけないよね。歌わなくても生活はできるけど、生活することと生きることは全然違うし。それが、歌い手という生き物なんだよね」
「なんていうか……やっぱり美玲先輩って、すごいです」
「そう?陽菜?だから陽菜も、頑張って。歌もだけど、なにより、ちゃんと幸せになることに貪欲になって?」
「幸せに貪欲に……」
「あたしは歌う覚悟をしたよ。陽菜は、明るく生きる覚悟をするの。振り返らないで、幸せのために生きるんだよ」
「はい……わかりました……!」陽菜が答えると、美玲はまた、隙だらけの笑顔を取り戻した。
そこに冬真と鐘がやってきた。2人は2限同じ授業を取っている。冬真は、柄にもなくにやにやしている。それもそのはず、この秋大学院を合格したからだった。
「冬真!合格おめでと!」美玲は言った。
「ありがとうございます」冬真は終始、口角がぷるぷるしている。
「ほんとほんと。おめでとー」鐘も続けた。
「鐘!陽菜と付き合ったんでしょ!知ってるよー。やなやつやなやつ」美玲も冬真に続いてキャラが崩壊してきた。
「うん、俺やなやつだよね、本当」鐘は少し悲しそうな困った顔でそう言った。
陽菜はひとまず安堵した。美玲先輩と鐘先輩、普通に話せてる?のかな。4人の仲が壊れなくて、よかった。
抱えていない者などいない。だが陽菜たちの人生は、いつだって音楽とともにあり、忘れられない曲とともに流れて進んでいくのであった。