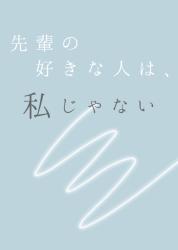「話を聞いてると、割とタイプな子に当てはまってる気がするんだけど、素っ気ないんだよね。どうしたらいいんだろう?」
「そうだなあ……」
知らないよ。
相手のタイプなんだったらもう直球で気持ちを伝えればいいじゃないか――いや、伝えないでくれ。
「馬鹿みたいなこと言っても笑ってくれて、優しいんだよ。へへ」
「そっか。いい人なんだね」
本人に言ってやれよ。僕に言ってどうするんだ。
でも、言ってくれなくて助かる。
「私、結構アピールしてるつもりなんだけど、全然効果ないみたいなんだよね。何でだと思う?」
だから、そんなの本人に――。
僕は耐えられなくなって、初めて自分からもう寝ると言って電話を切った。
彼女の「おやすみ」を期待して待つことなく。
僕は、ちゃんと相槌を打てていただろうか。
彼女を傷つけるような態度をとってしまわなかっただろうか。
自信がない。
次に電話がかかってきたときには、この関係に終止符を打つことを申し出た。
「最近ずっと考えていたんだけどさ。あまりこうやって他の男と親しくするのが、よくないんじゃないかなって。相手の男が知ったら、いい気はしないと思うよ。……だから、こういう風に電話するの、ちょっと控えよう」
なんとか声を絞り出す。
この6帖に響く声は、何とも情けない音色をしていた。