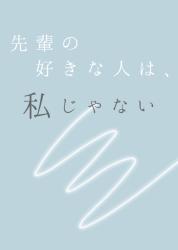「それはそうと、常盤さん。好きな人とは、うまくいきそうなの?」
突如投げかけられたその問いを聞き、固まってしまう。
これは、どっちだ。
自分のことだって気づいている?
それとも違う人だと思っている?
「あはは、どうかな」
彼がどう考えているのかわからないので、こちらもお茶を濁すことしかできない。
「最近ずっと考えていたんだけどさ。あまりこうやって他の男と親しくするのが、よくないんじゃないかなって。相手の男が知ったら、いい気はしないと思うよ」
冷や水を浴びせられて、頭の中が真っ白になった。
どうして、そんなことを言うの。
「だから、こういう風に電話するの、ちょっと控えよう」
どうして――ああ、私が余計なことを言ったせいか。
私は選択を間違えたんだ。今すぐ訂正すれば間に合うのだろうか。
違うよ、私の好きな人は秋津くんだから、これでいいんだよ、って。
でも、秋津くんは電話をやめようとするくらい、私のことを何とも思っていないのが明白なのに?
そんなことを言ってしまったら、事態が悪化しそうな気がする。
結局、私は何も言えなかった。
音がしなくなったスマホをぼーっと見つめる。
今まで存在を信じて疑わなかった、彼と私を結ぶ糸までプツンと切られてしまったように感じた。