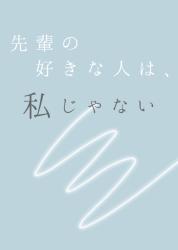部屋の電気をつけて、棚からグラスを、そして冷凍庫から氷を取り出しつつ考える。
今電話をかけて、出てくれたら、きっと花火大会には行っていないだろう。
だからもし出てくれたら、正直な私の気持ちを話そう。
出てくれなかったら、彼のことはちゃんと諦めよう。
これで最後にする。
そう心に誓って、履歴から彼に電話をかけた。
「もしもし」
出てくれた!
ということは、私はこれから真実を口にするのだ。
心臓が早鐘を打つ。
「もしもし、秋津くん?」
アイスコーヒーを飲もうと思って用意したグラス。
その中に入れた氷をじっと見つめながら声を発した。
「うん」
少し掠れた、気だるそうな声の色気にドキッとしてしまう。
「常盤さん、この前に僕がした話、忘れてる? 変わらず結構頻繁にかけてきてくれるけど」
少し困ったような声だ。