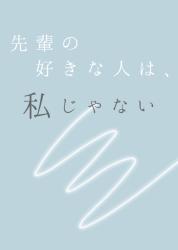それから秋津くんは、電話をかけてもほとんど出てくれなくなった。
珍しく出てくれたときでも、特に用件がないとわかるとすぐに切られてしまう。
あまりにも素っ気ない。
本当は、私の好きな人云々は関係なくて、単に私が鬱陶しくなっただけかもしれない。
目の前にあるホットのカフェラテをぐるぐるとかき混ぜながら考える。
もしかして、秋津くんにも好きな人ができたのだろうか。
それならば合点がいく。
これまで他の友達との予定がある日や遅くまでバイトの日を除いて、週の半分以上は寝落ちするまで通話をしていたけれども、もし新たに好きな人ができたとすれば、その習慣は邪魔になる。
私とこれだけ夜に電話することができるのだから、彼女はいないのだなあと思っていた。
その安心感を得られた行為の消失は、つまるところ行き着く先がその逆であることを意味する。
味気なくなった日々は、私に懊悩と憂いをもたらした。