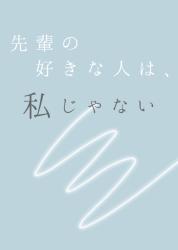「常盤さん、もう寝た?」
まだ起きているよ、と返事をしたいのに、体が言うことを聞いてくれない。
まだ、話していたいのに。
もっと、ふたりで話をしたいのに。
私の心に反して、何度も開こうとした目蓋が観念しなさいとでも言うように重みを増していく。
「おやすみ、常盤さん」
その声が甘く響いたように思えたのは、夢の中だからだろうか。
夢か現か、曖昧なその境目で微睡みながら、私は今日も幸福感に浸る。
深い色のコーヒーの中に、砂糖とミルクがたっぷりと注がれていくような感覚。
そして、私はその中に沈んでいくような気配を覚えながら、深い眠りに落ちていった。