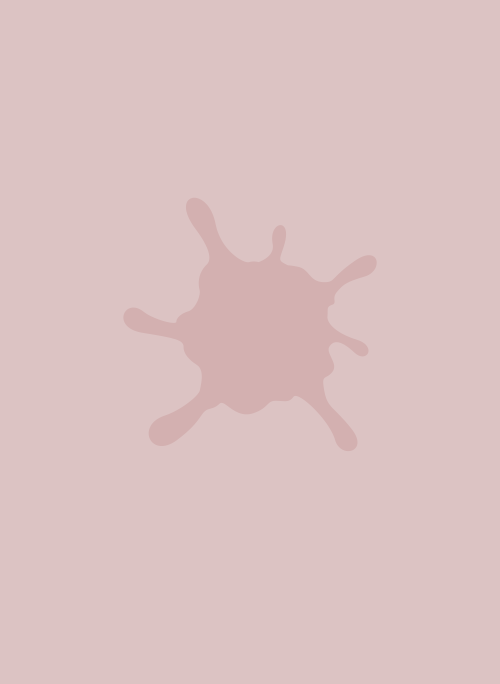私が君と出会ったとき。
それはまだ暑さの残る,いわゆる残暑で。
でも着実に秋へと近づいていたときだった。
最初に理解をしたのは暗闇の中,女の人が怒鳴り散らしている声。
次に,衝撃。ガラスが割れる音。
自分が殴られたと認識するのに少し時間がかかった。
いつの間にか私のほっぺたは地面に張り付いていて,そこで初めて突き飛ばされたのだと知った。
そして近くで響く微かな,震えた声。
頭の中にその声だけが響いて,こびりついてくる。
なんでだろう。なんでこんなにもこの声が気になるんだろう?
なんでこんなにも心が揺さぶられるんだろう?
そんなことを考えているうちにひたひたとこちらに歩いてくる足音が聞こえてくる。
『お前が……!!お前さえいなければっ!私はあの人と結婚できたのに!!!!』
狂気じみた声と小さく震える声が重なる。
そこでやっと震えている男の子はこの女の人に傷つけられ,苦しめられてるのだと知る。
そっと女の人を見ると,尖った,光るものを手に持っていた。
本能が,あれはやばいと伝えてくる。
そして次に逃げろという本能に従い,私は必死に手足をばたつかせる。
ゆっくりゆっくり近づいてくる影にぞわりと鳥肌が立つ。
そこからは,あまり記憶がない。
ただ,必死に必死に逃げて,近くの公園に駆け込んだのは覚えている。
気づけば君も隣にいて,小さなしゃくり上げる声だけが夜の公園に響いていた。
私はなんだか話してはいけない気がして,じっと男の子の後ろに回り込んだ。
そこからどのくらいたっただろうか。
気づけば夜は明けていて,太陽の眩しさに目を細める。
私は静かにすると決めたけれど,やっぱりいい加減気になって尋ねてしまった。
『あの人は,君のお母さん?』
男の子は不思議そうに辺りをキョロキョロしてそして後ろを振り返った。
透き通った,でも光のない目には私が映されているのがわかる。
私は椅子に座って彼に話しかける。
『なんで君を傷つけようとするの?』
男の子は瞳を揺らして,そして目を伏せたまま答えた。
『わから,ない。』
その1単語を絞り出すために男の子がどれだけの勇気を使ったのだろう。
その当時の私はそんなことを知る由もなく,でも‘’わからない”のではなく,‘’わかりたくない”のだと言うことだけはわかった。
『母さんは,ぼくに暴力をする。
昔はそうじゃなかった。でも,ぼくがいると結婚できないから,だからっ……。』
たどたどしい,けれども強い感情が混じった声だった。
その途切れた言葉の先はいくら私でもわかった。
‘’『僕は,いらない子なんだ……。』”
多分,そんなようなことを言おうとして,でも言えなかったのだと思う。
私はどーやって声をかければいいのかわからなくなって,そっと彼の声に耳を傾けた。
かすれた泣き声だけが夜明けの公園に響き渡る。
そのとき私は決意したのだ。
彼……未愛渡(みえど)は私が守ると。
何があっても絶対に1人にはさせないと。
そんなことを,考えていた。