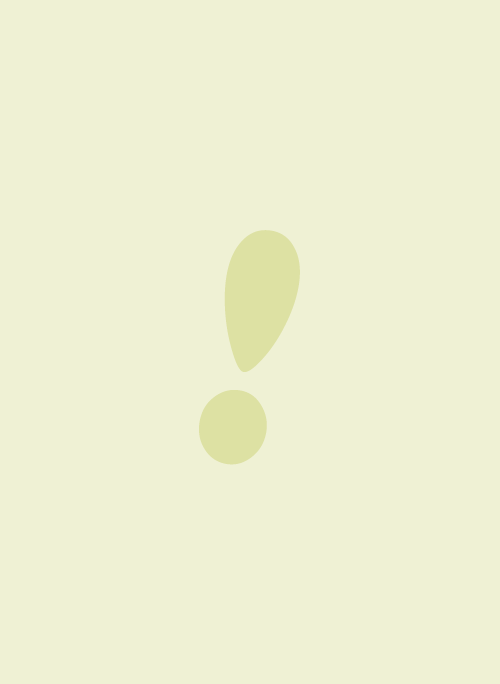紫色の瞳が特別珍しいというわけではないが、その多くは亜人か魔物に多い。それ故にメイドの間では長く見つめ合うと呪いがかけられるなどといった風潮が宮中に流れていた。当然、リゼもそのことは知っている。
「あなたも私が呪いをかけると思っているのね?」眉一つ動かさず、涼しい表情のまま問いかけるリゼにメイドはひれ伏して、萎縮してしまい震えた声で「滅相もございません。そんなことは一度も思ったことなどございません」
リゼは鼻をならした。
「メデューサって知っている?」
「いえ、知りません」
「頭には髪の毛の代わりに蛇が生えていてね、瞳は私の瞳のように怪しい紫色なの。それでその瞳を見た者がどうなるかわかる?」
メイドは思案にくれる。リゼの真意を推し量ろうとしている。リゼにとってみれば冗談のつもりだが、一介のメイドとしてみれば答えいかんによっては不敬罪にあたるとまで考え込んでいた。メイドは意を消しって答える。
「やっぱり呪われたりするのでしょうか?」
「あなたも私が呪いをかけると思っているのね?」眉一つ動かさず、涼しい表情のまま問いかけるリゼにメイドはひれ伏して、萎縮してしまい震えた声で「滅相もございません。そんなことは一度も思ったことなどございません」
リゼは鼻をならした。
「メデューサって知っている?」
「いえ、知りません」
「頭には髪の毛の代わりに蛇が生えていてね、瞳は私の瞳のように怪しい紫色なの。それでその瞳を見た者がどうなるかわかる?」
メイドは思案にくれる。リゼの真意を推し量ろうとしている。リゼにとってみれば冗談のつもりだが、一介のメイドとしてみれば答えいかんによっては不敬罪にあたるとまで考え込んでいた。メイドは意を消しって答える。
「やっぱり呪われたりするのでしょうか?」