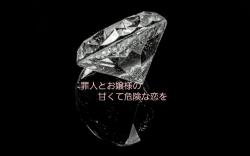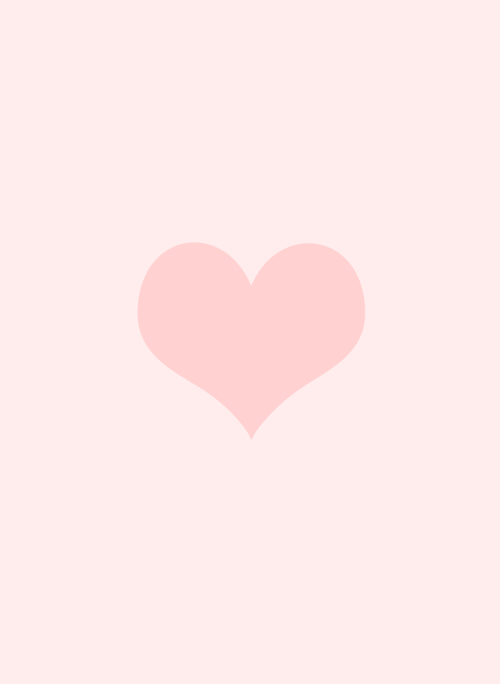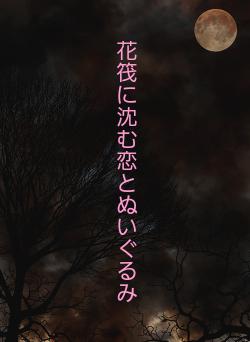それからというものの、優月は家族の反対を押しきり、左京が暮らした山の家で一人暮らすようになった。誰とも会わずに、ただただ左京との短くも楽しかった思い出に浸り、そして寂しさと悔しさを感じながら日々を過ごした。
結婚をすることもなく、年齢だけを重ねた。この時代の女など結婚し子ども産む事だけが生きる役割のようなものだ。そのため、優月は変わり者とされ、村の人たちからも次第に避けられるようになった。けれど、それでよかった。誰とも関わって暮らすつもりなどなかったのだから。
家族も見て見ぬふりをしていたけれど、さすがに哀れに思ったのか、月に数回、食材と少しの銭をこっそり山の家の玄関に置いてくれていた。自給自足で暮らしたことがなかった優月は、両親に甘えるのは嫌だったけれど、暮らしていくためにはそれを受けとるしかなかった。左京が守ってくれた命を易々と終わらせるのは申し訳ないと思えていたので、両親のその行いには感謝をしていた。
そして、そんな暮らしの中でも、優月にはやることがあった。
矢鏡神社のお参りと清掃だった。左京が蛇の化け物を倒すとその後は安定した天気が戻ってきた。そのため、左京は神のように慕われるようになった。そして、村の人々は左京への感謝と労りの気持ちを表すために、彼を神様として崇め、神社を作ったのだ。そう、あの山の中の、優月を助けた崖付近に。崖のすぐ傍では危険があるとして、近くに神社を建てた。そのため、優月が暮らす左京の家からは目と鼻の先にあるのだ。
神社へ赴き、風を感じながら、物言わぬ神となった左京の傍で静かに過ごすのが何よりも楽しみであった。
歳をとり、死ぬまで神社と共に過ごしていきたい。それが、ささやかな願いであった。
けれど、その願いも叶わなかった。
また優月が年老いてきた頃に、また村の悪天候が続いた。今となれば、悪天候が続いてしまうことも長い年月の中ではあるものだとわかるが、その頃は全て何かの祟りや神様が怒っていると考えられていた。そのため、今回も何かよくない事があるのだと考えてしまった。そして、その矛先はなんと矢鏡神社であった。