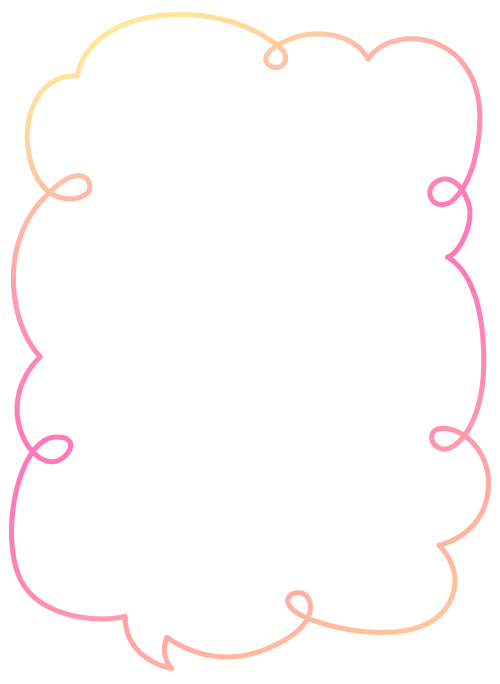ーside 奏都(かなと)ー
午前中の診察ラッシュが一段落し、午後の2時半ようやく休憩がとれた。
医局へ戻り、背中を大きく伸ばしていると胸ポケットに入っていた携帯が鳴った。
画面に表示された人の名前は、懐かしい人からの電話だった。
その電話の相手は、高校の時の恩師で今は校長先生として働いていると聞いた。
「夏目先生。お久しぶりです。」
「あっ、城山君。久しぶり。元気だったかな?」
「はい。元気にやってます。」
「折り入って、話があるんだけど今大丈夫かな?」
「はい。大丈夫ですよ。」
「実はね、去年の4月に健康診断で心臓に病気が見つかった子がいるんだ。
その子、今は高校2年生になったんだけど…。
ちょうど今年の3月で、うちの高校にいた保健医が辞めてしまって。
それで、城山君に保健医と保健室の教師としてうちに来てくれないかな?」
「急ですね…。それに、保健室の教師って…」
「城山君は、大学で医学部と教育学部の両方の単位を取得したと聞いたんだけど…」
確かに、大学で医学部と教育学部の両方の単位を取得し両方の免許を持っているけど…。
保健医にも興味があって、病院に常駐しながらでは無く、学校に席を置き保健医として働きたい気持ちがあった。
大学の時から興味のある保健医として働けるならこれはチャンスじゃないのか?
元々、保健医としての枠は少なくそこに入れる人も極わずかだと聞いたことがある。
夏目校長先生は、教育委員会と深い繋がりがあるから俺を推薦してくれたのかもしれない。
「もちろん。無理にとは言わない。
だけど、うちの学校は医療の知識を持っている人がいないし、その子はなんの前触れもなく倒れてしまうから対処も難しくて。
いつか、私たちの知識不足や力不足であの子の命を奪ってしまうんじゃないかと考えると、いてもたっても居られなくなって。
それでも、彼女には皆と同じようにここで学んで卒業してほしいと思うんだ。
彼女の未来を守りたい。」
保健医が、今年の3月で辞めてしまったのか…。
その子の、心の支えとなる人が今はいないということだよな。
ただでさえ、病気を抱えて不安なのにそんな状況だと余計に学校に通うことが怖くなってしまうよな。
俺が、助けに行くしかないよな。
それ以外に、選択肢はなかった。
「分かりました。ぜひ、私にその役目を務めさせてください。」
「ありがとう、城山君。よろしく頼んだよ。」
「こちらこそよろしくお願い致します。」
「それから、その子のことなんだけど。」
「はい。」
「実は、その子。ちょっと複雑な家庭で。
今は、彼女の治療にあたっている主治医の方と暮らしているんだ。」
「それって…。」
「詳しいことは、よく分からない。
彼女自身に聞いても、話そうとしてくれなくて。
苗字は変わっていないから、養子としてその医師が引き取ったわけではないと思うんだけど。」
「そうなんですね。分かりました。
明日、そちらに伺います。
それで、もし大丈夫でしたらその子とじっくり話をさせてくれませんか?」
「ありがとう。
そうしてほしいのは、山々なんだけどその子は大人に対して聞く耳を持たなくて。
教師が深入りしてくることが嫌いな子なんだ。
だから、じっくり話ができるかは正直分からないけど…。」
「それでも、構いません。
明日からよろしくお願い致します。」
「こちらこそ。」
病気以外にも、抱えていることはたくさんありそうだな。
まあ、近づきすぎず離れすぎず。
程よい距離を保ちながら、彼女をみていこう。
俺は、この時想像もしていなかった。
まさか、10歳も離れたその子に本気になることなんて。
午前中の診察ラッシュが一段落し、午後の2時半ようやく休憩がとれた。
医局へ戻り、背中を大きく伸ばしていると胸ポケットに入っていた携帯が鳴った。
画面に表示された人の名前は、懐かしい人からの電話だった。
その電話の相手は、高校の時の恩師で今は校長先生として働いていると聞いた。
「夏目先生。お久しぶりです。」
「あっ、城山君。久しぶり。元気だったかな?」
「はい。元気にやってます。」
「折り入って、話があるんだけど今大丈夫かな?」
「はい。大丈夫ですよ。」
「実はね、去年の4月に健康診断で心臓に病気が見つかった子がいるんだ。
その子、今は高校2年生になったんだけど…。
ちょうど今年の3月で、うちの高校にいた保健医が辞めてしまって。
それで、城山君に保健医と保健室の教師としてうちに来てくれないかな?」
「急ですね…。それに、保健室の教師って…」
「城山君は、大学で医学部と教育学部の両方の単位を取得したと聞いたんだけど…」
確かに、大学で医学部と教育学部の両方の単位を取得し両方の免許を持っているけど…。
保健医にも興味があって、病院に常駐しながらでは無く、学校に席を置き保健医として働きたい気持ちがあった。
大学の時から興味のある保健医として働けるならこれはチャンスじゃないのか?
元々、保健医としての枠は少なくそこに入れる人も極わずかだと聞いたことがある。
夏目校長先生は、教育委員会と深い繋がりがあるから俺を推薦してくれたのかもしれない。
「もちろん。無理にとは言わない。
だけど、うちの学校は医療の知識を持っている人がいないし、その子はなんの前触れもなく倒れてしまうから対処も難しくて。
いつか、私たちの知識不足や力不足であの子の命を奪ってしまうんじゃないかと考えると、いてもたっても居られなくなって。
それでも、彼女には皆と同じようにここで学んで卒業してほしいと思うんだ。
彼女の未来を守りたい。」
保健医が、今年の3月で辞めてしまったのか…。
その子の、心の支えとなる人が今はいないということだよな。
ただでさえ、病気を抱えて不安なのにそんな状況だと余計に学校に通うことが怖くなってしまうよな。
俺が、助けに行くしかないよな。
それ以外に、選択肢はなかった。
「分かりました。ぜひ、私にその役目を務めさせてください。」
「ありがとう、城山君。よろしく頼んだよ。」
「こちらこそよろしくお願い致します。」
「それから、その子のことなんだけど。」
「はい。」
「実は、その子。ちょっと複雑な家庭で。
今は、彼女の治療にあたっている主治医の方と暮らしているんだ。」
「それって…。」
「詳しいことは、よく分からない。
彼女自身に聞いても、話そうとしてくれなくて。
苗字は変わっていないから、養子としてその医師が引き取ったわけではないと思うんだけど。」
「そうなんですね。分かりました。
明日、そちらに伺います。
それで、もし大丈夫でしたらその子とじっくり話をさせてくれませんか?」
「ありがとう。
そうしてほしいのは、山々なんだけどその子は大人に対して聞く耳を持たなくて。
教師が深入りしてくることが嫌いな子なんだ。
だから、じっくり話ができるかは正直分からないけど…。」
「それでも、構いません。
明日からよろしくお願い致します。」
「こちらこそ。」
病気以外にも、抱えていることはたくさんありそうだな。
まあ、近づきすぎず離れすぎず。
程よい距離を保ちながら、彼女をみていこう。
俺は、この時想像もしていなかった。
まさか、10歳も離れたその子に本気になることなんて。