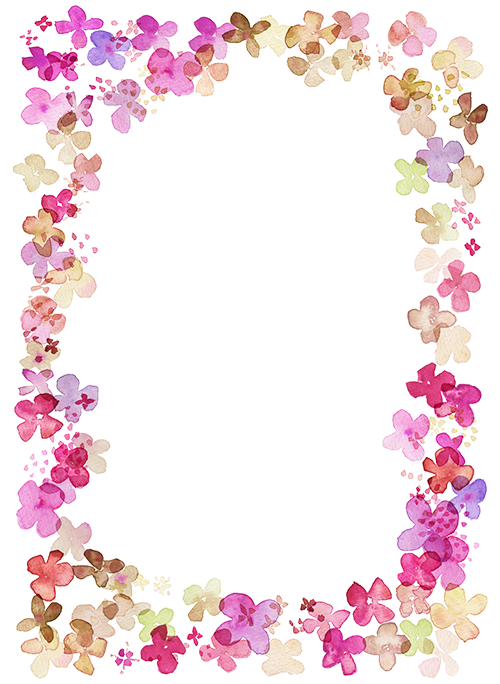「君はけしてそんなことをするような女性じゃないだろう? 馬鹿な真似はやめるんだ」
彼女は俯いた。
塞ぎこんでしまっている今の彼女には、どんな言葉を言ってもだめなのだろう。
運よく今夜は救うことができたけれど、すっかり思いつめている彼女がまた馬鹿な行動に出てしまうのは目に見えていた。
「…いったい何があったら、君の口からそんな言葉が出るの?」
「……」
彼女が押し黙るのも無理はない。
彼女にとっては、俺は気まぐれに自分を助けただけの初対面の男。
そんな人間に真意を打ち明かすわけがない。
それに、打ち明かしたところで、彼女の心を覆う闇は容易く消えやしないのだろう。
汚れること。
唯一そのことだけが、彼女が闇から脱出する手段なのだとしたら―――。
彼女を、俺だけのものにしたい。
猛烈な衝動が生まれた。
それは、あの雨の日に芽生えた願望そのものだった。
誰にも触れさせたくない。渡したくない。汚されたくない。
俺が彼女のなにもかもを奪いきってしまいたい。
俺は握っていた彼女の手に力を込め、強引に引き寄せた。
片腕だけでも余るほどの華奢な背中を抱き締め、怯えたように揺れる漆黒の瞳を一心に見つめて、戸惑うように半開きになった紅い唇を親指で愛撫する。
「そんなに汚れたいのなら、俺が染めてあげる」
そうして彼女の許可を得ることもなく、まず最初に唇を奪った。
彼女は俯いた。
塞ぎこんでしまっている今の彼女には、どんな言葉を言ってもだめなのだろう。
運よく今夜は救うことができたけれど、すっかり思いつめている彼女がまた馬鹿な行動に出てしまうのは目に見えていた。
「…いったい何があったら、君の口からそんな言葉が出るの?」
「……」
彼女が押し黙るのも無理はない。
彼女にとっては、俺は気まぐれに自分を助けただけの初対面の男。
そんな人間に真意を打ち明かすわけがない。
それに、打ち明かしたところで、彼女の心を覆う闇は容易く消えやしないのだろう。
汚れること。
唯一そのことだけが、彼女が闇から脱出する手段なのだとしたら―――。
彼女を、俺だけのものにしたい。
猛烈な衝動が生まれた。
それは、あの雨の日に芽生えた願望そのものだった。
誰にも触れさせたくない。渡したくない。汚されたくない。
俺が彼女のなにもかもを奪いきってしまいたい。
俺は握っていた彼女の手に力を込め、強引に引き寄せた。
片腕だけでも余るほどの華奢な背中を抱き締め、怯えたように揺れる漆黒の瞳を一心に見つめて、戸惑うように半開きになった紅い唇を親指で愛撫する。
「そんなに汚れたいのなら、俺が染めてあげる」
そうして彼女の許可を得ることもなく、まず最初に唇を奪った。