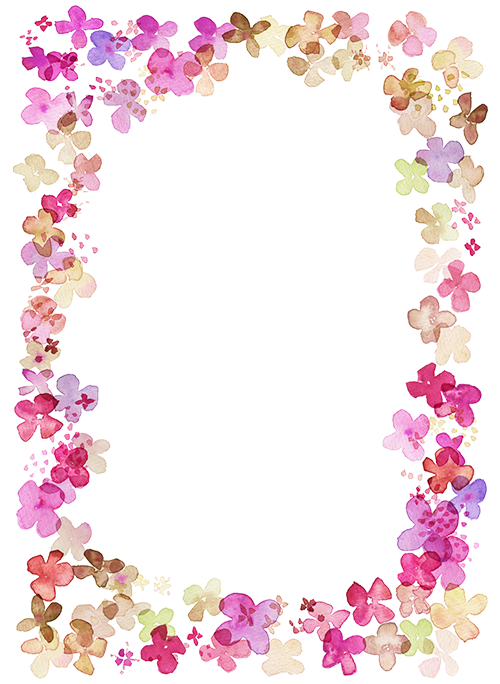しとしとと雨は続いていた。六月の雨だ。
水分を含んだ空気のように、彼女の余韻が俺の胸をひたしていた。
近くに車を待たせている。別に傘はいらないが、なんだかのぼせたような心地になって、ぼんやりと空を見上げる。
彼女を名残惜しく想う心を表したように、空は鈍色の曇天だった。
「お客様…!」
不意に鈴の音のような澄んだ声に話しかけられて振り向くと、彼女がいた。
「お客様、よろしければ傘をお持ちください。私の…女性用の傘でよろしければ…」
「え…」
「お召になっている単衣、大島紬ですよね。雨に濡れたらせっかくの高価な品が台無しになってしまいますよ」
そう微笑むと、彼女は傘を開いて両手で差し出した。
「また、お越しくださいませ」
白い歯を零したその愛らしい笑顔に見惚れながら、俺は誘われるように傘を手に取った。
礼すら言えなかった。
けれども彼女は意に介した様子もなく店の中へ戻っていく。
そうだ、名前を―――。
そう気付いて口を開いたが、柄にもなく戸惑ってしまって声が出せなかった。
彼女のような高い教養と唯一無二の美しさを併せ持つ女性に、俺のような男が軽々しく名前を訊いてよいのかと。
水分を含んだ空気のように、彼女の余韻が俺の胸をひたしていた。
近くに車を待たせている。別に傘はいらないが、なんだかのぼせたような心地になって、ぼんやりと空を見上げる。
彼女を名残惜しく想う心を表したように、空は鈍色の曇天だった。
「お客様…!」
不意に鈴の音のような澄んだ声に話しかけられて振り向くと、彼女がいた。
「お客様、よろしければ傘をお持ちください。私の…女性用の傘でよろしければ…」
「え…」
「お召になっている単衣、大島紬ですよね。雨に濡れたらせっかくの高価な品が台無しになってしまいますよ」
そう微笑むと、彼女は傘を開いて両手で差し出した。
「また、お越しくださいませ」
白い歯を零したその愛らしい笑顔に見惚れながら、俺は誘われるように傘を手に取った。
礼すら言えなかった。
けれども彼女は意に介した様子もなく店の中へ戻っていく。
そうだ、名前を―――。
そう気付いて口を開いたが、柄にもなく戸惑ってしまって声が出せなかった。
彼女のような高い教養と唯一無二の美しさを併せ持つ女性に、俺のような男が軽々しく名前を訊いてよいのかと。