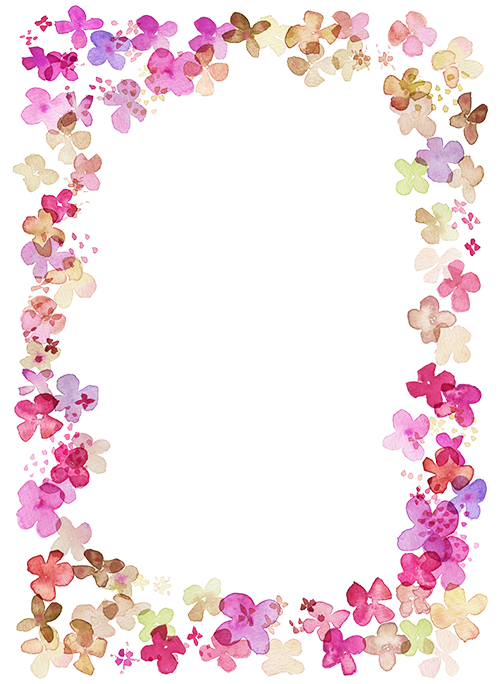「訊きたいのは俺の方だ。どうしてあの朝、黙って俺から逃げたの?」
「だって…だって私たちはそういう関係でしょう? 一晩が終わったから朝になって消えた、ただそれだけ…。あなたには、ただそれだけの女でしかないでしょう…?」
「ずいぶんと高飛車なことを言うんだな。処女を一晩だけの男に捧げただけはある」
少し傷ついたような表情を見せつつも、彼は怒りをにじませた口調で吐き捨てた。
眩暈がしそうな羞恥とその固い声に怯えを感じる私をさらに引き寄せ、彼はなおも低い声で続ける。
「俺はそんなつもりは微塵もなかった。言ったよね、『けして君を離さない』って。何度も何度も告げたよね。…君は乱れきっていたから、覚えていないのかもしれないけれど」
身体の火照りを払うように、私は必死にかぶりを振る。
「だって…だって私たちはそういう関係でしょう? 一晩が終わったから朝になって消えた、ただそれだけ…。あなたには、ただそれだけの女でしかないでしょう…?」
「ずいぶんと高飛車なことを言うんだな。処女を一晩だけの男に捧げただけはある」
少し傷ついたような表情を見せつつも、彼は怒りをにじませた口調で吐き捨てた。
眩暈がしそうな羞恥とその固い声に怯えを感じる私をさらに引き寄せ、彼はなおも低い声で続ける。
「俺はそんなつもりは微塵もなかった。言ったよね、『けして君を離さない』って。何度も何度も告げたよね。…君は乱れきっていたから、覚えていないのかもしれないけれど」
身体の火照りを払うように、私は必死にかぶりを振る。