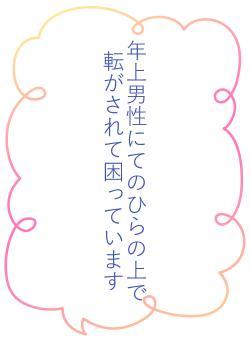二十一歳になった秋のこと。希子はちょっとムッとしながら喋っている。
「コンビニに行こうとしてこっちは歩いているだけなのにね、駐車場に止まってた車が勢いよく私に向かってきたんだよ。あれは絶対周りを確認してない」
テーブルを挟んで向かいの椅子に座る男性はそれは災難だったねと軽く笑う。
「しかもそれだけじゃないんだから。右側に避けたら、右側に止めてあった車もこっちに向かってバックしてきたの。絶対にあちこちで小さい事故が多発してるって。ねぇ、ちょっと笑ってないで聞いてる?」
「聞いてるよ、それは腹が立つしその運転手たちを疑っちゃうね」
なおも小さく笑う彼の元にコーヒーが届けられた。
昭和中期を思わせるような西洋風の内観をしている喫茶店の中では希子たちのほかにも会話に花を咲かせる人たちが多数座っている。
一本の木から切り出し組み立てられたような、武骨なテーブルは、細かい所までやすりがかけられていて肌触りは滑らかだ。
ニスを何度も塗り重ねたテーブルはどっしりと茶色くて、艶がある。
「今度はここの紅茶も飲んでみてよ、美味しいんだから」
そう言って一緒に頼んだラスクを一口頬張った。サクサクと音を立てて口の中に広がっていく。
「口にラスクが付いてるぞ」
希子に目線を合わせながら彼が口へコーヒーを運んだ。
口元の右側をパパっとほろう希子をみて、違う違う逆側だよと笑った。