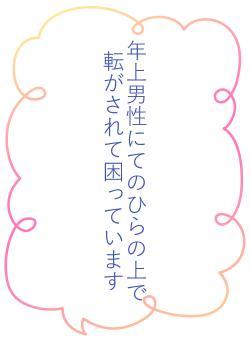右手で頭を抱えるようにベッドに倒される希子はもう、一樹が欲しくてたまらなかった。
ゆっくりと撫でられる頬、首筋を通って肩を掴む。
一樹の口は希子の鎖骨をなぞり始める。
一樹の心臓の鼓動が聞こえてきそうな程、希子の神経は丸裸になっていた。
上着のボタンをはずされているときも、胸を撫でてもらっているときも、ずっと特別な感情が希子を包んでいた。
改めて部屋の中を見回した時、隣には寝息を立てている一樹がいた。
こんな感じなのか。そう思った。初めての経験はとても特別なものだった。
終わってみるととてもあっさりとした気持だった。
それでも隣で眠っている一樹の横顔を見ているととても幸せな気持ちになる。自分の初めてをこの人に捧げてよかった。
希子は今まで自分の意見がない人間だと自分のことを思っていた。自分を持たないから他人の意見に簡単に流されて生きてきた人間だと思っていた。
紅茶が好きだと言う人がいれば自分も紅茶についてネットで情報を調べ、このメーカーが美味しいと聞けば何種類かの茶葉を買い集めたりもした。
職場の同僚が海を見るのが好きだと言うと近くの海まで出かけて行って、同僚が言うように浜辺に座り込んでしばらく海を眺める時間を作ったりもした。
一樹は後輩の兄だ。職場の後輩の兄だから特別な感じがしているだけで、流されて惹かれているだけなのではないかと不安に思うこともあった。
しかしこの気持ちは誰かに流されてできた想いなどではない。
一樹に出会い、一樹のことを好きになり、一樹に大切にしてもらいたいと思ったのは自分自身の気持ちである、それに間違いはなかった。
誰かに流されて惹かれたわけではない。そう確信できた。
一樹の手を握り、自分の頬に寄せながら再び眠りに落ちてゆく。