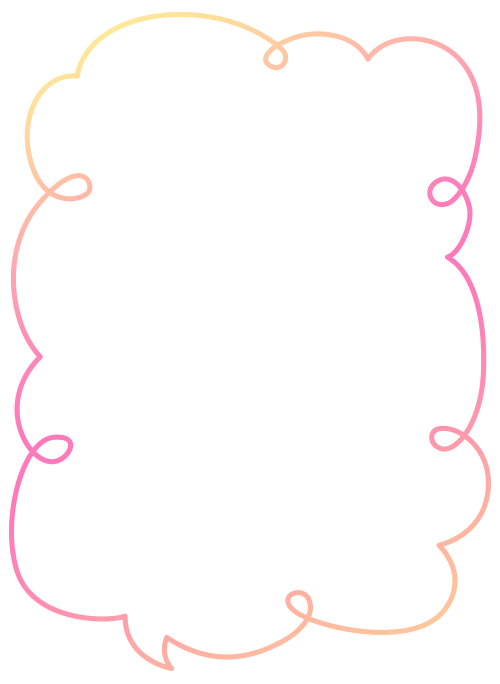「西さん知ってました?」
「知らない。」
「まだ何も言ってません!」
事務所に戻ってきて真亜子は、先輩である西に話しかけた。
いつも同じ文句で真亜子が話し始めるため、西はいつもと同じ返しをする。
「西さん、知らないと思います。」
「知ってるかもな。」
と、パソコンから視線すら離さず返答をする。
ぐっと言葉に詰まった真亜子に、西は淡々と告げた。
「お前さ、いつも言ってるけど、要点を言ってから俺が知ってるどうか聞けよ。」
「はい。7階の新しいテナントの事です。」
西はマウスをカチリカチリと動かしながら、少し逡巡し「ああ」と思い至ったようだった。
「えー!喜多さん、7階の虹イスト行ったんですかぁ??」
同僚の相田由貴(あいだゆき)が甲高い声をあげた。
「違うの、そーじゃなくて。下で女の人に場所聞かれて7階まで案内しただけだけどね。めっちゃ怪しい、何あれ。気持ち悪かった。」
相田は真亜子の怪訝そうな表情にも臆さず鼻息荒く興奮している。
「喜多さん、流行り物に疎いからなぁ。今人気の占いの館ですよ、虹イストっていうと。」
きっかけは真亜子が西に話しかけた事だったが、今はすっかり話題を相田が持っていってしまっている。
そういえばフォーチュンテラーと書いてあった、と真亜子が口を挟む間もなく相田は虹イスト情報を連ねた。
西はすっかりこちらに興味を失っている。
占いにさほど興味のない真亜子は、相田の話を無意識に受け流していた。
真亜子は視界の端にいる西に気を取られながら、相田を少し恨めしく思った。
営業職の西はあまり事務所に長居することはない。
たまに事務所に戻ったかと思えば、慌ただしく電話をして、書類をまとめてまた出て行ってしまう。
今日のように事務処理で長く座っているなんて滅多にないのだ。
それに仕事以外の話題を何度もするのは気がひけるし、せっかくの貴重な雑談タイムだったのに。
真亜子は、西の事をかっこいい人だと思っている。
付き合いたいとか、恋心とかそういうのではなく、まるで芸能人の推しを贔屓するかのような感覚で西を見ているのが楽しいのだ。
美容のスパイス扱いというか、西が事務所に帰る予定時刻になるとちょっとデスクを綺麗にしたりだとか。入口に設置してあるパンフレット類を整えたりだとか。コーヒーの在庫を確認したりとか。
要は西にできる女だと思われたい、という学生のような気持ちでいる。
西は猫背でパソコンの画面に顔を近づけ、難しい顔をしている。
「かっこいいんですよ!」
ふいの大声、真亜子は心を見透かされたのかと、相田のセリフにギョッと反応してしまった。
「喜多さん7階で見ました?虹イストの創始者。めちゃかっこいいんですよ。」
「そ…創始者?わかんない。誰かいたけど顔わかんなかった。」
あー驚いた、と真亜子の鼓動が物語っている。
自分の西推しを誰かに打ち明ける気はない真亜子は、この会話を終わらすべく、書類の入ったファイルをどさりと自分の前に置き、おもむろにペンを手にとった。
真亜子が事務処理にとりかかるのと同時に、西が背中をぐいーっと伸ばし「相田はそういう話が好きだな」と、終わらせようとした会話に食いついた。
「もともと占いとか心理テストとか好きですし、しかもそれがイケメンで今人気!なんて惹かれるに決まってるじゃないですか。」
自分が終わらせようとした会話に再びここで戻っていくのは気が引ける。
それに、真亜子がしたかった会話は「占い」をメインにしたものではなく、「7階に新しく来た新テナント」の話だ。
「西さんもこれを機に見てもらったらどうですか。婚期のがしてるじゃないですか。」
「あのねぇ、のがしてるんじゃないよ、今からが男の適齢期だよ。」
「そんなこと言っちゃって、余裕かましてると相手してもらえない年齢になっちゃいますよ。」
相田の遠慮ない物言いに西はニヤニヤと笑っている。
何気なく取った手元の資料に空白がある、ここを空白にしたままで保管した人誰よ、という不服と、自分が提供した話題で相田と西が仲良く会話していることへの不服とで真亜子は思わず「むぅー」と唸った。
その小さなうめきが聞こえたのか、西は真亜子を一瞥し「ほら相田、しゃべってないで仕事しろ。喜多先生がご立腹じゃないか。」と会話を終わらせた。
「知らない。」
「まだ何も言ってません!」
事務所に戻ってきて真亜子は、先輩である西に話しかけた。
いつも同じ文句で真亜子が話し始めるため、西はいつもと同じ返しをする。
「西さん、知らないと思います。」
「知ってるかもな。」
と、パソコンから視線すら離さず返答をする。
ぐっと言葉に詰まった真亜子に、西は淡々と告げた。
「お前さ、いつも言ってるけど、要点を言ってから俺が知ってるどうか聞けよ。」
「はい。7階の新しいテナントの事です。」
西はマウスをカチリカチリと動かしながら、少し逡巡し「ああ」と思い至ったようだった。
「えー!喜多さん、7階の虹イスト行ったんですかぁ??」
同僚の相田由貴(あいだゆき)が甲高い声をあげた。
「違うの、そーじゃなくて。下で女の人に場所聞かれて7階まで案内しただけだけどね。めっちゃ怪しい、何あれ。気持ち悪かった。」
相田は真亜子の怪訝そうな表情にも臆さず鼻息荒く興奮している。
「喜多さん、流行り物に疎いからなぁ。今人気の占いの館ですよ、虹イストっていうと。」
きっかけは真亜子が西に話しかけた事だったが、今はすっかり話題を相田が持っていってしまっている。
そういえばフォーチュンテラーと書いてあった、と真亜子が口を挟む間もなく相田は虹イスト情報を連ねた。
西はすっかりこちらに興味を失っている。
占いにさほど興味のない真亜子は、相田の話を無意識に受け流していた。
真亜子は視界の端にいる西に気を取られながら、相田を少し恨めしく思った。
営業職の西はあまり事務所に長居することはない。
たまに事務所に戻ったかと思えば、慌ただしく電話をして、書類をまとめてまた出て行ってしまう。
今日のように事務処理で長く座っているなんて滅多にないのだ。
それに仕事以外の話題を何度もするのは気がひけるし、せっかくの貴重な雑談タイムだったのに。
真亜子は、西の事をかっこいい人だと思っている。
付き合いたいとか、恋心とかそういうのではなく、まるで芸能人の推しを贔屓するかのような感覚で西を見ているのが楽しいのだ。
美容のスパイス扱いというか、西が事務所に帰る予定時刻になるとちょっとデスクを綺麗にしたりだとか。入口に設置してあるパンフレット類を整えたりだとか。コーヒーの在庫を確認したりとか。
要は西にできる女だと思われたい、という学生のような気持ちでいる。
西は猫背でパソコンの画面に顔を近づけ、難しい顔をしている。
「かっこいいんですよ!」
ふいの大声、真亜子は心を見透かされたのかと、相田のセリフにギョッと反応してしまった。
「喜多さん7階で見ました?虹イストの創始者。めちゃかっこいいんですよ。」
「そ…創始者?わかんない。誰かいたけど顔わかんなかった。」
あー驚いた、と真亜子の鼓動が物語っている。
自分の西推しを誰かに打ち明ける気はない真亜子は、この会話を終わらすべく、書類の入ったファイルをどさりと自分の前に置き、おもむろにペンを手にとった。
真亜子が事務処理にとりかかるのと同時に、西が背中をぐいーっと伸ばし「相田はそういう話が好きだな」と、終わらせようとした会話に食いついた。
「もともと占いとか心理テストとか好きですし、しかもそれがイケメンで今人気!なんて惹かれるに決まってるじゃないですか。」
自分が終わらせようとした会話に再びここで戻っていくのは気が引ける。
それに、真亜子がしたかった会話は「占い」をメインにしたものではなく、「7階に新しく来た新テナント」の話だ。
「西さんもこれを機に見てもらったらどうですか。婚期のがしてるじゃないですか。」
「あのねぇ、のがしてるんじゃないよ、今からが男の適齢期だよ。」
「そんなこと言っちゃって、余裕かましてると相手してもらえない年齢になっちゃいますよ。」
相田の遠慮ない物言いに西はニヤニヤと笑っている。
何気なく取った手元の資料に空白がある、ここを空白にしたままで保管した人誰よ、という不服と、自分が提供した話題で相田と西が仲良く会話していることへの不服とで真亜子は思わず「むぅー」と唸った。
その小さなうめきが聞こえたのか、西は真亜子を一瞥し「ほら相田、しゃべってないで仕事しろ。喜多先生がご立腹じゃないか。」と会話を終わらせた。