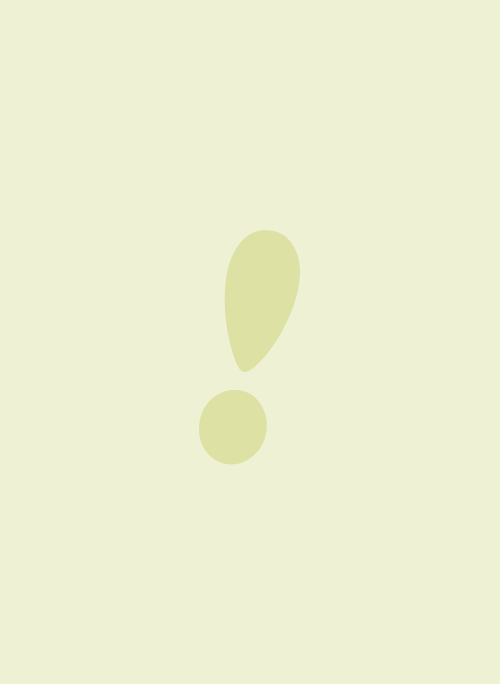汗をびっしょりとかいてシャツがへばりつく感触が気持ち悪い。クーラーがついている店内のはずが、濡れたシャツを冷やしているはずなのにその感覚がない。気持ち悪くなり視線を自分の膝に落としていると、俺の異常に気づいた詩織が心配そうな顔で、
「どうしたの?調子悪いの?」などと訊いてくる。
「ねえ、大丈夫?救急車呼んでもらう?」
ことを大きくしようとする詩織に俺は「大丈夫、すぐに治まるから」と静止した。
詩織は俺の席の背後に回ると背中をさすりだした。汗でびっしょり搔いて気持ち悪いであろうに詩織は気にも止めない。
「どうしたの、どれくらいで治まるの?」
「もうだいぶ収まってきたよ」
「病気なの?いつから?」
「病気と言えばそうかもしれない。ストレスが原因なんだ。これは、親友と詩織を殴った代償だよ。」後は裏切られたときのショックの。これは流石に本人を目の前にして言えるはずもない。
「どうしたの?調子悪いの?」などと訊いてくる。
「ねえ、大丈夫?救急車呼んでもらう?」
ことを大きくしようとする詩織に俺は「大丈夫、すぐに治まるから」と静止した。
詩織は俺の席の背後に回ると背中をさすりだした。汗でびっしょり搔いて気持ち悪いであろうに詩織は気にも止めない。
「どうしたの、どれくらいで治まるの?」
「もうだいぶ収まってきたよ」
「病気なの?いつから?」
「病気と言えばそうかもしれない。ストレスが原因なんだ。これは、親友と詩織を殴った代償だよ。」後は裏切られたときのショックの。これは流石に本人を目の前にして言えるはずもない。