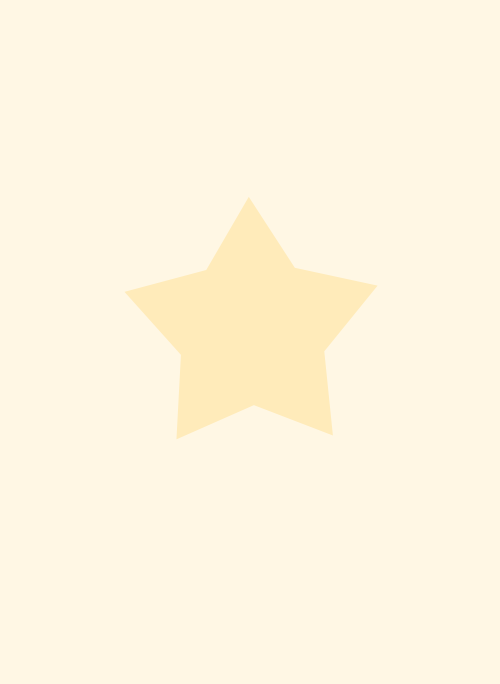彼と出会ったのは、大好きなアーティストのライブ会場。初めて会った時から気が合って、話も尽きなくて、笑顔が絶えなくて。住んでる場所も歳も違うのに、なぜか私たちは出会った時からお互いが大切な存在だった。何度もライブ会場で会った彼と私は、周りに人が沢山いても連絡を取らなくても、お互いを必ず見つけることが出来た。そして、再会した時には必ず抱きついて笑顔で沢山話をした。
私たちは、普段会えない代わりに毎日LINEをして過ごした。月が綺麗な夜に、私は彼に見せようと月の写真を撮って送ろうとした。すると、彼も私のために月の写真を撮ってくれていて、私たちは月の写真を交換した。離れていても同じものを見ている、同じことを考えている不思議な関係だった。
複雑だった家庭環境に耐えられなくて、私は真夜中に「会いたい」とLINEをしたことがあった。送ったメッセージは消そうと思ったけど、すぐに既読がついて電話がかかってきた。私の名前を呼ぶ彼の声が優しくて涙が止まらなくなってしまって。何かあった?と聞かれても上手く答えられなかった。でも、そんな私に「寂しいね、心春。大丈夫、分かってるから」と彼は言ってくれた。彼は私が言葉に出来なかった想いを、欲しかった言葉をくれて、その日は私が眠くなるまで話をしてくれた。朝起きると家には誰もいなくて、静まり返った家で泣きそうになっていたけど、「おはよう、心春。ちゃんと起きた?」と彼からLINEが来ていた。彼は友達でも恋人でも、家族でもない。でも、そんな言葉じゃ言い表せないような存在で。そんなものじゃ埋められないものを埋めてくれていた。彼は、言葉に出来ない気持ちをいつだって共有してくれた。
彼と出会って、4年以上の月日が流れた。相変わらずライブ会場で会って、LINEをして。ずっとこのままこの関係が続くのだと思っていたのに、私はライブ会場で彼の彼女を見かけてしまった。彼は私に「彼女ができた」とは言わなかったけど、私はその事実を共通の友人から聞いていた。いつからか、お互い恋愛について触れないことが暗黙の了解だった。それでもLINEはしてくれていて変わらない日々を過ごしていた。
そのうち、彼と私が話していると彼の彼女が嫌がるようになった。彼はそのことを分かっていたけど、私と話すことは辞めなかった。彼が彼女に呼ばれても私と話していた時、彼女が苦しそうに地面で蹲った。彼が彼女の肩を抱えてその場を立ち去る姿を、私は見ていることしか出来なかった。彼は知らなかったと思うけど、その時彼女は私のことを睨んでいた。
それから私は「もう終わりにしよう」と彼に告げた。彼女がいるのだから、いつまでも彼に甘えていてはいけないと思った。耐えられなくなる前に、想いが溢れる前に、彼から離れようと思った。でも彼は、私から離れてくれなかった。優しい彼は、不安定な私を、寂しがりやな私を、放っておけなかったんだと思う。
ある日、お酒に酔った彼が電話をしてきた。「彼女が嫌がるからデートではコーヒーが飲めないんだ」「彼女の行きたいお店が高くて、月は金欠なんだ」「絵文字を入れないと彼女が怒るんだ」彼はそんな話をしていた。私は、大好きなコーヒーを飲んでいる彼が好きだった。私は、コンビニで買った安いアイスを半分こにして、彼と一緒に食べるのが好きだった。私は、びっくりマークの多いシンプルな彼のLINEが好きだった。私は彼のことが本当に好きだったんだと実感してしまった。私は、出会った時から彼が好きだったのかもしれないし、そうじゃなかったのかもしれない。私は再び彼に別れを告げた。
最後に、2人で水族館に行くことになった。最初で最後のデートだった。その日もやっぱり話が尽きなくて、ずっと笑い合っていた。あんなにも楽しい水族館は、初めてだった。あっという間に時間が過ぎて帰る時間になった。駅のホームで電車を待っている間、彼はやっぱり離れたくないと言った。私は「彼女さんに悪いよ」と笑って言った。彼は優しすぎるから彼女と別れられないんだ。と、彼との共通の友人から聞いたことがあった。彼の優しさは残酷だと思った。
電車が来るアナウンスが聞こえて、私は彼に手紙を渡した。今までの感謝を言葉にしたら泣いてしまいそうだから、手紙という逃げ道を作っていた。手紙を受け取った彼は、苦しそうに私を見つめていた。到着した電車に乗り、私は「バイバイ」と笑って彼に言った。ドアが閉まる時、彼が私の名前を呼んだ。彼が手を伸ばそうとしている。私は泣きそうになるのを我慢して、ドア越しの彼に「好きだったよ」と笑顔で言った。伝わったか、伝わらなかったかは分からない。彼の気持ちも、私の気持ちも、私たちは本当は分かっていた。分かっていたからこそ、直接「好き」を伝えなかった。
その日の夜はなぜか泣けなかった。自分で選んだ道なのに失ったものが大きすぎて。私はたぶん、彼がいなくても生きていける。でも、彼のいない世界で生きていても意味がないと思っていた。気付いたら朝になっていて、色々なことがどうでも良くて、私は川沿いを歩いていた。このまま飛び込もうか。それとも、知らない誰かに心の穴を埋めてもらおうか。呆然とそんなことを考えていたんだと思う。
その時、彼の声が聞こえた気がした。顔を上げると「心春!」と叫ぶ、彼の姿が見えた。どうして彼は、こんな時まで私を見つけてしまうのだろう。駆け寄ってくる彼に抱きつくことはもう出来ないのに、彼が愛しくてたまらなかった。なぜここにいるのか尋ねる前に、彼は手紙を差し出してきた。彼が私のために書いてくれた手紙だ。「オレの気持ち、心春に伝え切れてなくて。誰かに運んでもらうのは違う気がして、直接届けに来た」と彼は笑って言った。彼も会えると思っていなかったようで、私はやっぱり運命だと思ってしまった。私は彼に別れてほしいわけじゃない。彼の隣で同じものを見ていたかった。ただ、彼と一緒に笑っていたかった。彼は最後に私を抱きしめた。
彼の手紙には「ずっと心春のことが好きだった」と書いてあった。出会った時から、心春が何よりも大切だったのに、結果的に傷つけてしまった、と。謝罪の文や、今までの感謝が記されていた。彼は、私が寂しくないように手紙を書いてくれたんだと思う。私は、彼のどうしようもない優しさも含めて好きだった。
それ以来、彼とは連絡を取っていない。ライブ会場で見つけても、会うことはないだろう。彼は、私の人生には不可欠だった。好きという感情の前に、大切だった。何よりも、誰よりも、幸せになってほしかった。彼は私にとってカッコ悪いスーパーマンで、好きなことを忘れるくらい、大切だった。言葉じゃ言い表せない関係。共有できる存在。お互いが、お互いの気持ちを分かり合える。嫌なことも、嬉しいことも、自然と分かる。友達でも、恋人でも、家族でもなかったけれど、きっとそれ以上の存在だった。
私はもう、彼の名前を呼べない。彼に抱きつくことも、話すことも出来ない。彼が今、何をして、何を想っているのか。私にはもう、分からない。彼と私の関係に名前があれば、今も隣にいられたのかもしれない。それでも、彼が幸せならそれで良い。彼が笑っていれば、彼がくれた思い出があれば、私はきっと、生きていける気がする。
私たちは、普段会えない代わりに毎日LINEをして過ごした。月が綺麗な夜に、私は彼に見せようと月の写真を撮って送ろうとした。すると、彼も私のために月の写真を撮ってくれていて、私たちは月の写真を交換した。離れていても同じものを見ている、同じことを考えている不思議な関係だった。
複雑だった家庭環境に耐えられなくて、私は真夜中に「会いたい」とLINEをしたことがあった。送ったメッセージは消そうと思ったけど、すぐに既読がついて電話がかかってきた。私の名前を呼ぶ彼の声が優しくて涙が止まらなくなってしまって。何かあった?と聞かれても上手く答えられなかった。でも、そんな私に「寂しいね、心春。大丈夫、分かってるから」と彼は言ってくれた。彼は私が言葉に出来なかった想いを、欲しかった言葉をくれて、その日は私が眠くなるまで話をしてくれた。朝起きると家には誰もいなくて、静まり返った家で泣きそうになっていたけど、「おはよう、心春。ちゃんと起きた?」と彼からLINEが来ていた。彼は友達でも恋人でも、家族でもない。でも、そんな言葉じゃ言い表せないような存在で。そんなものじゃ埋められないものを埋めてくれていた。彼は、言葉に出来ない気持ちをいつだって共有してくれた。
彼と出会って、4年以上の月日が流れた。相変わらずライブ会場で会って、LINEをして。ずっとこのままこの関係が続くのだと思っていたのに、私はライブ会場で彼の彼女を見かけてしまった。彼は私に「彼女ができた」とは言わなかったけど、私はその事実を共通の友人から聞いていた。いつからか、お互い恋愛について触れないことが暗黙の了解だった。それでもLINEはしてくれていて変わらない日々を過ごしていた。
そのうち、彼と私が話していると彼の彼女が嫌がるようになった。彼はそのことを分かっていたけど、私と話すことは辞めなかった。彼が彼女に呼ばれても私と話していた時、彼女が苦しそうに地面で蹲った。彼が彼女の肩を抱えてその場を立ち去る姿を、私は見ていることしか出来なかった。彼は知らなかったと思うけど、その時彼女は私のことを睨んでいた。
それから私は「もう終わりにしよう」と彼に告げた。彼女がいるのだから、いつまでも彼に甘えていてはいけないと思った。耐えられなくなる前に、想いが溢れる前に、彼から離れようと思った。でも彼は、私から離れてくれなかった。優しい彼は、不安定な私を、寂しがりやな私を、放っておけなかったんだと思う。
ある日、お酒に酔った彼が電話をしてきた。「彼女が嫌がるからデートではコーヒーが飲めないんだ」「彼女の行きたいお店が高くて、月は金欠なんだ」「絵文字を入れないと彼女が怒るんだ」彼はそんな話をしていた。私は、大好きなコーヒーを飲んでいる彼が好きだった。私は、コンビニで買った安いアイスを半分こにして、彼と一緒に食べるのが好きだった。私は、びっくりマークの多いシンプルな彼のLINEが好きだった。私は彼のことが本当に好きだったんだと実感してしまった。私は、出会った時から彼が好きだったのかもしれないし、そうじゃなかったのかもしれない。私は再び彼に別れを告げた。
最後に、2人で水族館に行くことになった。最初で最後のデートだった。その日もやっぱり話が尽きなくて、ずっと笑い合っていた。あんなにも楽しい水族館は、初めてだった。あっという間に時間が過ぎて帰る時間になった。駅のホームで電車を待っている間、彼はやっぱり離れたくないと言った。私は「彼女さんに悪いよ」と笑って言った。彼は優しすぎるから彼女と別れられないんだ。と、彼との共通の友人から聞いたことがあった。彼の優しさは残酷だと思った。
電車が来るアナウンスが聞こえて、私は彼に手紙を渡した。今までの感謝を言葉にしたら泣いてしまいそうだから、手紙という逃げ道を作っていた。手紙を受け取った彼は、苦しそうに私を見つめていた。到着した電車に乗り、私は「バイバイ」と笑って彼に言った。ドアが閉まる時、彼が私の名前を呼んだ。彼が手を伸ばそうとしている。私は泣きそうになるのを我慢して、ドア越しの彼に「好きだったよ」と笑顔で言った。伝わったか、伝わらなかったかは分からない。彼の気持ちも、私の気持ちも、私たちは本当は分かっていた。分かっていたからこそ、直接「好き」を伝えなかった。
その日の夜はなぜか泣けなかった。自分で選んだ道なのに失ったものが大きすぎて。私はたぶん、彼がいなくても生きていける。でも、彼のいない世界で生きていても意味がないと思っていた。気付いたら朝になっていて、色々なことがどうでも良くて、私は川沿いを歩いていた。このまま飛び込もうか。それとも、知らない誰かに心の穴を埋めてもらおうか。呆然とそんなことを考えていたんだと思う。
その時、彼の声が聞こえた気がした。顔を上げると「心春!」と叫ぶ、彼の姿が見えた。どうして彼は、こんな時まで私を見つけてしまうのだろう。駆け寄ってくる彼に抱きつくことはもう出来ないのに、彼が愛しくてたまらなかった。なぜここにいるのか尋ねる前に、彼は手紙を差し出してきた。彼が私のために書いてくれた手紙だ。「オレの気持ち、心春に伝え切れてなくて。誰かに運んでもらうのは違う気がして、直接届けに来た」と彼は笑って言った。彼も会えると思っていなかったようで、私はやっぱり運命だと思ってしまった。私は彼に別れてほしいわけじゃない。彼の隣で同じものを見ていたかった。ただ、彼と一緒に笑っていたかった。彼は最後に私を抱きしめた。
彼の手紙には「ずっと心春のことが好きだった」と書いてあった。出会った時から、心春が何よりも大切だったのに、結果的に傷つけてしまった、と。謝罪の文や、今までの感謝が記されていた。彼は、私が寂しくないように手紙を書いてくれたんだと思う。私は、彼のどうしようもない優しさも含めて好きだった。
それ以来、彼とは連絡を取っていない。ライブ会場で見つけても、会うことはないだろう。彼は、私の人生には不可欠だった。好きという感情の前に、大切だった。何よりも、誰よりも、幸せになってほしかった。彼は私にとってカッコ悪いスーパーマンで、好きなことを忘れるくらい、大切だった。言葉じゃ言い表せない関係。共有できる存在。お互いが、お互いの気持ちを分かり合える。嫌なことも、嬉しいことも、自然と分かる。友達でも、恋人でも、家族でもなかったけれど、きっとそれ以上の存在だった。
私はもう、彼の名前を呼べない。彼に抱きつくことも、話すことも出来ない。彼が今、何をして、何を想っているのか。私にはもう、分からない。彼と私の関係に名前があれば、今も隣にいられたのかもしれない。それでも、彼が幸せならそれで良い。彼が笑っていれば、彼がくれた思い出があれば、私はきっと、生きていける気がする。