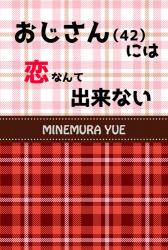ランチの少し後、少女の部屋にまたミラルカが訪ねてきた。
「お庭に行きますか?」
少女はつい嫌な想像をして体が強張った。庭に行くことは聞いていたが、いざファビオに会うと思うと足が少し震えた。
あれだけ散々ファビオの性格について聞いたというのに情けない。だが、ミラルカが一緒にいるのだ。きっとなんとかなる。自分に言い聞かせ、怖気付く足を奮い立たせた。
庭に出るのは初めてではないが、以前見た時は朝方で霧が濃く、逃げ出そうとしていためまともに見ていなかった。
侯爵邸の庭は見た事がないくらい綺麗で、色んな花が咲き誇っていた。
そこらじゅうに部屋に飾られた花と同じ形の花が咲いている。アーチに巻き付いた蔦には大きな星のような花が咲き、庭園にある噴水からは清涼な水が流れ出ていた。
────素敵なお庭。声が出たのなら思わずそう言っていただろう。
辺りを見回していると、少し向こうに花に埋もれていた人影を見つけた。
「ファビオ」
ミラルカが呼ぶとその影が振り向いた。まだあどけない顔をした少年がそこにいた。
ファビオはミラルカから聞いていた通り、同じぐらいの歳の頃だ。背丈が小さく、バラに埋もれて顔の半分が見えなかった。
ファビオはゆっくりちこちらに近づいて来た。少女はついミラルカの服の袖を握った。
「えっと、こんにちは」
ファビオが目の前まで来た時、少女は体の半分をミラルカの後ろに隠していた。怖くない。怖くないと言い聞かせても、体はどうにもいうことを聞かなかった。
「この子がファビオですよ。言ったとおり、小さい子でしょう?」
「ミラルカさん、そういう教え方はしないでくださいよ。君は……名前は?」
「そういえば聞いていなかったわね」
少女は持っていた紙に『しらない』と書いた。
「知らない?」
ファビオは不思議そうな顔をした。
人間は普通名前がある。少女も、かつては名前があった────のかもしれない。
少女は名前があった頃のことを覚えていなかった。というのも、物心ついた頃にはすでに閉じ込められた生活を送っており、「お前」以外の名前で呼ばれたことがなかった。
何年もそんな生活を続けていたから、名前がどういうものかさえ忘れてしまった。
「まぁ、いいじゃない。それよりファビオ、バラ園を見せてあげて」
「うん。えっと……この庭園にはいろんな色んな国のバラが植えてあるんだ」
ファビオは庭にあるバラをひとつひとつ説明した。
最初は怖いと思っていたが、綺麗な花は自然と嫌なことを忘れさせてくれた。話を聞いているうちにだんだんとファビオにも慣れてきた。
ファビオはミラルカと同じで怖くない。怒鳴ったりもしない。触ってこない。本当に心の優しい男の子なんだと分かった。
『せんぶファビオさんがおせわをしているんですか?』
「うん、そうだよ。大変だけど、綺麗に咲いたら嬉しいからね」
『またみにきてもいいですか?』
「好きなだけ見ていいよ。言ってくれたら好きな花部屋に持って帰っていいから」
ファビオははにかんだような笑顔を向けた。
まだ子供のようなあどけない笑顔。屈託のない純粋な笑み。信じろ、などと言われずとも自然とそう思える。
この日少女は少しだけ人に心を開いた。
「お庭に行きますか?」
少女はつい嫌な想像をして体が強張った。庭に行くことは聞いていたが、いざファビオに会うと思うと足が少し震えた。
あれだけ散々ファビオの性格について聞いたというのに情けない。だが、ミラルカが一緒にいるのだ。きっとなんとかなる。自分に言い聞かせ、怖気付く足を奮い立たせた。
庭に出るのは初めてではないが、以前見た時は朝方で霧が濃く、逃げ出そうとしていためまともに見ていなかった。
侯爵邸の庭は見た事がないくらい綺麗で、色んな花が咲き誇っていた。
そこらじゅうに部屋に飾られた花と同じ形の花が咲いている。アーチに巻き付いた蔦には大きな星のような花が咲き、庭園にある噴水からは清涼な水が流れ出ていた。
────素敵なお庭。声が出たのなら思わずそう言っていただろう。
辺りを見回していると、少し向こうに花に埋もれていた人影を見つけた。
「ファビオ」
ミラルカが呼ぶとその影が振り向いた。まだあどけない顔をした少年がそこにいた。
ファビオはミラルカから聞いていた通り、同じぐらいの歳の頃だ。背丈が小さく、バラに埋もれて顔の半分が見えなかった。
ファビオはゆっくりちこちらに近づいて来た。少女はついミラルカの服の袖を握った。
「えっと、こんにちは」
ファビオが目の前まで来た時、少女は体の半分をミラルカの後ろに隠していた。怖くない。怖くないと言い聞かせても、体はどうにもいうことを聞かなかった。
「この子がファビオですよ。言ったとおり、小さい子でしょう?」
「ミラルカさん、そういう教え方はしないでくださいよ。君は……名前は?」
「そういえば聞いていなかったわね」
少女は持っていた紙に『しらない』と書いた。
「知らない?」
ファビオは不思議そうな顔をした。
人間は普通名前がある。少女も、かつては名前があった────のかもしれない。
少女は名前があった頃のことを覚えていなかった。というのも、物心ついた頃にはすでに閉じ込められた生活を送っており、「お前」以外の名前で呼ばれたことがなかった。
何年もそんな生活を続けていたから、名前がどういうものかさえ忘れてしまった。
「まぁ、いいじゃない。それよりファビオ、バラ園を見せてあげて」
「うん。えっと……この庭園にはいろんな色んな国のバラが植えてあるんだ」
ファビオは庭にあるバラをひとつひとつ説明した。
最初は怖いと思っていたが、綺麗な花は自然と嫌なことを忘れさせてくれた。話を聞いているうちにだんだんとファビオにも慣れてきた。
ファビオはミラルカと同じで怖くない。怒鳴ったりもしない。触ってこない。本当に心の優しい男の子なんだと分かった。
『せんぶファビオさんがおせわをしているんですか?』
「うん、そうだよ。大変だけど、綺麗に咲いたら嬉しいからね」
『またみにきてもいいですか?』
「好きなだけ見ていいよ。言ってくれたら好きな花部屋に持って帰っていいから」
ファビオははにかんだような笑顔を向けた。
まだ子供のようなあどけない笑顔。屈託のない純粋な笑み。信じろ、などと言われずとも自然とそう思える。
この日少女は少しだけ人に心を開いた。