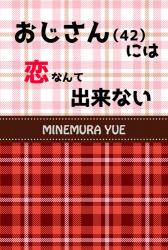翌朝、怒涛のパーティーから解放されたミラルカが疲れた顔でアーリー・モーニングティーを持ってきた。
この屋敷で暮らしてそこそこ経つが、ミラルカのこんな疲れた顔は初めて見る。
だが無理もない、屋敷の従者は多くはない。それなのにあの数の招待客をもてなしたのだから疲れるのも当然だ。
「ごめんなさいエル様。昨日はとても手が回らなくて────色々と困ったでしょう」
ポットからティーカップに移された紅茶が湯気を立てる。
エルは気にしてないと首を横に振った。
「お屋敷にあれだけのお客様がいらっしゃるのはなかなか珍しいことなのですよ。私も久しぶりで疲れたのでしょうね」
ミラルカはこの屋敷で働いて長い。それこそ、ネリウスが幼い頃からここにいる。ならば、アレクシアやフォーミュラー公爵のことも知っているだろうか。
エルはごくりと唾を飲み込んだ。こんなことを聞くのは差し出がましい気もするが、どうしても気になる。
『アレクシア様はネリウス様と親しい方なのですか』
ノートに書かれた文字を見て、ミラルカは気まずそうに目を逸らした。
幼馴染だとアレクシアは言っていたが、雰囲気が妙だった。フォーミュラー公爵の態度も。
「エル様……あの、お気を悪くなさらないで下さいね。旦那様がお好きなのはエル様だけですから」
ミラルカは言い訳するように取り繕う。だが、その言い方が余計に疑念を煽った。
一呼吸おいて、ミラルカは重い口を開いた。
「アレクシア様は……以前、旦那様の許嫁だった方です」
ミラルカの言葉を聞いて、ないはずの言葉を失った。
許嫁────。だからあの二人はあんなに親しそうに話していたのだ。横にいた彼女の父親も、フォーミュラー公爵も、だからだ。
全てのピースが繋がって、エルは納得したと同時に大きなショックを受けた。二人は貴族だ。上流階級のことはよく知らないが、世間知らずの自分でも分かる。力の強いもの同士が結びつき合うのは必須だ。
「大旦那様が生きていた頃にそういうお約束をなさいました。ですが、大旦那様も大奥様も亡くなられて、縁談は頓挫してなくなったと聞いています。フォーミュラー公爵は大旦那様と親しい方でしたので、パーティに招待したのですが……」
ミラルカの話を聞きながら、エルは遠くを見つめた。
本当はなんとなく、そうだと思っていた。許嫁だったということは、もしネリウスの両親が亡くならなければそのまま結婚していたのだろう。
ネリウスの気持ちを疑うわけではない。いつだってネリウスの言葉を信じている。けれど────自分は本当にここにいてもいいのだろうか。
「エル様……悲しまないで下さい。昔の話です。旦那様は元々色恋の類には興味がなくて、その話が出た時も無関心でした。今は本当にエル様のことを愛しているのですよ」
ミラルカは落ち込んでいると思ってフォローしたのだろう。
分かっている。昨日の夜も、ネリウスは自分がどこかへ行かないか、嫌いにならないかと不安がっていた。
ネリウスは自分を心から愛してくれている。なのにどうして、こんなに不安になるのだろう。大丈夫なはずなのに胸のざわめきが治まらなかった。
この屋敷で暮らしてそこそこ経つが、ミラルカのこんな疲れた顔は初めて見る。
だが無理もない、屋敷の従者は多くはない。それなのにあの数の招待客をもてなしたのだから疲れるのも当然だ。
「ごめんなさいエル様。昨日はとても手が回らなくて────色々と困ったでしょう」
ポットからティーカップに移された紅茶が湯気を立てる。
エルは気にしてないと首を横に振った。
「お屋敷にあれだけのお客様がいらっしゃるのはなかなか珍しいことなのですよ。私も久しぶりで疲れたのでしょうね」
ミラルカはこの屋敷で働いて長い。それこそ、ネリウスが幼い頃からここにいる。ならば、アレクシアやフォーミュラー公爵のことも知っているだろうか。
エルはごくりと唾を飲み込んだ。こんなことを聞くのは差し出がましい気もするが、どうしても気になる。
『アレクシア様はネリウス様と親しい方なのですか』
ノートに書かれた文字を見て、ミラルカは気まずそうに目を逸らした。
幼馴染だとアレクシアは言っていたが、雰囲気が妙だった。フォーミュラー公爵の態度も。
「エル様……あの、お気を悪くなさらないで下さいね。旦那様がお好きなのはエル様だけですから」
ミラルカは言い訳するように取り繕う。だが、その言い方が余計に疑念を煽った。
一呼吸おいて、ミラルカは重い口を開いた。
「アレクシア様は……以前、旦那様の許嫁だった方です」
ミラルカの言葉を聞いて、ないはずの言葉を失った。
許嫁────。だからあの二人はあんなに親しそうに話していたのだ。横にいた彼女の父親も、フォーミュラー公爵も、だからだ。
全てのピースが繋がって、エルは納得したと同時に大きなショックを受けた。二人は貴族だ。上流階級のことはよく知らないが、世間知らずの自分でも分かる。力の強いもの同士が結びつき合うのは必須だ。
「大旦那様が生きていた頃にそういうお約束をなさいました。ですが、大旦那様も大奥様も亡くなられて、縁談は頓挫してなくなったと聞いています。フォーミュラー公爵は大旦那様と親しい方でしたので、パーティに招待したのですが……」
ミラルカの話を聞きながら、エルは遠くを見つめた。
本当はなんとなく、そうだと思っていた。許嫁だったということは、もしネリウスの両親が亡くならなければそのまま結婚していたのだろう。
ネリウスの気持ちを疑うわけではない。いつだってネリウスの言葉を信じている。けれど────自分は本当にここにいてもいいのだろうか。
「エル様……悲しまないで下さい。昔の話です。旦那様は元々色恋の類には興味がなくて、その話が出た時も無関心でした。今は本当にエル様のことを愛しているのですよ」
ミラルカは落ち込んでいると思ってフォローしたのだろう。
分かっている。昨日の夜も、ネリウスは自分がどこかへ行かないか、嫌いにならないかと不安がっていた。
ネリウスは自分を心から愛してくれている。なのにどうして、こんなに不安になるのだろう。大丈夫なはずなのに胸のざわめきが治まらなかった。