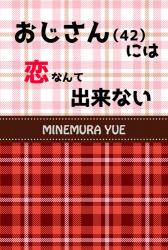ネリウスはアレクシアの手を引きながらも、今すぐに戻ってエルを抱きしめたい気分だった。
エルは「いいですよ」と頷いたが、悲しんでいることは分かっていた。
ずっと一緒にいると、エスコートすると最初に言ったのは自分なのに、どうしてその約束を破ってしまったのか。
ネリウスが離れてすぐに、他の男達が待っていたと言わんばかりにエルに近づいた。エルは返事も返すことが出来ずにうろたえている。
ミラルカが気づいてフォローを入れたようだが、男はエルの手を引いてダンスホールの中央へ向かってしまった。
────俺のエルに触るな。そう何度叫びたかったか。
咄嗟に「エルの対人恐怖症が治らなければよかった」なんて考えてしまった。酷い男だ。残酷なことだと分かっているのに、そんなことまで考えている。
けれど他の男の手が、指が、唇が、エルの身体に触れる。その手に指を絡めて、手の甲に口付けすると、今すぐにでも駆け寄って引き剥がしてしまいたい衝動に駆られる。
「ネリウス、どうしたの?」
「……ああ」
「まるで心ここにあらずよ。彼女が心配?」
「いや……」
「いきなり私が来て驚いたでしょう。私も来るつもりじゃなかったんだけど、父に言われて仕方なく来たの」
アレクシアは目を伏せて苛立たしげに呟いた。
「ネリウス、今のうちに言っておくわ。お父様、まだあの話を諦めてないみたいよ」
────あの話。それを聞いて、ネリウスはつい足を止めた。
「あの話はもう、うちの両親が死んで立ち消えしたはずだろう」
「さあ、お父様はそう思っていないみたいよ。だから私まで誘ってここに来たんでしょう」
「お前はどうなんだ」
「私は、お父様にそうだと言われたらそうするしかないわ。そういう家柄だから……」
アレクシアは諦めたように言った。
アレクシアとは小さいからの付き合いだ。物心つくくらいまでは一緒に遊んだりもしていたが、ここしばらくは会うことも喋ることもしていなかった。
両親が亡くなりフォーミュラー家との繋がりも薄くなった。だからネリウスも必要以上に関わるつもりはなかった。他の貴族はそうではないが、権力に集る男とは思われたくない。両親は親しくしていたが、手を借りるつもりは毛頭なかった。
アレクシアは公爵家の娘で、デビューしてからは社交活動に忙しい。うまくやっていると思っていたが、この顔を見る限りそうではないようだ。
しかし、困ったことになった。ネリウスは先程アレクシアに言われたことを思い出した。
もしアレクシアが言ったことが本当なら自分は────。
エルは「いいですよ」と頷いたが、悲しんでいることは分かっていた。
ずっと一緒にいると、エスコートすると最初に言ったのは自分なのに、どうしてその約束を破ってしまったのか。
ネリウスが離れてすぐに、他の男達が待っていたと言わんばかりにエルに近づいた。エルは返事も返すことが出来ずにうろたえている。
ミラルカが気づいてフォローを入れたようだが、男はエルの手を引いてダンスホールの中央へ向かってしまった。
────俺のエルに触るな。そう何度叫びたかったか。
咄嗟に「エルの対人恐怖症が治らなければよかった」なんて考えてしまった。酷い男だ。残酷なことだと分かっているのに、そんなことまで考えている。
けれど他の男の手が、指が、唇が、エルの身体に触れる。その手に指を絡めて、手の甲に口付けすると、今すぐにでも駆け寄って引き剥がしてしまいたい衝動に駆られる。
「ネリウス、どうしたの?」
「……ああ」
「まるで心ここにあらずよ。彼女が心配?」
「いや……」
「いきなり私が来て驚いたでしょう。私も来るつもりじゃなかったんだけど、父に言われて仕方なく来たの」
アレクシアは目を伏せて苛立たしげに呟いた。
「ネリウス、今のうちに言っておくわ。お父様、まだあの話を諦めてないみたいよ」
────あの話。それを聞いて、ネリウスはつい足を止めた。
「あの話はもう、うちの両親が死んで立ち消えしたはずだろう」
「さあ、お父様はそう思っていないみたいよ。だから私まで誘ってここに来たんでしょう」
「お前はどうなんだ」
「私は、お父様にそうだと言われたらそうするしかないわ。そういう家柄だから……」
アレクシアは諦めたように言った。
アレクシアとは小さいからの付き合いだ。物心つくくらいまでは一緒に遊んだりもしていたが、ここしばらくは会うことも喋ることもしていなかった。
両親が亡くなりフォーミュラー家との繋がりも薄くなった。だからネリウスも必要以上に関わるつもりはなかった。他の貴族はそうではないが、権力に集る男とは思われたくない。両親は親しくしていたが、手を借りるつもりは毛頭なかった。
アレクシアは公爵家の娘で、デビューしてからは社交活動に忙しい。うまくやっていると思っていたが、この顔を見る限りそうではないようだ。
しかし、困ったことになった。ネリウスは先程アレクシアに言われたことを思い出した。
もしアレクシアが言ったことが本当なら自分は────。