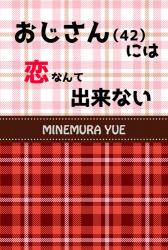ジャックと分かれた後、ネリウスとミラルカは別の場所を探した。
時間が経ち、霧は次第に薄くなってきて、視界の先が見えるようになった。
「いつかは見つかると思いますけど、あの子大丈夫でしょうか……」
「医者を呼べ」
「え?」
ネリウスの視線を捉えていたのは数十メートル先に倒れていた少女だった。間も無く事態に気付いたミラルカが声をあげた。
「ああっ」
「ミラルカ、あいつ等に知らせろ。医者を呼べ」
「は、はいっ」
ミラルカはすぐに屋敷へと向かった。ネリウスは倒れていた少女の手を取り、脈を測った。正常に動いている。どうやら生きているようだ。
だが、少女はぐったりとした様子で横たわっていた。
顔色が悪い。額に手を当てると熱かった。外を走り回ったせいで肺炎がぶりかえしてしまったのだろうか。
ネリウスは少女を抱き抱え、揺らさないよう早歩きしながら屋敷へ急いだ。
その後少女は再び医者の診察を受けた。
医者からはきつく、無理をさせないようにと言われた。元々こじらせかけた肺炎が悪化しているそうだ。深い霧の中をあの体で歩き回ったのだ。無理もない。
「私何かしてしまったかしら……。気をつけたつもりだったんですけれど」
ミラルカは少女が逃げ出したのは自分の責任だと深く反省した。
「さぁな……だが、こんな状態じゃ何をしても脅威にしか見えないかもしれないな」
「私……ちょっと自信がなくなりました」
「この屋敷で女はお前しかいないんだ。お前がやらないなら誰がやるんだ」
そこまで言われたらミラルカも断れなかった。嫌ではない。ただ虐待された子供の世話などしたことがないためどうしたらいいか分からなかった。
せっかく保護したのに逃げ出すなんて、きっと今までよほど怖い思いをしていたのだろう。このまま放っておくのはあまりにも気の毒だ。
「……やります」
「他の奴らには俺から説明しておこう。お前はそいつに付いてやれ」
ミラルカは少女の看病を続けた。温めたからか、少女の顔色は少し赤みが差してきた。だが、それでもやはり白い。
少女の顔を眺めていると、ふと、少女の瞳が数度瞬いた。鮮やかなグリーンの瞳がミラルカを捉えた。
少女はミラルカに驚いたのか、ベッドから抜け出そうと激しく動いた。
だが、熱があるためかすぐにふらついて床に倒れてしまった。
「大人しくしていて下さい! あなたは病気なんですよ! 悪化してしまったらどうするんですかっ」
だが少女はそれでも逃げ出そうとしているのか、ベッドから落ちたあと壁に寄り添うようにして怯えた瞳でミラルカを見た。
怖がらせてしまったようだ。ミラルカは怯える少女に少しずつ近寄って、目線を合わせるようにしゃがんだ。
「ここにはあなたが怖がるものなんて何もありません。ここにいる人達は、あなたを傷つけることはありません。だから安心してください」
子供を諭すような口調で、ミラルカはゆっくりと少女の手を握った。
「あなたをここに閉じ込めるつもりはありません。外に出たいなら出ても構いません。だけどまだ病気が治ってないから、出るならちゃんと治してからにして下さい」
ミラルカの気持ちが少しは伝わったのか、少女は先ほどよりも少し大人しくなった。
分からない事だらけで不安だったのだろう。突然連れてこられた屋敷でいきなり世話をされて、ラッキーだとは思えなかったのかもしれない。今までの彼女の待遇を考えれば当然のことだ。
「さあ、ベッドに横になってください。体が冷えてしまいますから」
少女はおずおずと立ち上がり、隠れるようにベッドの中に入った。
ミラルカの方を何か言いたげな様子で見つめている。やがてサイドテーブルに置かれたノートとペンに気付いたのか、確認するようにミラルカの方を見てそれを手に取った。
少女は文字を書いた。だが、字がめちゃくちゃだ。スペルも間違えている。恐らくきちんとした文字を習っていなかったのだろう。
ミラルカはノートに書かれた文字を必死で読み解いた。
『ここはどこですか』、そう書かれているようだった。
「ここは街外れにあるベッカー侯爵家のお屋敷です。旦那様が雨の中倒れていたあなたを連れて帰ってきたのです。それであなたを屋敷で看病することになりました」
少女は説明を聞いて納得したようだった。
だがまたしても少女の腹の虫が鳴った。ミラルカはくすっと笑った。
「朝食をお召し上がりになっていらっしゃらないんですものね。今すぐ持って参ります」
ミラルカは立ち上がって、釘をさすように少女に言った。
「抜け出しちゃダメですよ?」
すぐにキッチンに向かい、シェフに朝食を作り直すよう言いつけた。
ミラルカはただのメイドだが、この屋敷で働いて長い。実質、使用人の中では彼女がナンバーワンだと囁かれていた。
ネリウスは低血圧で朝が弱いため、この時間でも普段のキッチンはのんびりしているのだが、今日は違う。
シェフは再び叩き起こされ、フライパンを握る羽目になった。
病人用の食事はほとんど作らないもの、さすがシェフなだけあって注文通りの料理が仕上がった。
ミラルカはそれを持って再び部屋に戻った。少女は今度こそは大人しくベッドの中にいたようだ。ミラルカは思わず安堵した。
「さ、どうぞ」
料理を見て少女は目を丸くしていた。クリームの中に野菜を細かく刻んだものを入れて煮込んだ特製スープだ。
ミラルカも一口味見してみたが、晩餐に出しても問題ない。病人食とは思えない素晴らしい出来栄えだ。
まだ湯気の立ち上るそれをひとさじすくって少女に向けた。少女は遠慮がちにそれを口にした。
「……どうですか?」
少女はびっくりしたような目をしたあと、慌てて紙に「おいしいです」と書いた。驚いた様を見る限り、スープが気に入ったようだ。
「よかった。おかわりはいくらでもありますからね」
少女はまともな食事もしていなかったのか、食べながら涙を流していた。
傷を見てまともな扱いを受けていないことは察していたが、食べ物すら与えられていなかったのだろう。少女の体が痩せ細っているところを見れば一目瞭然だ。つられてミラルカも涙ぐんだ。
この少女のためにできることをしてやろうと決心した。
時間が経ち、霧は次第に薄くなってきて、視界の先が見えるようになった。
「いつかは見つかると思いますけど、あの子大丈夫でしょうか……」
「医者を呼べ」
「え?」
ネリウスの視線を捉えていたのは数十メートル先に倒れていた少女だった。間も無く事態に気付いたミラルカが声をあげた。
「ああっ」
「ミラルカ、あいつ等に知らせろ。医者を呼べ」
「は、はいっ」
ミラルカはすぐに屋敷へと向かった。ネリウスは倒れていた少女の手を取り、脈を測った。正常に動いている。どうやら生きているようだ。
だが、少女はぐったりとした様子で横たわっていた。
顔色が悪い。額に手を当てると熱かった。外を走り回ったせいで肺炎がぶりかえしてしまったのだろうか。
ネリウスは少女を抱き抱え、揺らさないよう早歩きしながら屋敷へ急いだ。
その後少女は再び医者の診察を受けた。
医者からはきつく、無理をさせないようにと言われた。元々こじらせかけた肺炎が悪化しているそうだ。深い霧の中をあの体で歩き回ったのだ。無理もない。
「私何かしてしまったかしら……。気をつけたつもりだったんですけれど」
ミラルカは少女が逃げ出したのは自分の責任だと深く反省した。
「さぁな……だが、こんな状態じゃ何をしても脅威にしか見えないかもしれないな」
「私……ちょっと自信がなくなりました」
「この屋敷で女はお前しかいないんだ。お前がやらないなら誰がやるんだ」
そこまで言われたらミラルカも断れなかった。嫌ではない。ただ虐待された子供の世話などしたことがないためどうしたらいいか分からなかった。
せっかく保護したのに逃げ出すなんて、きっと今までよほど怖い思いをしていたのだろう。このまま放っておくのはあまりにも気の毒だ。
「……やります」
「他の奴らには俺から説明しておこう。お前はそいつに付いてやれ」
ミラルカは少女の看病を続けた。温めたからか、少女の顔色は少し赤みが差してきた。だが、それでもやはり白い。
少女の顔を眺めていると、ふと、少女の瞳が数度瞬いた。鮮やかなグリーンの瞳がミラルカを捉えた。
少女はミラルカに驚いたのか、ベッドから抜け出そうと激しく動いた。
だが、熱があるためかすぐにふらついて床に倒れてしまった。
「大人しくしていて下さい! あなたは病気なんですよ! 悪化してしまったらどうするんですかっ」
だが少女はそれでも逃げ出そうとしているのか、ベッドから落ちたあと壁に寄り添うようにして怯えた瞳でミラルカを見た。
怖がらせてしまったようだ。ミラルカは怯える少女に少しずつ近寄って、目線を合わせるようにしゃがんだ。
「ここにはあなたが怖がるものなんて何もありません。ここにいる人達は、あなたを傷つけることはありません。だから安心してください」
子供を諭すような口調で、ミラルカはゆっくりと少女の手を握った。
「あなたをここに閉じ込めるつもりはありません。外に出たいなら出ても構いません。だけどまだ病気が治ってないから、出るならちゃんと治してからにして下さい」
ミラルカの気持ちが少しは伝わったのか、少女は先ほどよりも少し大人しくなった。
分からない事だらけで不安だったのだろう。突然連れてこられた屋敷でいきなり世話をされて、ラッキーだとは思えなかったのかもしれない。今までの彼女の待遇を考えれば当然のことだ。
「さあ、ベッドに横になってください。体が冷えてしまいますから」
少女はおずおずと立ち上がり、隠れるようにベッドの中に入った。
ミラルカの方を何か言いたげな様子で見つめている。やがてサイドテーブルに置かれたノートとペンに気付いたのか、確認するようにミラルカの方を見てそれを手に取った。
少女は文字を書いた。だが、字がめちゃくちゃだ。スペルも間違えている。恐らくきちんとした文字を習っていなかったのだろう。
ミラルカはノートに書かれた文字を必死で読み解いた。
『ここはどこですか』、そう書かれているようだった。
「ここは街外れにあるベッカー侯爵家のお屋敷です。旦那様が雨の中倒れていたあなたを連れて帰ってきたのです。それであなたを屋敷で看病することになりました」
少女は説明を聞いて納得したようだった。
だがまたしても少女の腹の虫が鳴った。ミラルカはくすっと笑った。
「朝食をお召し上がりになっていらっしゃらないんですものね。今すぐ持って参ります」
ミラルカは立ち上がって、釘をさすように少女に言った。
「抜け出しちゃダメですよ?」
すぐにキッチンに向かい、シェフに朝食を作り直すよう言いつけた。
ミラルカはただのメイドだが、この屋敷で働いて長い。実質、使用人の中では彼女がナンバーワンだと囁かれていた。
ネリウスは低血圧で朝が弱いため、この時間でも普段のキッチンはのんびりしているのだが、今日は違う。
シェフは再び叩き起こされ、フライパンを握る羽目になった。
病人用の食事はほとんど作らないもの、さすがシェフなだけあって注文通りの料理が仕上がった。
ミラルカはそれを持って再び部屋に戻った。少女は今度こそは大人しくベッドの中にいたようだ。ミラルカは思わず安堵した。
「さ、どうぞ」
料理を見て少女は目を丸くしていた。クリームの中に野菜を細かく刻んだものを入れて煮込んだ特製スープだ。
ミラルカも一口味見してみたが、晩餐に出しても問題ない。病人食とは思えない素晴らしい出来栄えだ。
まだ湯気の立ち上るそれをひとさじすくって少女に向けた。少女は遠慮がちにそれを口にした。
「……どうですか?」
少女はびっくりしたような目をしたあと、慌てて紙に「おいしいです」と書いた。驚いた様を見る限り、スープが気に入ったようだ。
「よかった。おかわりはいくらでもありますからね」
少女はまともな食事もしていなかったのか、食べながら涙を流していた。
傷を見てまともな扱いを受けていないことは察していたが、食べ物すら与えられていなかったのだろう。少女の体が痩せ細っているところを見れば一目瞭然だ。つられてミラルカも涙ぐんだ。
この少女のためにできることをしてやろうと決心した。