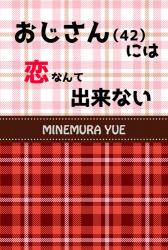エルは朝から部屋に引きこもっていた。窓の外を見ることさえしなかった。
外を眺めればまたバラ園に行きたくなってしまう。ネリウスの姿を探そうとしてしまう。いっそのこと、ずっとこの部屋の中で過ごす方がいいのかもしれないとさえ思っていた。
目が覚めても昨日のことは忘れていなかった。現実に起きたことだと理解はしている。
だけどそれが、自分の頭の中ではまるで夢のようで────現実なのに現実的に考えられなかった。
あの思い出は忘れないといけない。この気持ちはきっと、吊り橋効果のようなものだと。
昨日はとても緊張していたから、ネリウスがとても頼りに見えただけ。無理やりな言い訳に自分でも笑ってしまう。
やがてしばらくして、ミラルカが朝食を持ってきた。
椅子に座って本を読んでいたエルの前に、カトラリーや食器を置いていく。
元気はないが、お腹だけは正直なもので、目の前に料理を出されるとお腹がすいてきた。
「今日は軽めの食事に致しました。デザートもございますから、仰っていただければすぐにお持ちします」
ミラルカはいつもと同じように、エルのそばに立ってニッコリと微笑む。
だけどそれが、余計に不安を煽った。こんな自分を見透かしていやしないだろうか。ミラルカはここにきた時から優しく接してくれた一番の理解者だ。
だけど、それもネリウスに仕えるからこそで、もし自分がこんな気持ちを抱いていることを知ったら────。そう思うと身がすくむ思いがした。
「エル様? お食事が冷めてしまいますよ?」
ミラルカは心配そうな顔で覗き込んだ。その顔を見ると罪悪感が湧く。
エルは居心地が悪くて顔を背けた。ミラルカはそんなエルを見ると、頭を下げて席を外した。
────いつまで私はここにいられるんだろう。
ふと、そう思った。
たまたま倒れていたところを拾われ、ネリウス達の好意でここに置いてもらっているが、本来ならば元気になったのだから出て行かなくてはならない。
それなのにどうして今まで我が物顔でここにいたのだろう。当たり前のように過ごしていた。おまけに社交界まで連れて行ってもらって、身の程知らずにもほどがある。
少し経って、ミラルカが部屋に戻ってきた。
手に乗せたトレーには、マグカップが置かれていて甘い香りを放っていた。
「具合が悪いようでしたらこれをどうぞ。ホットショコラですよ」
それは、チョコレートの香りがした。初めて見る飲み物だった。
「旦那様が、今日は冷えるからこれを持って行けと。エル様に無理をさせたのではないかと心配してらっしゃいました。早くお元気になって、旦那様にいつもの元気なお姿を見せて差し上げてくださいね」
────ネリウス様が……?
自分がどう思っているかは、まだネリウスの耳に入っていない。ミラルカにも気付かれていない。
エルは少しホッとして、飲み物に口をつけた。甘い。だけどどこか苦かった。
そうだ、自分はネリウスの母親に似ているから────だから置いてもらえているだけだ。だから優しくしてもらえる。それを履き違えちゃいけない。
愛おしい優しささえもそんなふうに思わなければならないなんて残酷だ。けれど嫌われて、ここを出ていけと言われるよりはいい。
それから数週間が経ち、いつもの日々が戻ってきた。
あの夢のような出来事も、ネリウスと顔さえ合わせなければ段々と記憶の中から消えていった。
時折顔を合わせても、エルは呪文のように自分に言い聞かせた。
「私はネリウス様の母親の代わり」だと。そう思えば無駄なことを考えずに済んだ。
冷静に、だけど冷めた心で毎日を過ごした。
外を眺めればまたバラ園に行きたくなってしまう。ネリウスの姿を探そうとしてしまう。いっそのこと、ずっとこの部屋の中で過ごす方がいいのかもしれないとさえ思っていた。
目が覚めても昨日のことは忘れていなかった。現実に起きたことだと理解はしている。
だけどそれが、自分の頭の中ではまるで夢のようで────現実なのに現実的に考えられなかった。
あの思い出は忘れないといけない。この気持ちはきっと、吊り橋効果のようなものだと。
昨日はとても緊張していたから、ネリウスがとても頼りに見えただけ。無理やりな言い訳に自分でも笑ってしまう。
やがてしばらくして、ミラルカが朝食を持ってきた。
椅子に座って本を読んでいたエルの前に、カトラリーや食器を置いていく。
元気はないが、お腹だけは正直なもので、目の前に料理を出されるとお腹がすいてきた。
「今日は軽めの食事に致しました。デザートもございますから、仰っていただければすぐにお持ちします」
ミラルカはいつもと同じように、エルのそばに立ってニッコリと微笑む。
だけどそれが、余計に不安を煽った。こんな自分を見透かしていやしないだろうか。ミラルカはここにきた時から優しく接してくれた一番の理解者だ。
だけど、それもネリウスに仕えるからこそで、もし自分がこんな気持ちを抱いていることを知ったら────。そう思うと身がすくむ思いがした。
「エル様? お食事が冷めてしまいますよ?」
ミラルカは心配そうな顔で覗き込んだ。その顔を見ると罪悪感が湧く。
エルは居心地が悪くて顔を背けた。ミラルカはそんなエルを見ると、頭を下げて席を外した。
────いつまで私はここにいられるんだろう。
ふと、そう思った。
たまたま倒れていたところを拾われ、ネリウス達の好意でここに置いてもらっているが、本来ならば元気になったのだから出て行かなくてはならない。
それなのにどうして今まで我が物顔でここにいたのだろう。当たり前のように過ごしていた。おまけに社交界まで連れて行ってもらって、身の程知らずにもほどがある。
少し経って、ミラルカが部屋に戻ってきた。
手に乗せたトレーには、マグカップが置かれていて甘い香りを放っていた。
「具合が悪いようでしたらこれをどうぞ。ホットショコラですよ」
それは、チョコレートの香りがした。初めて見る飲み物だった。
「旦那様が、今日は冷えるからこれを持って行けと。エル様に無理をさせたのではないかと心配してらっしゃいました。早くお元気になって、旦那様にいつもの元気なお姿を見せて差し上げてくださいね」
────ネリウス様が……?
自分がどう思っているかは、まだネリウスの耳に入っていない。ミラルカにも気付かれていない。
エルは少しホッとして、飲み物に口をつけた。甘い。だけどどこか苦かった。
そうだ、自分はネリウスの母親に似ているから────だから置いてもらえているだけだ。だから優しくしてもらえる。それを履き違えちゃいけない。
愛おしい優しささえもそんなふうに思わなければならないなんて残酷だ。けれど嫌われて、ここを出ていけと言われるよりはいい。
それから数週間が経ち、いつもの日々が戻ってきた。
あの夢のような出来事も、ネリウスと顔さえ合わせなければ段々と記憶の中から消えていった。
時折顔を合わせても、エルは呪文のように自分に言い聞かせた。
「私はネリウス様の母親の代わり」だと。そう思えば無駄なことを考えずに済んだ。
冷静に、だけど冷めた心で毎日を過ごした。