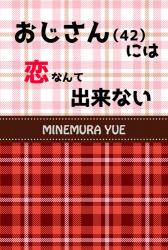エルは慌ててネリウスから視線を逸らした。
胸が詰まったような感覚がして苦しい。足と手ばかりが動いて、ネリウスの顔を見ることが出来ない。
練習していた時もそんなことがあった。目があって、お互いに動けなくなったことが────。
本当は、ずっとその瞳を見ていたい。そう思っているのに体が言うことをきかない。
掌の温度も。腰に回された手も。近づいた時に僅かに触れた胸からも────鼓動が伝わってくる。
それはけして緩やかではない。急いで駆けてきた後のように早いものだ。ネリウスも緊張しているのだろうか。
エルはその鼓動の意味を確かめたくなって、もう一度勇気を出してネリウスの瞳に視線を合わせた。
お互いこんなに近くで見つめ合うのは何度目だろうか。時が止まったかのように、その瞳以外目に入らなくなった。
吸い込まれそうな美しい色に、息をしていることさえ忘れてしまった。
音楽が鳴り終わったことにも、しばらく気付かないでいた。
やがて長いようで短い時間が終わり、パーティはお開きとなった。
帰りの馬車に揺られ、二人は無言のまま向かい合った。
エルは気不味かった。気持ちを自覚してしまっただけに、今までのような態度を取れなかった。
早くこの場から離れたい。部屋に帰って一人になりたい。そうでもしなければ、この感情を相手に悟られてしまうような気がした。
踊っていた時より二人の距離は離れているのに、益々鼓動が早くなる。
やがて屋敷に着くと、ミラルカが出迎えてくれた。
笑顔の彼女に少し安心しつつも、エルはネリウスに深々と頭を下げると、慌てて二階に向かった。
部屋に戻ると倒れこむようにベッドにうつ伏せになった。ようやく誰もいない場所にこれて安心した。
早くドレスを脱ぎたくて仕方ない。このネックレスも────ネリウスを思い出すものは全部、取り去らないと。でないとこの鼓動を抑えられそうにない。
それなのにまだネリウスの感触を覚えていたくて、触れ合った箇所を指でなぞる。
きっとこれは、シンデレラのようなおとぎ話の夢だ。だから、朝になったら消えている────。そう無理やり思い込ませるしかなかった。
だけど皮肉なことに、ネリウスのことをを考えて目を閉じると、幸福な記憶がまるで子守唄のように眠りへと誘った。
あまりにも幸せな夢だった。
胸が詰まったような感覚がして苦しい。足と手ばかりが動いて、ネリウスの顔を見ることが出来ない。
練習していた時もそんなことがあった。目があって、お互いに動けなくなったことが────。
本当は、ずっとその瞳を見ていたい。そう思っているのに体が言うことをきかない。
掌の温度も。腰に回された手も。近づいた時に僅かに触れた胸からも────鼓動が伝わってくる。
それはけして緩やかではない。急いで駆けてきた後のように早いものだ。ネリウスも緊張しているのだろうか。
エルはその鼓動の意味を確かめたくなって、もう一度勇気を出してネリウスの瞳に視線を合わせた。
お互いこんなに近くで見つめ合うのは何度目だろうか。時が止まったかのように、その瞳以外目に入らなくなった。
吸い込まれそうな美しい色に、息をしていることさえ忘れてしまった。
音楽が鳴り終わったことにも、しばらく気付かないでいた。
やがて長いようで短い時間が終わり、パーティはお開きとなった。
帰りの馬車に揺られ、二人は無言のまま向かい合った。
エルは気不味かった。気持ちを自覚してしまっただけに、今までのような態度を取れなかった。
早くこの場から離れたい。部屋に帰って一人になりたい。そうでもしなければ、この感情を相手に悟られてしまうような気がした。
踊っていた時より二人の距離は離れているのに、益々鼓動が早くなる。
やがて屋敷に着くと、ミラルカが出迎えてくれた。
笑顔の彼女に少し安心しつつも、エルはネリウスに深々と頭を下げると、慌てて二階に向かった。
部屋に戻ると倒れこむようにベッドにうつ伏せになった。ようやく誰もいない場所にこれて安心した。
早くドレスを脱ぎたくて仕方ない。このネックレスも────ネリウスを思い出すものは全部、取り去らないと。でないとこの鼓動を抑えられそうにない。
それなのにまだネリウスの感触を覚えていたくて、触れ合った箇所を指でなぞる。
きっとこれは、シンデレラのようなおとぎ話の夢だ。だから、朝になったら消えている────。そう無理やり思い込ませるしかなかった。
だけど皮肉なことに、ネリウスのことをを考えて目を閉じると、幸福な記憶がまるで子守唄のように眠りへと誘った。
あまりにも幸せな夢だった。