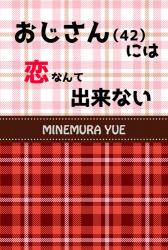大雨。それは少女にとってまたとないチャンスだった。
叩きつけるような雨の音で、少しぐらいなら音を立ててもバレないだろうと思った。
少女は閉じ込められた部屋にある唯一の窓を見た。
窓には格子が付いているが、雨ざらしのせいか錆びていて脆くなっている。どうにかすれば出られそうだ。
小さい格子の枠を何度か手をぐーにして叩いたり、手で持って引っ張ったりした。思った通り、朽ちた箇所がパキンと音を立てて崩れた。体全てを入れるにはまだ狭いが、出られないこともない。
少女は捻るようにして無理矢理外に出た。体が細くなければ出来なかっただろう。
格子から出た体はドサリと音を立てて庭に落ちた。痛い。だが、そんなにゆっくりもしていられない。
雨音で足音が消えている。足を踏み出すと無我夢中で走った。
雨で前が見えない。久しぶりに見た外の世界は暗くて寒い。どれだけ走ったか分からない。
体はすぐに力を無くした。長いこと閉じ込められていたせいで体力がなかった。
だが、それでも走らないといけない。なのに、痛くて冷たくて動けなくない。
逃げなければ。あの男から逃げなければならないのに。
────俺から逃げられるとでも思っているのか!
耳にこびりつく声を思い出し、凄まじい嫌悪感が体を包む。全身が拒絶していた。
逃げ出さなければ死んでしまう。心も体も、ぐちゃぐちゃにされてしまう。
目が届かないところへ行かなければ。もっと遠くへ逃げなければ────。
「────っ!」
飛び起きて最初に目に入ったのは、見たことがない天井だった。
少女は知らない場所にいた。自分の体は大きなベッドの上に寝かされている。部屋は以前いたあの場所ではない。
美しい調度品に囲まれ、シーツはふかふかで真っ白だ。
────どこ?
体を起こそうとするとあちこちがギシギシと痛む。全力疾走したせいか、反動で体が悲鳴をあげていた。
ふと見ると、いつの間にか腕や顔の傷が手当てされていた。しっかりと包帯が巻かれている。けれどズキズキと痛んで、体が重くなかなか動けない。
あの雨の夜の続きが思い出せなかった。逃げて走って、その後どうなったのだろう。一体どこまで走ったのだろう。
キョロキョロ見回していると、不意にパタパタと歩く音がした。
瞬間、少女の体がビクリと震えた。嫌な予感が全身を駆け巡り、体に悪寒が走る。背筋が冷たく凍るようだった。
逃げ出したと分かればどんな仕置きをされるだろう。考えただけでも恐ろしい。少女はあまりの恐ろしさに布団の中にもぐりこんで縮まった。
こんな事をしたってきっと剥ぎ取られてしまうのだろうが、自らを守る術など耐えることぐらいしか知らなかった。
コンコン、と音がした。それはかつて聞いたことがない程優しい音だった。
だが、少女は体を震わせ、ぎゅっと拳を握りしめた。
────また酷い言葉を浴びせられる。殴られる。嫌なことを言われて……。
あれこれと嫌な想像を浮かべる。
やがて、扉が開く音がした。足音はすぐ近くまで来た。
「もしかして、起きていらっしゃる?」
知らない声だった。女性だろうか。聞いたことのない、優しい、穏やかな声だ。
「寝ていたならごめんなさい。ゆっくり休んで下さいね」
声が少し遠ざかる。その人物はそのまま部屋の中を移動しているようだ。
何かスライドする音がして、眩しさが増す。太陽の光だ。
少女が顔を少しだけ出すと、臙脂色のエプロンを付けた女性がカーテンを開けていた。それを終えると女性はまたベッドの方に踵を返した。
少女は慌てて布団に隠れた。
「私はこのお屋敷でメイド長をしております、ミラルカと申します。何か御用がありましたらどうぞご遠慮なくお申し付けください」
礼儀正しい挨拶に、少女は拍子抜けした。
どうやら怖い人間ではないらしい。自分に暴力を振るっていたあの男ではない────そのことがほんの少しだけ安心させた。
ミラルカと名乗ったメイドはニッコリ微笑んだ。歳は自分よりずっと上のようだが、若い女性に見える。
少女は事態が飲み込めずミラルカとしばらくの間──ほんの十秒ほど見つめ合った。
ここは一体どこなのか。どうして自分はここにいるのか。
聞きたいが、生憎声が出ない。どうにかして伝えるすべはないだろうか。
「差し出がましいと思ったのですが、こちらを用意させて頂きました」
少女が困っていると、ミラルカは紙と万年筆を差し出した。
「どうぞ、仰りたいことがあればそれにお書きになって下さい」
声が出ないと分かったのだろう。少女は恐る恐るそれを受け取った。
だが、書くことがあまりにも久し振りすぎて、文字がうまく書けない。ミミズが這ったような跡が紙の上に残った。
ミラルカはハッと気づいてすぐに謝った。
「申し訳ありません。私の考えが至りませんでした。無理に書かなくても大丈夫ですよ」
────ぐう。
部屋にミラルカの声以外の何かが聞こえた。少女のお腹が鳴った音だった。
まるで返事のように鳴ったそれに、少女は恥ずかしいよりも恐怖した。みっともない。はしたないと怒られると思った。
「朝食をお召し上がりになりますか? すぐ用意しますね」
だが、ミラルカは気を悪くしたふうでもなくクスッと笑って部屋から出て行った。
再び一人になった部屋で、少女は呆然とした。
────ここは、あの男の家じゃないの?
逃げ出す前、自分はある男に飼われていた。金持ちの男だった。
檻の中に閉じ込められ、男の慰み者として、時には八つ当たりの道具として暴力を振るわれた。まともな人間として扱われたことはなかった。
男の元にいた時はこのような扱いを受けたことはなかった。優しくされたことはおろか、労りの言葉などかけられたこともなかった。
ミラルカはメイド長と言ってた。主人は別にいるのだろう。
少女は急に恐ろしくなった。
またあんな目に遭うのだろうか。せっかく逃げ出したのに絶望的な生活に逆戻るなんて絶対に嫌だ。毎日毎日死を望むような、そんな苦しい生活は────。
叩きつけるような雨の音で、少しぐらいなら音を立ててもバレないだろうと思った。
少女は閉じ込められた部屋にある唯一の窓を見た。
窓には格子が付いているが、雨ざらしのせいか錆びていて脆くなっている。どうにかすれば出られそうだ。
小さい格子の枠を何度か手をぐーにして叩いたり、手で持って引っ張ったりした。思った通り、朽ちた箇所がパキンと音を立てて崩れた。体全てを入れるにはまだ狭いが、出られないこともない。
少女は捻るようにして無理矢理外に出た。体が細くなければ出来なかっただろう。
格子から出た体はドサリと音を立てて庭に落ちた。痛い。だが、そんなにゆっくりもしていられない。
雨音で足音が消えている。足を踏み出すと無我夢中で走った。
雨で前が見えない。久しぶりに見た外の世界は暗くて寒い。どれだけ走ったか分からない。
体はすぐに力を無くした。長いこと閉じ込められていたせいで体力がなかった。
だが、それでも走らないといけない。なのに、痛くて冷たくて動けなくない。
逃げなければ。あの男から逃げなければならないのに。
────俺から逃げられるとでも思っているのか!
耳にこびりつく声を思い出し、凄まじい嫌悪感が体を包む。全身が拒絶していた。
逃げ出さなければ死んでしまう。心も体も、ぐちゃぐちゃにされてしまう。
目が届かないところへ行かなければ。もっと遠くへ逃げなければ────。
「────っ!」
飛び起きて最初に目に入ったのは、見たことがない天井だった。
少女は知らない場所にいた。自分の体は大きなベッドの上に寝かされている。部屋は以前いたあの場所ではない。
美しい調度品に囲まれ、シーツはふかふかで真っ白だ。
────どこ?
体を起こそうとするとあちこちがギシギシと痛む。全力疾走したせいか、反動で体が悲鳴をあげていた。
ふと見ると、いつの間にか腕や顔の傷が手当てされていた。しっかりと包帯が巻かれている。けれどズキズキと痛んで、体が重くなかなか動けない。
あの雨の夜の続きが思い出せなかった。逃げて走って、その後どうなったのだろう。一体どこまで走ったのだろう。
キョロキョロ見回していると、不意にパタパタと歩く音がした。
瞬間、少女の体がビクリと震えた。嫌な予感が全身を駆け巡り、体に悪寒が走る。背筋が冷たく凍るようだった。
逃げ出したと分かればどんな仕置きをされるだろう。考えただけでも恐ろしい。少女はあまりの恐ろしさに布団の中にもぐりこんで縮まった。
こんな事をしたってきっと剥ぎ取られてしまうのだろうが、自らを守る術など耐えることぐらいしか知らなかった。
コンコン、と音がした。それはかつて聞いたことがない程優しい音だった。
だが、少女は体を震わせ、ぎゅっと拳を握りしめた。
────また酷い言葉を浴びせられる。殴られる。嫌なことを言われて……。
あれこれと嫌な想像を浮かべる。
やがて、扉が開く音がした。足音はすぐ近くまで来た。
「もしかして、起きていらっしゃる?」
知らない声だった。女性だろうか。聞いたことのない、優しい、穏やかな声だ。
「寝ていたならごめんなさい。ゆっくり休んで下さいね」
声が少し遠ざかる。その人物はそのまま部屋の中を移動しているようだ。
何かスライドする音がして、眩しさが増す。太陽の光だ。
少女が顔を少しだけ出すと、臙脂色のエプロンを付けた女性がカーテンを開けていた。それを終えると女性はまたベッドの方に踵を返した。
少女は慌てて布団に隠れた。
「私はこのお屋敷でメイド長をしております、ミラルカと申します。何か御用がありましたらどうぞご遠慮なくお申し付けください」
礼儀正しい挨拶に、少女は拍子抜けした。
どうやら怖い人間ではないらしい。自分に暴力を振るっていたあの男ではない────そのことがほんの少しだけ安心させた。
ミラルカと名乗ったメイドはニッコリ微笑んだ。歳は自分よりずっと上のようだが、若い女性に見える。
少女は事態が飲み込めずミラルカとしばらくの間──ほんの十秒ほど見つめ合った。
ここは一体どこなのか。どうして自分はここにいるのか。
聞きたいが、生憎声が出ない。どうにかして伝えるすべはないだろうか。
「差し出がましいと思ったのですが、こちらを用意させて頂きました」
少女が困っていると、ミラルカは紙と万年筆を差し出した。
「どうぞ、仰りたいことがあればそれにお書きになって下さい」
声が出ないと分かったのだろう。少女は恐る恐るそれを受け取った。
だが、書くことがあまりにも久し振りすぎて、文字がうまく書けない。ミミズが這ったような跡が紙の上に残った。
ミラルカはハッと気づいてすぐに謝った。
「申し訳ありません。私の考えが至りませんでした。無理に書かなくても大丈夫ですよ」
────ぐう。
部屋にミラルカの声以外の何かが聞こえた。少女のお腹が鳴った音だった。
まるで返事のように鳴ったそれに、少女は恥ずかしいよりも恐怖した。みっともない。はしたないと怒られると思った。
「朝食をお召し上がりになりますか? すぐ用意しますね」
だが、ミラルカは気を悪くしたふうでもなくクスッと笑って部屋から出て行った。
再び一人になった部屋で、少女は呆然とした。
────ここは、あの男の家じゃないの?
逃げ出す前、自分はある男に飼われていた。金持ちの男だった。
檻の中に閉じ込められ、男の慰み者として、時には八つ当たりの道具として暴力を振るわれた。まともな人間として扱われたことはなかった。
男の元にいた時はこのような扱いを受けたことはなかった。優しくされたことはおろか、労りの言葉などかけられたこともなかった。
ミラルカはメイド長と言ってた。主人は別にいるのだろう。
少女は急に恐ろしくなった。
またあんな目に遭うのだろうか。せっかく逃げ出したのに絶望的な生活に逆戻るなんて絶対に嫌だ。毎日毎日死を望むような、そんな苦しい生活は────。