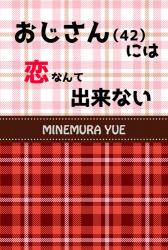レッスンは数日間続いた。回を追うごとにエルの動きは滑らかに、洗練されていった。
恐らく一人でも練習しているのだろう。ミラルカにも教わっているらしく、ネリウスは仕事中ミラルカからエルの上達ぶりを何度も聞かされた。
基本のステップは問題なさそうなので、本格的にワルツ教えることにした。
「三ステップ目で身体の方向を九十度変えるんだ。ゆっくり動くからやってみろ」
ワン、ツー、とカウントを取りながら、ゆっくり身体の方向を変える。エルが問題なくついてきたので、そのまま次の動作を教えた。
「そうだ、そこでターン……」
教えている間に、ネリウスは自分が笑っていることに気がついた。エルと踊るのが楽しかった。
ダンスは教養の一つだから今までやっていただけだ。つまらない社交界でやらないといけない面倒な行事の一つ。
女の手を引くこともあんなに疎ましく思っていたのに、その自分がダンスを楽しいなんて思っている。
だが、それは他でもないエルと踊るからなのだろう。
エルは慣れてきたのか、足元を見ることが少なくなって目線を合わせるようになった。
ふと深い緑色の瞳がまっすぐ自分を捉えて、つい足を止めてしまった。
そのまま数秒の間、時が止まったかのようにお互いを見つめた。
目が逸らせなかった。その緑色の瞳が心を見透かそうとしているように思えた。やましい気持ちが見透かされているような気がした。
先に目を逸らしたのはネリウスだった。
「すまない」
エルの瞳はいつまでも見ていたいくらい綺麗だった。視線を逸らした後も目の奥に残るほど。
最初出会った時からそうだ。透き通っていて、その名を冠した宝石のように美しい。
ネリウスは今更エルに抱くこの気持ちがなんなのか悟った。
だがそれは、伝えてはならない気持ちだ。ようやく平穏を手にした女性に言うべきではない言葉。
エルはやっと心を取り戻した。心安らかに暮らしてほしい。だから、自分が余計なことをして乱すべきではない。
それから数日間、ネリウスは時間を作ってワルツを教えた。
ワルツさえ踊れれば、社交界に行っても問題ない。エルは格段に上手くなったし、エル自身楽しんで踊れるようになったようだ。
もう教えることはない。この夢のような時間も、あと少しで終わる。
「もう、問題ないな。いつ連れて行くかは……またミラルカに知らせておく」
ネリウスがそう告げると、エルは不安げな瞳で見つめた。その瞳を見ていると妙な方向に解釈してしまいそうになる。しかし、ありえないことだ。
「そんな心配そうな顔をするな。お前なら大丈夫だ。もう十分上手く踊れている」
ネリウスは、エルの目を直視できなかった。見たら今度は、本当に抱きしめてしまいそうだった。
名残惜しいと感じる体を引き剥がすように、足早にその場を後にした。
恐らく一人でも練習しているのだろう。ミラルカにも教わっているらしく、ネリウスは仕事中ミラルカからエルの上達ぶりを何度も聞かされた。
基本のステップは問題なさそうなので、本格的にワルツ教えることにした。
「三ステップ目で身体の方向を九十度変えるんだ。ゆっくり動くからやってみろ」
ワン、ツー、とカウントを取りながら、ゆっくり身体の方向を変える。エルが問題なくついてきたので、そのまま次の動作を教えた。
「そうだ、そこでターン……」
教えている間に、ネリウスは自分が笑っていることに気がついた。エルと踊るのが楽しかった。
ダンスは教養の一つだから今までやっていただけだ。つまらない社交界でやらないといけない面倒な行事の一つ。
女の手を引くこともあんなに疎ましく思っていたのに、その自分がダンスを楽しいなんて思っている。
だが、それは他でもないエルと踊るからなのだろう。
エルは慣れてきたのか、足元を見ることが少なくなって目線を合わせるようになった。
ふと深い緑色の瞳がまっすぐ自分を捉えて、つい足を止めてしまった。
そのまま数秒の間、時が止まったかのようにお互いを見つめた。
目が逸らせなかった。その緑色の瞳が心を見透かそうとしているように思えた。やましい気持ちが見透かされているような気がした。
先に目を逸らしたのはネリウスだった。
「すまない」
エルの瞳はいつまでも見ていたいくらい綺麗だった。視線を逸らした後も目の奥に残るほど。
最初出会った時からそうだ。透き通っていて、その名を冠した宝石のように美しい。
ネリウスは今更エルに抱くこの気持ちがなんなのか悟った。
だがそれは、伝えてはならない気持ちだ。ようやく平穏を手にした女性に言うべきではない言葉。
エルはやっと心を取り戻した。心安らかに暮らしてほしい。だから、自分が余計なことをして乱すべきではない。
それから数日間、ネリウスは時間を作ってワルツを教えた。
ワルツさえ踊れれば、社交界に行っても問題ない。エルは格段に上手くなったし、エル自身楽しんで踊れるようになったようだ。
もう教えることはない。この夢のような時間も、あと少しで終わる。
「もう、問題ないな。いつ連れて行くかは……またミラルカに知らせておく」
ネリウスがそう告げると、エルは不安げな瞳で見つめた。その瞳を見ていると妙な方向に解釈してしまいそうになる。しかし、ありえないことだ。
「そんな心配そうな顔をするな。お前なら大丈夫だ。もう十分上手く踊れている」
ネリウスは、エルの目を直視できなかった。見たら今度は、本当に抱きしめてしまいそうだった。
名残惜しいと感じる体を引き剥がすように、足早にその場を後にした。