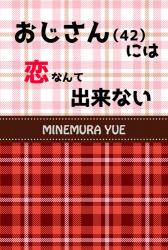ネリウスは書斎の窓から庭を眺めた。
今日は天気も良く日差しも心地よい。外で昼寝するなら最高だろう。
エルにバラを贈ってから、彼女は頻繁にバラ園に立ち寄るようになったようだ。どうやら気に入ってくれたらしい。エルは今日も庭で過ごしていた。
エルが喜んでくれたのならそれでいい。たとえ会話できなくても、近づけなくても、喜んでくれているのなら自分は満足だ。
そう言い聞かせながらも、ネリウスはどこかモヤモヤした気持ちを抱いた。
突然ノックの音がして、扉からミラルカが現れた。コーヒーを持ってきたらしい。
ミラルカはキャビネットの上で慣れた動作を繰り返す。ネリウスはミラルカに指摘される前に庭を眺めることをやめて新聞に目を通した。
「本日はブルーマウンテンでございます」
いつものようにミラルカが珈琲の銘柄を報告し、用事を終えれば部屋から下がるはずだった。しかし、ミラルカは目前に控えたまま動こうとしない。
さすがに不審に思って顔を上げると、ミラルカがニンマリと笑いながら立っていた。ネリウスは思わず怪訝な顔をした。
「……なんだその顔は」
「いえいえ、旦那様もやっと女心がわかるようになったんだと思うと嬉しくて」
「それでそんな気色悪い顔をしてるのか」
「エル様、とても喜んでますよ」
「知ってる。毎日ベンチに座っているだろう」
「やっぱり、見てたんですね」
ネリウスはしまった、と視線をそらした。
ミラルカはそんなネリウスをからかうでもなく満足そうに見つめている。
「エル様、ここに来た時と比べたら随分お美しくなられました。それに、いつ社交界に出しても恥ずかしくない教養も身に付けられました」
「……お前は遠回しに何が言いたいんだ?」
「私、エル様に持てる全ての教養を教えたつもりです。ですが、まだ教えていないことがあります」
ネリウスはミラルカが言わんとしていることを理解してゲンナリした。
社交界、教養────とくれば、次はダンスだ。ミラルカはエルにダンスを教えようと思っているのだろう。
「俺には無理だ」
だが、ネリウスは即座に拒否した。
「あら? 無理だなんて旦那様のお言葉とも思えませんね」
「大体あいつはそもそも男に触るなんて無理だろう。そんな状態でどうやってエスコートするんだ」
「あら、いつ私がエスコートしろなんて言いました?」
ネリウスは今度こそ盛大にため息を吐いた。
ミラルカにいいように動かされている気がしてならない。彼女は巧みな言葉で自分を誘導して、目的に近づけたいのだろう。
「エル様は旦那様に会いたいはずです。あんなにバラを眺めて……旦那様のことを大事に思っているんだと思います」
「物事を仮定で話すな。あいつは男性恐怖症で俺に近づきもしないじゃないか。どうやって話しかけろっていうんだ」
「旦那様、一体いつのことを話しているんです? もう、ファビオとだって握手も出来るようになりましたし、ジャックや他の人とだって二人きりで話せるんですよ。ご主人様とだって────」
「俺をあいつらと一緒にするな」
「ただのヤキモチじゃないですか。旦那様が紳士的にエスコートすれば、エル様だってきっと分かってくれますよ」
「……ハッ、どうだかな」
ミラルカの言う通り、ネリウスはそばに行きたいと思いながら拒絶されるのが怖くて近づけないでいた。
ファビオ達と話す姿が羨ましくて、自分とも話してほしいと思いながら、自分だけは特別でいたいなんて勝手なわがままを言っている。
だが、本当は自分だって一緒にいたいと思っていた。
「……本人に聞け。それでいいなら俺がやる」
「承知しました! すぐに聞いてまいります!」
返事を聞くなりミラルカは勢いよく部屋から飛び出した。
────いいのか、これで?
許可を出したものの、ネリウスは気が進まなかった。だが今更どうしようもない。開き直ってしまえばどうとでもなるだろう。
もし断られたら関わらないようにすればいいだけだ。この広い屋敷を要塞代わりにすればいい。
だけどもし、いいのなら────。
今日は天気も良く日差しも心地よい。外で昼寝するなら最高だろう。
エルにバラを贈ってから、彼女は頻繁にバラ園に立ち寄るようになったようだ。どうやら気に入ってくれたらしい。エルは今日も庭で過ごしていた。
エルが喜んでくれたのならそれでいい。たとえ会話できなくても、近づけなくても、喜んでくれているのなら自分は満足だ。
そう言い聞かせながらも、ネリウスはどこかモヤモヤした気持ちを抱いた。
突然ノックの音がして、扉からミラルカが現れた。コーヒーを持ってきたらしい。
ミラルカはキャビネットの上で慣れた動作を繰り返す。ネリウスはミラルカに指摘される前に庭を眺めることをやめて新聞に目を通した。
「本日はブルーマウンテンでございます」
いつものようにミラルカが珈琲の銘柄を報告し、用事を終えれば部屋から下がるはずだった。しかし、ミラルカは目前に控えたまま動こうとしない。
さすがに不審に思って顔を上げると、ミラルカがニンマリと笑いながら立っていた。ネリウスは思わず怪訝な顔をした。
「……なんだその顔は」
「いえいえ、旦那様もやっと女心がわかるようになったんだと思うと嬉しくて」
「それでそんな気色悪い顔をしてるのか」
「エル様、とても喜んでますよ」
「知ってる。毎日ベンチに座っているだろう」
「やっぱり、見てたんですね」
ネリウスはしまった、と視線をそらした。
ミラルカはそんなネリウスをからかうでもなく満足そうに見つめている。
「エル様、ここに来た時と比べたら随分お美しくなられました。それに、いつ社交界に出しても恥ずかしくない教養も身に付けられました」
「……お前は遠回しに何が言いたいんだ?」
「私、エル様に持てる全ての教養を教えたつもりです。ですが、まだ教えていないことがあります」
ネリウスはミラルカが言わんとしていることを理解してゲンナリした。
社交界、教養────とくれば、次はダンスだ。ミラルカはエルにダンスを教えようと思っているのだろう。
「俺には無理だ」
だが、ネリウスは即座に拒否した。
「あら? 無理だなんて旦那様のお言葉とも思えませんね」
「大体あいつはそもそも男に触るなんて無理だろう。そんな状態でどうやってエスコートするんだ」
「あら、いつ私がエスコートしろなんて言いました?」
ネリウスは今度こそ盛大にため息を吐いた。
ミラルカにいいように動かされている気がしてならない。彼女は巧みな言葉で自分を誘導して、目的に近づけたいのだろう。
「エル様は旦那様に会いたいはずです。あんなにバラを眺めて……旦那様のことを大事に思っているんだと思います」
「物事を仮定で話すな。あいつは男性恐怖症で俺に近づきもしないじゃないか。どうやって話しかけろっていうんだ」
「旦那様、一体いつのことを話しているんです? もう、ファビオとだって握手も出来るようになりましたし、ジャックや他の人とだって二人きりで話せるんですよ。ご主人様とだって────」
「俺をあいつらと一緒にするな」
「ただのヤキモチじゃないですか。旦那様が紳士的にエスコートすれば、エル様だってきっと分かってくれますよ」
「……ハッ、どうだかな」
ミラルカの言う通り、ネリウスはそばに行きたいと思いながら拒絶されるのが怖くて近づけないでいた。
ファビオ達と話す姿が羨ましくて、自分とも話してほしいと思いながら、自分だけは特別でいたいなんて勝手なわがままを言っている。
だが、本当は自分だって一緒にいたいと思っていた。
「……本人に聞け。それでいいなら俺がやる」
「承知しました! すぐに聞いてまいります!」
返事を聞くなりミラルカは勢いよく部屋から飛び出した。
────いいのか、これで?
許可を出したものの、ネリウスは気が進まなかった。だが今更どうしようもない。開き直ってしまえばどうとでもなるだろう。
もし断られたら関わらないようにすればいいだけだ。この広い屋敷を要塞代わりにすればいい。
だけどもし、いいのなら────。