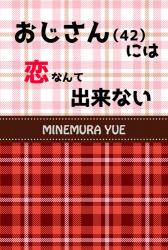────俺はほんまに杉野さんが好きなんか? 計画のターゲットやんか。
文也は帰宅してからもずっとそのことを考えた。なぜよりによって杉野なのだろう。好きになる相手なんて誰だって良かったはずだ。
だが、杉野には今まで付き合った誰よりも特別なものを感じていた。
最初は好きになるつもりなんてなかった。ただ早く父親から会社を取り戻したくて焦っていた。杉野のことだって嫌いだった。「津川」に媚びるその辺にいる女と同じ、軽蔑すべき対象だと思っていた。
それがいつの間にか嫌悪の感情は消え、杉野に対し親近感を抱くようになっていた。
気晴らしに酒を煽ってみるが昼間のことが頭から消えない。もしかして、杉野は青葉秘書のことが好きなのだろうか。噂が立つぐらいだ。もしかしたら本当のことなのかもしれない。
そんなことを考えているものだから余計に酔えなかった。ただアルコールに頭がくらくらして気分が悪くなっただけだ。
いつぞや見た杉野の笑顔は幻かなにかだったのだろうか。自分に笑いかけてくれたことも。
数日後、津川は「滝川」として出勤した。清掃の素晴らしいところは、要領さえ分かっていれば何も考えなくても手さえ動かしていればある程度仕事が進むことだ。
清掃の仕事を初めてまだ一年も経っていないが、そこそこ慣れてきたためそんな調子でも仕事はなんとかなった。
ただ、視界のどこかに杉野を探しながら。
今日も杉野は受付にいなかった。
本当に受付嬢を辞めてしまったのだろうか。本人から聞きたいが、話す機会がない。「文也」として話を聞いた時はただ驚いて、そして杉野の言葉に傷付いて、何も言えなかった。
貴重な時間を無駄にして、気が付いたら杉野は帰っていた。嫌な思い出として残された公園に一人で座って。
「滝川さん?」
すっかり気が抜けていたから気が付かなかった。待っていたはずの杉野に話し掛けられたのに意識はどこかに消えていた。
「こんにちは。お久しぶりですね」
杉野は穏やかに笑う。この間別れた時は冷たい顔をしていたのに。やっぱり滝川は津川より特別なのか。
波風が立つ心を押し殺して、文也は平静を装った。
「最近受付で見ませんね」
もう受付嬢は辞めてしまったのかと聞きたかった。けれどそんな勇気はなくて、知らないふりをして滝川のふりを続けた。
「そうなんです。ちょっと秘書課を手伝わないといけなくなって。しばらくは受付には立てないと思います」
「……辞めてしまうんですか」
「え?」
違う。本当に聞きたいのは「辞めてしまうか」ではない。「あの秘書のことをどう思っているのか」、「滝川のことをどう思っているのか」、「約束のことは忘れたのか」。
「杉野さん、今度────」
「杉野さん」
はっきりとした声が廊下に響く。杉野は振り返る。
「すみません。午後のミーティングの件でちょっといいですか」
呼び止めた青葉秘書は何やら急いでいる様子だった。杉野のつま先が文也から青葉の方向に向きを変えた。
「ごめんなさい、ちょっと行きますね」
────行くな。
文也は心の中で呟いた。だが、その言葉が杉野に届くことはなかった。彼女の後ろ姿を眺めながら、一体どっちの意味だろうと自問自答した。
馬鹿だから浅い考えで事を起こした。そうして彼女に嫌われた。それでもやっとのことで近付けたと思ったのに、どうしたまた離れてしまうのだろう。
浅はかだ。「津川文也」ではなく「滝川」なら好きになってもらえるとでも思ったのだろうか。
文也は帰宅してからもずっとそのことを考えた。なぜよりによって杉野なのだろう。好きになる相手なんて誰だって良かったはずだ。
だが、杉野には今まで付き合った誰よりも特別なものを感じていた。
最初は好きになるつもりなんてなかった。ただ早く父親から会社を取り戻したくて焦っていた。杉野のことだって嫌いだった。「津川」に媚びるその辺にいる女と同じ、軽蔑すべき対象だと思っていた。
それがいつの間にか嫌悪の感情は消え、杉野に対し親近感を抱くようになっていた。
気晴らしに酒を煽ってみるが昼間のことが頭から消えない。もしかして、杉野は青葉秘書のことが好きなのだろうか。噂が立つぐらいだ。もしかしたら本当のことなのかもしれない。
そんなことを考えているものだから余計に酔えなかった。ただアルコールに頭がくらくらして気分が悪くなっただけだ。
いつぞや見た杉野の笑顔は幻かなにかだったのだろうか。自分に笑いかけてくれたことも。
数日後、津川は「滝川」として出勤した。清掃の素晴らしいところは、要領さえ分かっていれば何も考えなくても手さえ動かしていればある程度仕事が進むことだ。
清掃の仕事を初めてまだ一年も経っていないが、そこそこ慣れてきたためそんな調子でも仕事はなんとかなった。
ただ、視界のどこかに杉野を探しながら。
今日も杉野は受付にいなかった。
本当に受付嬢を辞めてしまったのだろうか。本人から聞きたいが、話す機会がない。「文也」として話を聞いた時はただ驚いて、そして杉野の言葉に傷付いて、何も言えなかった。
貴重な時間を無駄にして、気が付いたら杉野は帰っていた。嫌な思い出として残された公園に一人で座って。
「滝川さん?」
すっかり気が抜けていたから気が付かなかった。待っていたはずの杉野に話し掛けられたのに意識はどこかに消えていた。
「こんにちは。お久しぶりですね」
杉野は穏やかに笑う。この間別れた時は冷たい顔をしていたのに。やっぱり滝川は津川より特別なのか。
波風が立つ心を押し殺して、文也は平静を装った。
「最近受付で見ませんね」
もう受付嬢は辞めてしまったのかと聞きたかった。けれどそんな勇気はなくて、知らないふりをして滝川のふりを続けた。
「そうなんです。ちょっと秘書課を手伝わないといけなくなって。しばらくは受付には立てないと思います」
「……辞めてしまうんですか」
「え?」
違う。本当に聞きたいのは「辞めてしまうか」ではない。「あの秘書のことをどう思っているのか」、「滝川のことをどう思っているのか」、「約束のことは忘れたのか」。
「杉野さん、今度────」
「杉野さん」
はっきりとした声が廊下に響く。杉野は振り返る。
「すみません。午後のミーティングの件でちょっといいですか」
呼び止めた青葉秘書は何やら急いでいる様子だった。杉野のつま先が文也から青葉の方向に向きを変えた。
「ごめんなさい、ちょっと行きますね」
────行くな。
文也は心の中で呟いた。だが、その言葉が杉野に届くことはなかった。彼女の後ろ姿を眺めながら、一体どっちの意味だろうと自問自答した。
馬鹿だから浅い考えで事を起こした。そうして彼女に嫌われた。それでもやっとのことで近付けたと思ったのに、どうしたまた離れてしまうのだろう。
浅はかだ。「津川文也」ではなく「滝川」なら好きになってもらえるとでも思ったのだろうか。