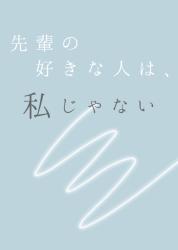「ほら、行くぞ」
梓に手を引かれて立ち上がる。
その瞬間、ぱっと花火大会の光景が脳裏に浮かんだ。
あのときのように、手が熱い。
「聞こえるぞオオオオオォォ! おなごたちの心の悲鳴が聞こえるッ……! なんて罪作りな男なんだッ……」
依然として田中先輩の実況アナウンスは派手なままである。
一瞬ちょっと大袈裟だと思ったけれども、梓が他の子の手を引くのを想像してみたら、あながち間違っていないのかもしれないと思えた。
ゴール地点へ戻って回り込み、正面からゴールテープを切る。
当然のごとく1着だった。
繋がれていた手が離れてしまい、熱を帯びていた私の手が、所在なく虚空をさ迷う。
そして梓は、近くにいた女子の体育祭実行委員ではなく、離れた方にいた男子の委員にお題の紙を渡した。
「あー。これは確かに女子の悲鳴が聞こえそうだわ」
紙を受け取った男子の委員は、すぐにそれを折り畳んで回収ボックスに入れてしまった。