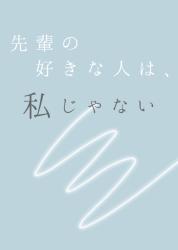「やっててよかったね」
2人とも同じランチプレートを選んだ。
向かい合わせの席に座る。
「もしまた同じ大学になったらこんな感じなのかな」
ふと自分からそんな言葉が出てきてしまったことに、内心焦った。
梓と同じ大学になったとしても、一緒にお昼ご飯を食べることにはならないはずだ。何を言っちゃっているの。
梓は瞬きを繰り返した後、おもむろに口を開いた。
「俺、ずっと永瀬に嫌われてるんだと思ってた」
そして手元に視線を落した後、もう一度私を見る。
「でも、案外そうでもない感じ?」
何も言えなくなる。
「特に最近はそんな気がする」
梓はそう言うとハンバーグに手を付け始めた。
私のことを貶していたのは梓の方だ。
でも、確かに次の日から拒絶を示したのは私だった。梓を避けた。
実はあのとき聞いていて、と説明すればいいのだろうか。
いや、話しちゃいけない。
どうしてそれが避ける理由になるのか、なんてところにまで話が及んだらおしまいだ。
本当にただの友達であるなら、恋愛対象外だと言われたくらいで打撃を受けて避けるはずがない。梓に好意を抱いていたことがバレてしまう。
「嫌ってないよ」
ただそう伝えることしかできなかった。
「中学のとき、俺のこと急に避けたくせに」
「あれはっ! ……あれは、その。そうだ、確か他に好きな人ができちゃって、その人に勘違いされたくなかったっていうか」
我ながら出てきた嘘がこれか、と思ってしまう。
「好きな人って誰」
梓の声のトーン下がった。
「え、っと、内緒」
名前を挙げようと過去のクラスメイトの顔を思い浮かべてみたけど、何と無しに他の人が好きだったことにしたくないな、と思ったので口を噤むことにした。
「ふーん」
梓もそれ以上追及してくることはなかった。