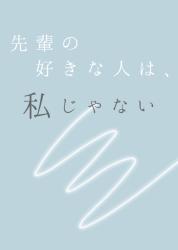「そ、そう言えば」
動揺を誤魔化すように、私は口を開いた。
「放送部に入るの、勧めてくれてありがとう。私には何もないと思っていたけど、いろいろなことに気づけたし、目標もできたよ」
梓に聞いてほしかったけど、話せていなかったこと。
それを今、ようやく梓に伝えられる。
放送部に入ったおかげで、大切なことに気づけた。
もし入っていなかったら、私はまだ梓に気持ちを伝えられずに、すれ違ったままだったかもしれない。
「俺としては、結衣子が倫太郎と仲良くなって複雑な心境だけど」
梓は冗談混じりに苦笑した。
「倫太郎君はむしろ、私たちのことを応援してくれていたよ」
「どうだか」
私は繋いでいる梓の手をぎゅっと握った。
「冗談。わかっているよ」
梓はそう言うと、私のおでこに口づけた。
思わず梓の唇が触れたところを、手で押さえてしまう。
言葉以外でも、考えていることが伝わったのかもしれない。
「人がいるから。口はまた2人きりのときに」
梓はそう言っていたずらっぽく笑った。