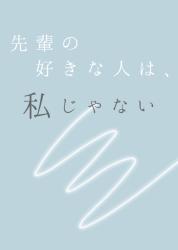「歩きスマホ、危ない」
「ごめんなさい。倫太郎君に道を教えてもらっていて」
私がそう言うと、梓の眉がピクッと動いた。
「へぇ。どこに行くつもりなの?」
「倫太郎君の家だよ」
「は?」
梓は眉を寄せている。
不味いことを言っちゃったかな。
「なんで」
梓はぶっきらぼうに理由を尋ねてくる。
「え? 数学を教えてもらう約束をして、それで」
私がそう答えると、梓は不快そうな表情を浮かべた。
「なにそれ」
梓が吐き捨てるように言う。
私たちの間に、気まずい空気が流れた。
「なんで、俺じゃないの」
梓が真っ直ぐに私の方を見て言う。
その瞳は揺れていた。
そしてまたすぐに、梓は地面に視線を落とす。
「絶対に俺の方が、できるはずなのに。数学、なんで俺に聞かないの」
凄い自信だ。
よほど普段のテストや模試での点数が良いのだろう。
なんだか梓がやきもちを焼いてくれているみたいに思えて、ドキドキしてしまう。
そんなはずはないのに。