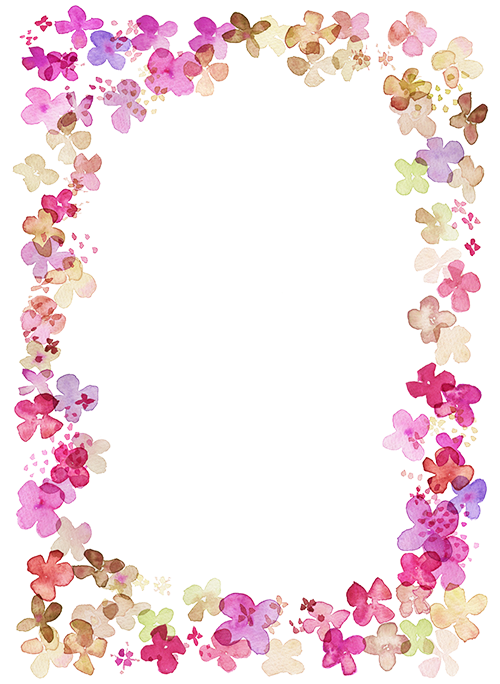「似合ってるよ。なんだか…お姫様みたいだ」
「え?」
思わず聞き返すと、レメックは少し顔を赤くした。
「いや…とにかく、似合ってるよ!」
あたしは聞き逃してはいなかった。
レメックが、あたしのことを…お姫様と言った!!
「ほんとに?」
「えっ?」
「あたし、お姫様みたい?」
「…聞いてたんだ」
レメックはまた顔を赤くして、そっぽを向いてしまった。
けれど、今度ははっきりと言った。
「うん、お姫様みたいだよ…ほんとに」
レメックは照れているようで、
しばらくの間、こちらを見てもくれなかった。
けれど、あたしは幸せだった。
あまりにも嬉しくて、
今すぐ空を飛べそうなほどフワフワした気分だった。
「アネタ?」
ようやく、レメックが口を開いた。
「ごめん…心配かけて。
でも、どうしても、帽子を取りに行きたくて体が動いちゃったんだ。
だって、それは…アネタの大切なものだから」
申し訳なさそうに言う、レメック。
あんなに怒って悪かったな、とあたしは思った。
「レメック…
あたしがこの帽子をお祖母ちゃんに買ってもらったこと、覚えてたんだ」
少し驚きながら言うと、レメックはうなずいた。
「当たり前だろ?すごく喜んでたじゃないか」
確かに、大好きだったお祖母ちゃんに買ってもらったこの帽子は、
あたしのお気に入りだった。
お祖母ちゃんが死んでしまった夏、葬式に出た時にも、
ずっとこの帽子をかぶっていたほどだった。
レメックは、ちゃんと見てくれていたんだ……温かい気持ちになった。
「ありがとう…レメック」
あたしが笑うと、レメックも笑顔になった。
大好きな笑顔。
小さかった頃から、ずっと守ってきてくれた笑顔。
あたしとレメックは、ほんの幼い頃から、ずっと一緒だった。
家もすぐ近所で、あたしはレメックとその家族のことが本当に大好きだった。
レメックのお父さんとお母さんは、とても親切な温かい人たちだった。
あたしが急に家にやって来ても、
嫌な顔一つせず、「いらっしゃい」と笑顔で迎え入れてくれた。
彼らは、あたしの実の両親よりも、あたしのことを理解しようとしてくれた。
あたしのことを「良い子」だと言ってくれた大人は、
死んでしまったお祖母ちゃん以外、彼らだけだった。
レメックには、小さな妹もいた。
とても可愛い子で、一人っ子のあたしにとっても、たった一人の妹のような存在だった。
レメックは本当に妹思いで、いつも妹のことを気にかけていた。
あたしは、レメックのそういうところも好きだった。
レメックの家族は、あたしの理想だった。
優しいお父さんに、明るいお母さん、そして可愛い妹…
レメックが持っていた全てを、あたしは一つも持っていなかったからだ。
まだ小学生になったばかりの頃、あたしはとある女の子に嫌がらせを受けた。
あたしは、それに抵抗しようとして、その女の子を押し倒してしまった。
すると、怒ったその女の子の両親が、
あたしのことを「娘を傷つけた問題児」と町中に言いふらした。
小さな町では、そういう話はあっという間に広まった。
そうして、あたしは町中で「問題児」と言われるようになった。
あたしは生まれつきとても感情的な性格なので、
それ以降も、たびたび学校でトラブルを起こした。
そういうわけで、「問題児」という汚名は、ずっとあたしについて回ってきた。
問題児のあたしに、友達はできなかった。
学校では、いつも、独りで絵を描くか、絵本を読んだりして過ごした。
けれど、そんなあたしに、唯一いつも声を掛けてきてくれる人物がいた。
それこそが、レメックだった―。