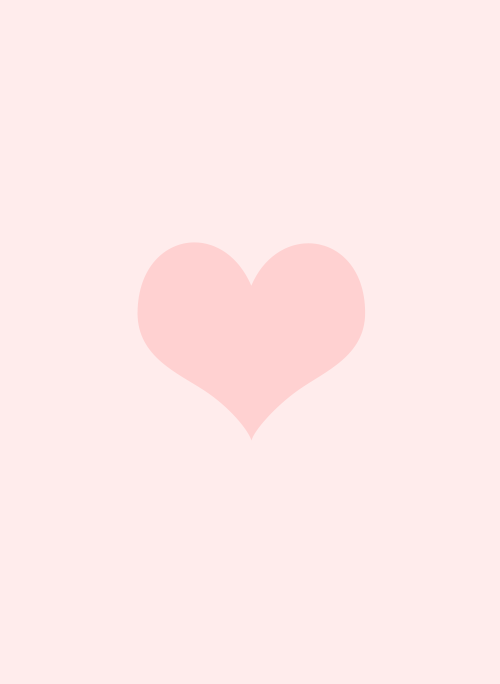鼻を突く匂いはもちろん、差し込んだ明かりに晒されたイーゼルと画材が、夏杏耶にそれを確証させた。
問題は〝どこの〟美術室あるいはアトリエなのか。
「……」
こんなとき鮎世が居たら……きっと、わずかなヒントから紐解いてくれるのに。
「さーて、そろそろ時間切れだけど。解った?……まぁ、それどころじゃないかなぁ」
巡らせている間にミャオは近くまでやってきて、夏杏耶の腕を結ぶ紐に、わざとらしく手を掛ける。
「……アトリエ」
「僕が訊いてるのは場所だよ、場所。それじゃあ可算名詞だよねぇ」
「……どこかの、学校の、」
「うーん、惜しいなぁ。ま、でも───残念」
パシンッ───!!
ミャオが放った直後、乾いた音が反響する。
覚えたのは、痺れるような頬の痛みと、口内を巡る鉄の味。
「……え、」
自分の頬が叩かれたことに気が付いたのは、反動で伏した視線の先で、ミャオが笑っているのを見た後だった。