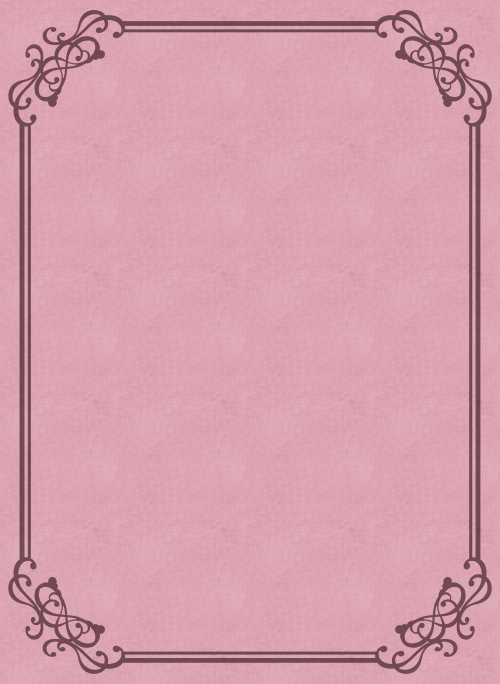すると浅見は顔が完全に固まっており、なんなら既に泣きそうだった。
……あっ、これは察した。
まだ飲み終わってもいないだろう缶コーヒーを手に、浅見は何事かを言って足早に遠藤さんの包囲網をすり抜けて去っていった。
一方遠藤さんは何も気にしてないようで、ゆったりとその場を去っていった。
俺は少しだけその場に留まって、二人のことを思い出してみる。
浅見は同期だ。部署も同じ。
話しやすくて、反応も良いので愛嬌がある。かく言う俺も浅見を良く飲みに誘う程度には仲が良い。
遠藤さんはひとつ年上の先輩で同じ部署。
良い人である。面倒見も良いし仕事もできる。上からも好かれている。
敢えて言うなら良い人すぎて胡散臭い。
その二人の間にどうやら一方的な好意の矢印が向いている。
浅見も満更でも無さそうならからかってやるところだが、どうやらさっきの反応を見ると割と洒落にならない程度に嫌がっている。
「これは勝手ながら助けてあげるべき……だよな、同期のよしみとして」
けれども正直、遠藤さんとの間に確執が残るのも避けたいところだが。
「浅見、ねえ……」
嬉しいことがあると寄ってきて俺に自慢してきたり、コンビニのおやつで餌付けしてやるとホクホクと幸せそうに口をもぐもぐさせている、あんまり悩みとか無さそうなイメージ。
遠藤さんとの関係と浅見への同情を天秤にかけて、俺は少しだけ悩んだ後、浅見側へ傾いた感情にひとり納得する。
あの悩みなんて無さそうな浅見が、今は疲れ切っていて、俺のイメージする浅見っぽくない。それはなんだかすごく解せない気分だった。