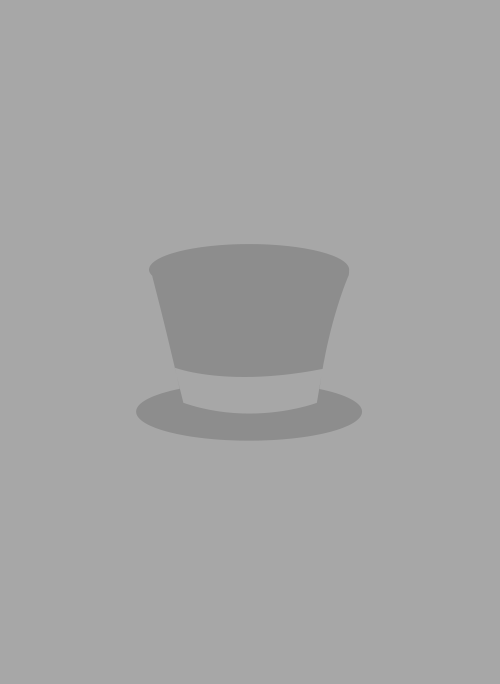どこの街にもある書店。
駅ビルにある大型書店に、それに、昔ながらの自動ドアすらない小さな本屋。
マンガのコーナーには「生殺与奪の権を他人に渡すなりゃああああああ」のヒット作品が平積みではなく正方形積みされている。
その近くに、派手な表紙のライトノベルが積まれ、その隣にライト系の小説が陣取っている。その小説たちにまぎれ、今や当たり前のように市民権を得たケータイ小説が存在をアピールしている。
もう、区別がつかない。
12年前はまだ、心ない大人たちから「ケータイ小説(笑)」的な扱いだった。でも、もう誰もそんなことを口にしない。
まだケータイ小説が知られていない頃。ひとりの女性作家が、自らの体験を元にした小説を公開し、絶大な支持を受けた。
当然のように、オレはケータイ小説の存在なんか知らなかったし、興味もまったく無かった。ハッキリいって、素人が書いた文章など読む気にもならなかった。
というか、健全は男子は目の前にあるエロを追及し、それに青春の情熱を全力で注ぎ込むものだろう。そして、すべての怠惰を愛し、すべての怠惰に愛され、怠惰に過ごす選手権で準優勝・・・まあ、そういうものだろう。
だけど、ふとしたキッカケで読み始めたネット上の小説に没頭した。
通学中に読んだばかりに、満員電車で真っ赤な目のウサちゃんに変身。思わずムーンクリスタル・・・ゲフンゲフン。
最初から最後まで一気読み。
あまりの感動に夜空に向かって「シャココール」。
星空に拡散されていったシャココールは、いつまでも苦情の声が追いかけてきたっけかな。
ネット上で見掛けたタイトルを手に取り、その表紙に視線を落とす。
確かに、書き手は格段に上手くなっているし、面白いとは思う。
だけど、心に響かない。
流行りを追い掛け、あやかしや神様のバーゲンセール。
面白いよ。
だけど、あのときのように、心が叫び出すことはない。
文字の向こう側に、作家の息遣いを感じない。
そして、あの日。
たまたま目にした番組は、「ケータイ小説特集」。そして、斜め後ろからのアングルで質問に答えていたのは、シャコだった。
プリン・・・中途半端に染まった茶髪に、かみかみ・・・不慣れな言葉たち。その存在がなぜだか愛おしくて、オレは一瞬で恋に落ちた。
あまりにも遠い存在。
接点などあるはずもなく。
どうしようもないことは分かっていたけど。
それでも、あふれる想いは止まらなくて。
どうしても、会いたくて。
「シャココール」を届けたくて。
キミに会いたくて。
キミの声を聴きたくて。
キミを守りたくて。
ケータイ小説を書いた。
想いがとどきますように、願いを込めて。