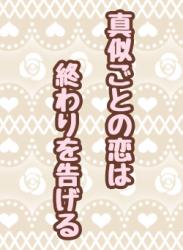ドレスの裾についたワインの染みを落とすために、コレットは化粧室へと急いでいた。
(ああ、どうしましょう。まだ何も終わっていないのに、こんなことになるなんて)
すでに頭はワインの染みを何とかすることでいっぱいだった。こういうとき、カロリーヌが側にいてくれればコレットを落ち着かせ、適切な対処を施してくれるのだが、彼女は今体調不良のため戦線離脱中である。
角をいくつか曲がって化粧室まで辿り着いたとき、ふいに手を引っ張られ、別の通路へと引きずり込まれた。
悲鳴を上げて抵抗しなかったのは、相手がジルベールだと直ぐに分かったからだ。
「じ、ジルベール様、一体どちらに行くのですか?」
「話がしたいんだ。二人だけでね」
「後にしてくださいませ。ドレスの染みを何とかしなければなりませんの!」
「ドレスなんて、また買いなおせばいいだろう」
カロリーヌが精魂こめて体調を崩してまで仕上げたドレスである。
レティシアが三人お揃いで着るのを楽しみにしていたドレスだ。
何よりも、このあとフランシスと話をしたいと思っていたのに、これでは人前にでることすら憚られる。
「大切なドレスなのです。それにまだ会場に戻らねばなりませんから」
ファーストダンスの感想をレティシアに伝えてあげたい。
体調を悪くしたカロリーヌの様子だって、本当は見にいってあげたいのだ。
「手を放してください。もう婚約解消したのですよ!」
力任せに腕を振れば、ジルベールに掴まれた手を振りほどくことができた。
「婚約解消は、お互いに本意ではないだろう? だって七年だ。七年も一緒にいたのに、簡単に割り切れるわけないだろう。そんなに簡単に僕たちの思い出は無くならないはずだ」
――簡単ではなかった。乗り越えるために、随分苦労した
「――私は、ちゃんと乗り越えました。割り切れていないのはジルベール様だけです」
「ありえないだろう。ちゃんと話し合おう。きっと思い出せるはずだ」
「ふ、フルール様はどうされるのですか。ジルベール様と婚約すると言っていたではありませんか」
同時にコレットの醜聞も言いふらしたのだ。もう一切合切思い出したくないし、関わりたくない気持ちが強い。
「あれは彼女が勝手に浮かれてやっただけだ。月並みな菓子や花を贈った程度で勘違いしただけで。家同士が乗り気だったのもあるだろうけど。コレット、僕たちは一度婚約解消してしまったから、互いに協力しないと成就できないんだ。頼むから僕の話を聞いてくれ」
「気持ちがないなら、贈り物などするべきではありません」
「嫉妬してくれたんだね。大丈夫、僕はコレットを愛しているよ」
ジルベールの言葉に、思わず一歩後ずさる。気持悪いと思ったし理解できなかった。
(思い合っていない相手から一方的な好意を向けられるのって、こんなに苦痛なのね。知らなかったわ)
ジルベールの熱に浮かされた瞳は、コレットには瞳孔が開きギラギラした異常な状態にしか見えない。
優しく伸ばされる手は、掴まれたらどこに連れていかれるかわからないという恐怖を与える。
ジルベールの期待にコレットは応えられないのに、彼の応えること以外を許容しない雰囲気が、何を言っても通じない会話が、絶望感を増幅させていった。
「ごめんなさい、ジルベール様……もう無理です」
徹底的な拒絶以外、とるべき態度が見当たらなかった。
「コレット、君は勘違いをしているんだ。大丈夫、僕たちの道は険しいけど、方法はある」
足がすくんで動けず、両手で顔を覆い目を瞑り、態度と全身で拒絶を示した。
「無理です」
「既成事実が出来てしまえば、誰もが仕方ないと認める。本当はこんなことしたくないけど、仕方ない」
「っ!」
コレットの中には、ジルベールへの恋慕は残っていなかったが、それでも七年間一緒に過ごしたときの優しい人柄や思慮深い印象が残っていた。だから、会話もしたし多少乱暴な行動に出てもそこまで危機感を募らせていなかった。――それが災いした。
目の前に立つ人は、コレットの知っているジルベールではないのだと思い知る。ようやくその結論に至ると、思わず身をひるがえして走り出した。女性の足と男性の足ではすぐに追いつかれてしまうだろうが、それでも逃げ出さずにはいられなかった。
肩を掴まれ、腕を握られ、引き戻される感覚に涙がにじむ。
「いや! 離して! 誰か」
「誰も来ないよ。お披露目会で利用する廊下からは、だいぶ距離をとったからね」
耳元で囁かれて、全身が絶望一色に染まる。
――ドスッ! ガタッ
諦めかけたその瞬間、掴まれていた腕が外れてコレットは廊下に倒れ込んだ。
鈍い音と呻き声、何かにぶつかる音が聞こえたが、転倒の衝撃による痛みで何が起きたのかは分からなかった。
固く瞑った目を開けると、廊下の先で人が倒れているのが、ぼんやりと見える。
「――大丈夫か? コレット」
声の主を見上げると、髪が少し乱れ、肩で息をするフランシスが、その傍に立っていた。
「……」
「酷い目にあったな。怪我はないか? どこか痛むところは?」
フランシスに抱き起されて、コレットはようやく自分が助かったことを、徐々に理解し始める。そして恐怖がぶり返しカタカタと体が震えだした。
「もう大丈夫だ。安心していい。何があっても守るから」
その言葉に安堵したせいで、コレットの目から涙が一粒こぼれおちた。
「あの、わたし、フランシス様と、お話をする、約束を」
「覚えていてくれて良かった。私も心待ちにしていた。でも今は手当てが先だろう」
「い、いま、すぐ、お伝えしたいことが」
まだ震えが収まらないせいで、言葉が上手く出てこない。が、どうしても伝えたくて、コレットはフランシスの腕を掴んだ。
「わたし、わたしは、フランシス様のことを――」
――思い合っていない相手から一方的な好意を向けられるのって、こんなに苦痛なのね
自分はジルベールと何が違うだろう。そんな考えが一瞬よぎり、その先を口にすることができなかった。
(ああ、どうしましょう。まだ何も終わっていないのに、こんなことになるなんて)
すでに頭はワインの染みを何とかすることでいっぱいだった。こういうとき、カロリーヌが側にいてくれればコレットを落ち着かせ、適切な対処を施してくれるのだが、彼女は今体調不良のため戦線離脱中である。
角をいくつか曲がって化粧室まで辿り着いたとき、ふいに手を引っ張られ、別の通路へと引きずり込まれた。
悲鳴を上げて抵抗しなかったのは、相手がジルベールだと直ぐに分かったからだ。
「じ、ジルベール様、一体どちらに行くのですか?」
「話がしたいんだ。二人だけでね」
「後にしてくださいませ。ドレスの染みを何とかしなければなりませんの!」
「ドレスなんて、また買いなおせばいいだろう」
カロリーヌが精魂こめて体調を崩してまで仕上げたドレスである。
レティシアが三人お揃いで着るのを楽しみにしていたドレスだ。
何よりも、このあとフランシスと話をしたいと思っていたのに、これでは人前にでることすら憚られる。
「大切なドレスなのです。それにまだ会場に戻らねばなりませんから」
ファーストダンスの感想をレティシアに伝えてあげたい。
体調を悪くしたカロリーヌの様子だって、本当は見にいってあげたいのだ。
「手を放してください。もう婚約解消したのですよ!」
力任せに腕を振れば、ジルベールに掴まれた手を振りほどくことができた。
「婚約解消は、お互いに本意ではないだろう? だって七年だ。七年も一緒にいたのに、簡単に割り切れるわけないだろう。そんなに簡単に僕たちの思い出は無くならないはずだ」
――簡単ではなかった。乗り越えるために、随分苦労した
「――私は、ちゃんと乗り越えました。割り切れていないのはジルベール様だけです」
「ありえないだろう。ちゃんと話し合おう。きっと思い出せるはずだ」
「ふ、フルール様はどうされるのですか。ジルベール様と婚約すると言っていたではありませんか」
同時にコレットの醜聞も言いふらしたのだ。もう一切合切思い出したくないし、関わりたくない気持ちが強い。
「あれは彼女が勝手に浮かれてやっただけだ。月並みな菓子や花を贈った程度で勘違いしただけで。家同士が乗り気だったのもあるだろうけど。コレット、僕たちは一度婚約解消してしまったから、互いに協力しないと成就できないんだ。頼むから僕の話を聞いてくれ」
「気持ちがないなら、贈り物などするべきではありません」
「嫉妬してくれたんだね。大丈夫、僕はコレットを愛しているよ」
ジルベールの言葉に、思わず一歩後ずさる。気持悪いと思ったし理解できなかった。
(思い合っていない相手から一方的な好意を向けられるのって、こんなに苦痛なのね。知らなかったわ)
ジルベールの熱に浮かされた瞳は、コレットには瞳孔が開きギラギラした異常な状態にしか見えない。
優しく伸ばされる手は、掴まれたらどこに連れていかれるかわからないという恐怖を与える。
ジルベールの期待にコレットは応えられないのに、彼の応えること以外を許容しない雰囲気が、何を言っても通じない会話が、絶望感を増幅させていった。
「ごめんなさい、ジルベール様……もう無理です」
徹底的な拒絶以外、とるべき態度が見当たらなかった。
「コレット、君は勘違いをしているんだ。大丈夫、僕たちの道は険しいけど、方法はある」
足がすくんで動けず、両手で顔を覆い目を瞑り、態度と全身で拒絶を示した。
「無理です」
「既成事実が出来てしまえば、誰もが仕方ないと認める。本当はこんなことしたくないけど、仕方ない」
「っ!」
コレットの中には、ジルベールへの恋慕は残っていなかったが、それでも七年間一緒に過ごしたときの優しい人柄や思慮深い印象が残っていた。だから、会話もしたし多少乱暴な行動に出てもそこまで危機感を募らせていなかった。――それが災いした。
目の前に立つ人は、コレットの知っているジルベールではないのだと思い知る。ようやくその結論に至ると、思わず身をひるがえして走り出した。女性の足と男性の足ではすぐに追いつかれてしまうだろうが、それでも逃げ出さずにはいられなかった。
肩を掴まれ、腕を握られ、引き戻される感覚に涙がにじむ。
「いや! 離して! 誰か」
「誰も来ないよ。お披露目会で利用する廊下からは、だいぶ距離をとったからね」
耳元で囁かれて、全身が絶望一色に染まる。
――ドスッ! ガタッ
諦めかけたその瞬間、掴まれていた腕が外れてコレットは廊下に倒れ込んだ。
鈍い音と呻き声、何かにぶつかる音が聞こえたが、転倒の衝撃による痛みで何が起きたのかは分からなかった。
固く瞑った目を開けると、廊下の先で人が倒れているのが、ぼんやりと見える。
「――大丈夫か? コレット」
声の主を見上げると、髪が少し乱れ、肩で息をするフランシスが、その傍に立っていた。
「……」
「酷い目にあったな。怪我はないか? どこか痛むところは?」
フランシスに抱き起されて、コレットはようやく自分が助かったことを、徐々に理解し始める。そして恐怖がぶり返しカタカタと体が震えだした。
「もう大丈夫だ。安心していい。何があっても守るから」
その言葉に安堵したせいで、コレットの目から涙が一粒こぼれおちた。
「あの、わたし、フランシス様と、お話をする、約束を」
「覚えていてくれて良かった。私も心待ちにしていた。でも今は手当てが先だろう」
「い、いま、すぐ、お伝えしたいことが」
まだ震えが収まらないせいで、言葉が上手く出てこない。が、どうしても伝えたくて、コレットはフランシスの腕を掴んだ。
「わたし、わたしは、フランシス様のことを――」
――思い合っていない相手から一方的な好意を向けられるのって、こんなに苦痛なのね
自分はジルベールと何が違うだろう。そんな考えが一瞬よぎり、その先を口にすることができなかった。