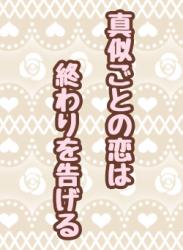没落しかけの子爵嫡男と、金だけはある商家の娘の政略結婚。それがカロリーヌの両親の馴れ初めだ。
夢も希望も愛もない。あるのは需要と供給の一致、ただそれだけである。
そんな二人の間に生まれたカロリーヌは、はじめに父親の指示で貴族令嬢としての作法を身に着けた。
けれど、お茶会に出席すると、たとえ子供同士でも成金子爵令嬢だと馬鹿にされ仲間に入れてもらえなかった。
居場所が無くて母親にかまってもらおうとしても、母は兼業のため常に忙しい人であった。
それでも気を引きたくて母の仕事の真似をしたのだが、カロリーヌはどうにも飽き性な性格らしく、なにをやっても長続きしない。
商売とは、利益がでるまで何年も耐え忍ぶ場面がある。母から見たカロリーヌの気性はとても商売には向いているように見えなかった。
結局両親のどちらにも悪く見えてしまったカロリーヌは、親に相手にされない幼少期を過ごす。
父親は貴族としての適性が乏しいことを理由に、商売を教える方が良いだろうと、カロリーヌを母親の元で学ばせることを希望した。
母親は商売人としての適性が乏しいことを理由に、貴族令嬢として育てるほうが良いだろうと、カロリーヌを父親の元で指導することを希望した。
両親は互いに相手が面倒を見るべきだと主張を譲らず、最後は金だけはあるので世話人を雇って済ませたのである。
父親と母親にダメ出しされ、カロリーヌは承認欲求を満たしてくれる相手を見失う。
年頃になると伴侶探しのために、父親から再び茶会や舞踏会にでるように指示が出た。その言いつけに従い久々の貴族社会に足を踏み入れれば、やはりカロリーヌは誰からも相手にされなかった。
彼女は外見や内面など評価されない。いつだってレッテルで評価される。
――どうせ、私なんかが何をやっても無駄なのだ
その結論に至ったカロリーヌの性格はひねくれていく。何に対しても、どうせ無駄だと言って適当にあしらい、親の言いつけには従いつつ惰性で過ごす日々が続いた。
お茶会では隅で気配を消してやり過ごし、舞踏会では壁の花というより壁と同化してやり過ごす。
そして、とある令嬢とたまに目が合うことに気付いたのである。
その令嬢は、パートナーと舞踏会に参加するのに、令嬢ばかりのお茶会では一人でいる様子だった。
年頃は、カロリーヌもその令嬢も十三歳くらいだったろうか。
ある日いつものように参加したお茶会で、目立たない席に座り時間を潰していたときだった。
「あの、お隣に座ってもよろしいかしら?」
ときどき目の合った、控えめに言ってふくよかな令嬢が話しかけてきたのである。
「――別に、私には他の席に意見する権利なんてありませんから。好きにすればよろしいのでは?」
「ありがとう。実は私、少し前からあなたのことが気になっていたの」
(お互いにボッチですもんね。そりゃ気になりますよね)
ふくよかな令嬢が同志願望で擦り寄ってきたように見えて、カロリーヌの心は同族嫌悪でいっぱいになった。
「私、シルフォン伯爵家のコレットと言います」
「……ショコル子爵家のカロリーヌよ」
コレットの家格に遠慮して、カロリーヌは態度を改める。そのせいかコレットにカロリーヌの嫌悪は伝わらなかったようで、お茶会の間中二人は会話をして過ごしたのだ。
コレットとは、婚約者を同伴しないパーティや茶会で出会うと言葉を交わすようになっていった。
互いに一人なので、出会うと会話する時間が長く、そうなると気持ちとは裏腹にコレットとの交流が深まっていくことになった。
「私は今、服飾の本を読んでいるのよ」
飽き性なカロリーヌの話題は、大概今自分がハマッているものに偏っていた。
その時は母親が布地の取り引きに力を入れて、市民相手の既製品ブランドを立ち上げた影響を受け、服飾に興味本位で手を出していたところだった。
「カロリーヌは、本当に色々なことを勉強するのね! 凄いわ」
(いや、飽き性だから手あたり次第目に着いたものに手を出しているだけだし。私はどうせ長続きしないから)
「実は私、服の悩みが尽きないの。相談に乗ってもらえるかしら?」
コレットは、そのふくよかな体型ゆえ全ての服飾がオーダーメイドであり、中々思ったものを手に取ることができないのだといった。
「オーダーメイドなら、好きなように注文できるでしょう?」
「私に似合わないという理由で、別のものを勧められてしまうの」
しょんぼりと力なく笑うコレットが、なんだか哀れに思えた。折角お金を払って作るのなら、本人の好みのものを仕立ててあげればいいのに、と。
「なら、私が作ってあげようか? シンプルなワンピースくらいならできると思うわ」
「ほ、本当?! 嬉しいわ、カロリーヌ!」
うっかり口を滑らせたカロリーヌは、コレットが物凄く喜んだせいで後に引けなくなった。
仕方なしに母親が仕入れた布で見本を作り、コレットに好きな柄の布地を選んでもらった。本をみせてワンピースのデザインを決めてもらい、コレットの体を採寸した。
ちゃんと準備をして作り始めたのだが、最初は失敗の連続だった。どうにか仕上げた頃には、季節も変わり着る機会を逃してしまっていた。
それでも、約束したのだからとコレットに差し出すと、嬉しそうにその場ですぐに着替えて見せてくれたのである。
結果は非常に残念としか言いようがなかった。
(全然コレットに似合っていない。これならいつものドレスの方がはるかに見栄えがするわ。それに何だか、きつそうに見えるし……)
反省点を見つけて落ち込むカロリーヌとは対照的に、コレットはとびきり笑顔であった。
「すごいわ! ずっとこういうワンピースを着てみたかったの。夢みたい」
(嘘ばっかり。内心文句を山ほど言っているくせに、白々しいわね)
「肩回りが窮屈そうにみえるから、採寸を間違えてしまったみたい」
「あ、それは私が太ったからよ。カロリーヌのせいではないわ」
「!」
オーダーメイドで仕立てるなら、依頼者の体型が変わることを考慮する必要があるのだと思い知った瞬間であった。
今からの季節では着ることができないワンピースは、この分だと来年にはサイズアウトして出番がないだろう。もう、今日これきりになるのかと、わびしい気持ちになった。
そんなカロリーヌとは対照的に、コレットは嬉しそうにクルクル回転しながら、鏡の前で立ち姿を確認している。
「今日から着るわね! 今からの季節に丁度良さそうだわ」
「は? 柄も布地も夏仕様よ!」
「そう? 私にはこれくらいが丁度いいみたい」
カロリーヌの気持ちなど全く気付かないコレットは、用意してあった代金を彼女に渡した。
「初めて自分の好みのワンピースを手にすることができたわ。好きなものを着るのって、こんなに楽しいのね」
反省点ばかりが目立つ初めての仕事。喜んでくれたコレットの生の声。気持よく手渡された代金を握りしめて、体中が沸騰するように熱くなる。
「つ、次はもっと素敵なものを作ってみせるわ!」
気付けば、次の約束をとりつける言葉を口にしていた。
「嬉しいわ! カロリーヌ」
多くの失敗と、手放しの賞賛が、カロリーヌを服飾の世界へとのめり込ませていった。
あれだけ何をやっても続かなかったカロリーヌは、コレットの服をデザインして作ることに没頭したのである。
軽装のワンピースに始まり、ドレスと名の付くものは全て網羅した。好きなものを似合うように着こなすためにはランジェリーも重要だと気づくと、そちらの書籍も買い漁って勉強する。
布の染色でコレットの肌が荒れたなら、染料の種類を知り、体に負担の少ないものを選ぶようにしたし、暑がりなコレットのために布地の織り方や種類を調べ、良いものを見つければ他国の布地も取り寄せた。
それなりに充実した日々を過ごすようになったある日、カロリーヌは珍しく母に褒められる。
「カロリーヌの作ったコルセットを見たけど、とても良くできているわね。ブランドの新作に参考にさせてもらってもいいかしら?」
(今さら褒めるなんてどういう風の吹きまわしかしら。――胡散臭いわね)
今まで見向きもしなかった母親が、急に擦り寄ってきたことに嫌悪して、カロリーヌはコレットに愚痴を零した。
「あら、お母さまはカロリーヌの素晴らしさに気付いたのね。どうして今まで気付けなかったのか不思議よね」
そう言われて、絶句したのをよく覚えている。
また別の日、あまり笑ったところを見たことのない父親が、珍しく笑顔で話しかけてくる。
「カロリーヌ。最近シルフォン伯爵令嬢と仲良くしているそうだな。お前には貴族令嬢の所作をちゃんと学ばせたからな。どこに出しても恥ずかしくないから、自信をもっていいぞ」
(何言ってんのこいつ。バッカみたい)
急に明後日な方向の褒め言葉を口にした父親に嫌悪して、カロリーヌはコレットに愚痴を零した。
「お父様はきっと、カロリーヌの事がずっと心配だったのね。私、あなたのお父様にカロリーヌのお友達として認めてもらえて嬉しいわ」
父親以上の明後日な見解に、度肝をぬかれた瞬間であった。
その後も、カロリーヌはいつもと違う周囲の気持ち悪い反応に遭遇するたびに、コレットに愚痴を零した。
そのたびにコレットからは想像を超える返答が返ってきて衝撃を受けるのである。その見解に、頭にきたりムカついたりすることもあったが、なぜか気付くと愚痴を零した。
コレットの言葉は、カロリーヌが受け取った事実の、もう一つの側面なのだ。
両親の需要と供給の一致した政略結婚を救済措置の逆転劇といい、カロリーヌの評価が覆ったことを、みんなの見る目が無かったのだという。
なんともおめでたいその発想は、とても受け入れられないと思う一方で、目を逸らすことができなかった。
――コレットの世界はきれいすぎる。あったかくて、優しくて、ありえない
カロリーヌにとって世界とは、冷ややかで、差別的で、厳しいものなのだ。
今さら世界を信じることなど、カロリーヌにはできなかった。
でも、コレットの見ている世界の優しさに触れたいと思った。そのあたたかさを欲して思わず手を伸ばす。
――コレットだったら信じてもいい
彼女を通して見ることのできる優しい世界なら、存在することを認めても良いと思えた。
――コレットと一緒だったら、その優しい世界の存在を、認めるのも悪くない
ひねくれた自分でも、やっとそう思えたのだ。
『どうせ私なんかが何をやっても無駄なのよ』
コレットが昔のカロリーヌと同じ思いを口にした、あの時。
――そんなことないわよ
思わず口にしそうになった言葉に絶望した。
思い詰めた悩みにそう返されたなら、カロリーヌは誰であろうと二度と相手を信用しない。
本人にとっては深い悩みを、他人の解釈で勝手に計り、軽々しく否定するのなら、そんな奴は信用に値しない。嘘つきの偽善者で、相手の事を理解しようとしない不誠実な人間だとして距離を置く。
大事な友人を、勇気づける言葉が見つからない。
その気持が痛いほどわかるのに、ひねくれて生きてきたせいで、ちっとも優しい言葉が見つからなかった。
夢も希望も愛もない。あるのは需要と供給の一致、ただそれだけである。
そんな二人の間に生まれたカロリーヌは、はじめに父親の指示で貴族令嬢としての作法を身に着けた。
けれど、お茶会に出席すると、たとえ子供同士でも成金子爵令嬢だと馬鹿にされ仲間に入れてもらえなかった。
居場所が無くて母親にかまってもらおうとしても、母は兼業のため常に忙しい人であった。
それでも気を引きたくて母の仕事の真似をしたのだが、カロリーヌはどうにも飽き性な性格らしく、なにをやっても長続きしない。
商売とは、利益がでるまで何年も耐え忍ぶ場面がある。母から見たカロリーヌの気性はとても商売には向いているように見えなかった。
結局両親のどちらにも悪く見えてしまったカロリーヌは、親に相手にされない幼少期を過ごす。
父親は貴族としての適性が乏しいことを理由に、商売を教える方が良いだろうと、カロリーヌを母親の元で学ばせることを希望した。
母親は商売人としての適性が乏しいことを理由に、貴族令嬢として育てるほうが良いだろうと、カロリーヌを父親の元で指導することを希望した。
両親は互いに相手が面倒を見るべきだと主張を譲らず、最後は金だけはあるので世話人を雇って済ませたのである。
父親と母親にダメ出しされ、カロリーヌは承認欲求を満たしてくれる相手を見失う。
年頃になると伴侶探しのために、父親から再び茶会や舞踏会にでるように指示が出た。その言いつけに従い久々の貴族社会に足を踏み入れれば、やはりカロリーヌは誰からも相手にされなかった。
彼女は外見や内面など評価されない。いつだってレッテルで評価される。
――どうせ、私なんかが何をやっても無駄なのだ
その結論に至ったカロリーヌの性格はひねくれていく。何に対しても、どうせ無駄だと言って適当にあしらい、親の言いつけには従いつつ惰性で過ごす日々が続いた。
お茶会では隅で気配を消してやり過ごし、舞踏会では壁の花というより壁と同化してやり過ごす。
そして、とある令嬢とたまに目が合うことに気付いたのである。
その令嬢は、パートナーと舞踏会に参加するのに、令嬢ばかりのお茶会では一人でいる様子だった。
年頃は、カロリーヌもその令嬢も十三歳くらいだったろうか。
ある日いつものように参加したお茶会で、目立たない席に座り時間を潰していたときだった。
「あの、お隣に座ってもよろしいかしら?」
ときどき目の合った、控えめに言ってふくよかな令嬢が話しかけてきたのである。
「――別に、私には他の席に意見する権利なんてありませんから。好きにすればよろしいのでは?」
「ありがとう。実は私、少し前からあなたのことが気になっていたの」
(お互いにボッチですもんね。そりゃ気になりますよね)
ふくよかな令嬢が同志願望で擦り寄ってきたように見えて、カロリーヌの心は同族嫌悪でいっぱいになった。
「私、シルフォン伯爵家のコレットと言います」
「……ショコル子爵家のカロリーヌよ」
コレットの家格に遠慮して、カロリーヌは態度を改める。そのせいかコレットにカロリーヌの嫌悪は伝わらなかったようで、お茶会の間中二人は会話をして過ごしたのだ。
コレットとは、婚約者を同伴しないパーティや茶会で出会うと言葉を交わすようになっていった。
互いに一人なので、出会うと会話する時間が長く、そうなると気持ちとは裏腹にコレットとの交流が深まっていくことになった。
「私は今、服飾の本を読んでいるのよ」
飽き性なカロリーヌの話題は、大概今自分がハマッているものに偏っていた。
その時は母親が布地の取り引きに力を入れて、市民相手の既製品ブランドを立ち上げた影響を受け、服飾に興味本位で手を出していたところだった。
「カロリーヌは、本当に色々なことを勉強するのね! 凄いわ」
(いや、飽き性だから手あたり次第目に着いたものに手を出しているだけだし。私はどうせ長続きしないから)
「実は私、服の悩みが尽きないの。相談に乗ってもらえるかしら?」
コレットは、そのふくよかな体型ゆえ全ての服飾がオーダーメイドであり、中々思ったものを手に取ることができないのだといった。
「オーダーメイドなら、好きなように注文できるでしょう?」
「私に似合わないという理由で、別のものを勧められてしまうの」
しょんぼりと力なく笑うコレットが、なんだか哀れに思えた。折角お金を払って作るのなら、本人の好みのものを仕立ててあげればいいのに、と。
「なら、私が作ってあげようか? シンプルなワンピースくらいならできると思うわ」
「ほ、本当?! 嬉しいわ、カロリーヌ!」
うっかり口を滑らせたカロリーヌは、コレットが物凄く喜んだせいで後に引けなくなった。
仕方なしに母親が仕入れた布で見本を作り、コレットに好きな柄の布地を選んでもらった。本をみせてワンピースのデザインを決めてもらい、コレットの体を採寸した。
ちゃんと準備をして作り始めたのだが、最初は失敗の連続だった。どうにか仕上げた頃には、季節も変わり着る機会を逃してしまっていた。
それでも、約束したのだからとコレットに差し出すと、嬉しそうにその場ですぐに着替えて見せてくれたのである。
結果は非常に残念としか言いようがなかった。
(全然コレットに似合っていない。これならいつものドレスの方がはるかに見栄えがするわ。それに何だか、きつそうに見えるし……)
反省点を見つけて落ち込むカロリーヌとは対照的に、コレットはとびきり笑顔であった。
「すごいわ! ずっとこういうワンピースを着てみたかったの。夢みたい」
(嘘ばっかり。内心文句を山ほど言っているくせに、白々しいわね)
「肩回りが窮屈そうにみえるから、採寸を間違えてしまったみたい」
「あ、それは私が太ったからよ。カロリーヌのせいではないわ」
「!」
オーダーメイドで仕立てるなら、依頼者の体型が変わることを考慮する必要があるのだと思い知った瞬間であった。
今からの季節では着ることができないワンピースは、この分だと来年にはサイズアウトして出番がないだろう。もう、今日これきりになるのかと、わびしい気持ちになった。
そんなカロリーヌとは対照的に、コレットは嬉しそうにクルクル回転しながら、鏡の前で立ち姿を確認している。
「今日から着るわね! 今からの季節に丁度良さそうだわ」
「は? 柄も布地も夏仕様よ!」
「そう? 私にはこれくらいが丁度いいみたい」
カロリーヌの気持ちなど全く気付かないコレットは、用意してあった代金を彼女に渡した。
「初めて自分の好みのワンピースを手にすることができたわ。好きなものを着るのって、こんなに楽しいのね」
反省点ばかりが目立つ初めての仕事。喜んでくれたコレットの生の声。気持よく手渡された代金を握りしめて、体中が沸騰するように熱くなる。
「つ、次はもっと素敵なものを作ってみせるわ!」
気付けば、次の約束をとりつける言葉を口にしていた。
「嬉しいわ! カロリーヌ」
多くの失敗と、手放しの賞賛が、カロリーヌを服飾の世界へとのめり込ませていった。
あれだけ何をやっても続かなかったカロリーヌは、コレットの服をデザインして作ることに没頭したのである。
軽装のワンピースに始まり、ドレスと名の付くものは全て網羅した。好きなものを似合うように着こなすためにはランジェリーも重要だと気づくと、そちらの書籍も買い漁って勉強する。
布の染色でコレットの肌が荒れたなら、染料の種類を知り、体に負担の少ないものを選ぶようにしたし、暑がりなコレットのために布地の織り方や種類を調べ、良いものを見つければ他国の布地も取り寄せた。
それなりに充実した日々を過ごすようになったある日、カロリーヌは珍しく母に褒められる。
「カロリーヌの作ったコルセットを見たけど、とても良くできているわね。ブランドの新作に参考にさせてもらってもいいかしら?」
(今さら褒めるなんてどういう風の吹きまわしかしら。――胡散臭いわね)
今まで見向きもしなかった母親が、急に擦り寄ってきたことに嫌悪して、カロリーヌはコレットに愚痴を零した。
「あら、お母さまはカロリーヌの素晴らしさに気付いたのね。どうして今まで気付けなかったのか不思議よね」
そう言われて、絶句したのをよく覚えている。
また別の日、あまり笑ったところを見たことのない父親が、珍しく笑顔で話しかけてくる。
「カロリーヌ。最近シルフォン伯爵令嬢と仲良くしているそうだな。お前には貴族令嬢の所作をちゃんと学ばせたからな。どこに出しても恥ずかしくないから、自信をもっていいぞ」
(何言ってんのこいつ。バッカみたい)
急に明後日な方向の褒め言葉を口にした父親に嫌悪して、カロリーヌはコレットに愚痴を零した。
「お父様はきっと、カロリーヌの事がずっと心配だったのね。私、あなたのお父様にカロリーヌのお友達として認めてもらえて嬉しいわ」
父親以上の明後日な見解に、度肝をぬかれた瞬間であった。
その後も、カロリーヌはいつもと違う周囲の気持ち悪い反応に遭遇するたびに、コレットに愚痴を零した。
そのたびにコレットからは想像を超える返答が返ってきて衝撃を受けるのである。その見解に、頭にきたりムカついたりすることもあったが、なぜか気付くと愚痴を零した。
コレットの言葉は、カロリーヌが受け取った事実の、もう一つの側面なのだ。
両親の需要と供給の一致した政略結婚を救済措置の逆転劇といい、カロリーヌの評価が覆ったことを、みんなの見る目が無かったのだという。
なんともおめでたいその発想は、とても受け入れられないと思う一方で、目を逸らすことができなかった。
――コレットの世界はきれいすぎる。あったかくて、優しくて、ありえない
カロリーヌにとって世界とは、冷ややかで、差別的で、厳しいものなのだ。
今さら世界を信じることなど、カロリーヌにはできなかった。
でも、コレットの見ている世界の優しさに触れたいと思った。そのあたたかさを欲して思わず手を伸ばす。
――コレットだったら信じてもいい
彼女を通して見ることのできる優しい世界なら、存在することを認めても良いと思えた。
――コレットと一緒だったら、その優しい世界の存在を、認めるのも悪くない
ひねくれた自分でも、やっとそう思えたのだ。
『どうせ私なんかが何をやっても無駄なのよ』
コレットが昔のカロリーヌと同じ思いを口にした、あの時。
――そんなことないわよ
思わず口にしそうになった言葉に絶望した。
思い詰めた悩みにそう返されたなら、カロリーヌは誰であろうと二度と相手を信用しない。
本人にとっては深い悩みを、他人の解釈で勝手に計り、軽々しく否定するのなら、そんな奴は信用に値しない。嘘つきの偽善者で、相手の事を理解しようとしない不誠実な人間だとして距離を置く。
大事な友人を、勇気づける言葉が見つからない。
その気持が痛いほどわかるのに、ひねくれて生きてきたせいで、ちっとも優しい言葉が見つからなかった。