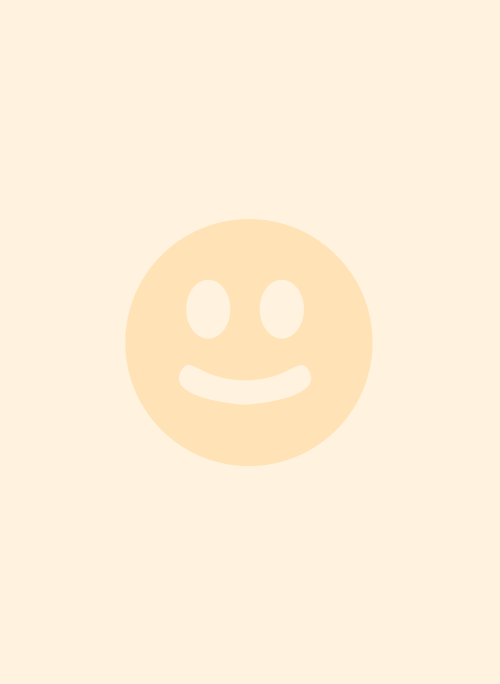激しく求め合った後、私たちは少し眠りについた。
今日は日曜日、智明も仕事は休み。だから先に目覚めた私は、智明の寝顔をそっと見つめていた。
初めて、智明が私に弱音を吐いてくれた。いつも自分のことは何も言わず、辛い表情すら見せない智明が、私を頼ってくれた。すごく、すごくうれしかった。こんな私でも誰かの役に立てる、いや、大好きな人の役に立てるんだって。
「んん・・・ 杏子・・・?」
智明がゆっくりと目を覚ました。
「おはよう」
寝ぼけ眼の智明を見て、私は自然と笑みがこぼれる。
そして私は、「熱は下がったかな?」と言って、智明の額に自分の額をくっつけた。
「下がってる?」と、智明。
「うん、大丈夫」
智明と視線が合う。私たちの唇は自然と引き寄せられる。
「さぁ、朝ご飯でも作るかな」
私がそう言って体を起こそうとした時、「杏子、俺・・・」と、智明が何かを言いかけた。私はすかさず智明の唇を人差し指で押さえる。
「何も言わないで、私は気にしてない」
智明の言いたいことはわかる。きっと私を抱いたことを謝ろうとしているんだ。感情に任せて私を抱いてしまったことに罪悪感を持っている。
「いや・・・」
「私は私のしたいようにしただけ。知ってるでしょ? 私がどういう女か」
そう言って瞬間、私は智明に抱き締められた。
「そういう言い方をするな、おまえはめっちゃいい女や」
「智明・・・」
智明は私をそんな風に思ってくれているんだ。いや、そういえば初めから智明はそう言ってくれていた。その言葉だけで十分、私は救われる。
私はうれしくて胸があたたかくなっていくのを感じた。
今日は日曜日、智明も仕事は休み。だから先に目覚めた私は、智明の寝顔をそっと見つめていた。
初めて、智明が私に弱音を吐いてくれた。いつも自分のことは何も言わず、辛い表情すら見せない智明が、私を頼ってくれた。すごく、すごくうれしかった。こんな私でも誰かの役に立てる、いや、大好きな人の役に立てるんだって。
「んん・・・ 杏子・・・?」
智明がゆっくりと目を覚ました。
「おはよう」
寝ぼけ眼の智明を見て、私は自然と笑みがこぼれる。
そして私は、「熱は下がったかな?」と言って、智明の額に自分の額をくっつけた。
「下がってる?」と、智明。
「うん、大丈夫」
智明と視線が合う。私たちの唇は自然と引き寄せられる。
「さぁ、朝ご飯でも作るかな」
私がそう言って体を起こそうとした時、「杏子、俺・・・」と、智明が何かを言いかけた。私はすかさず智明の唇を人差し指で押さえる。
「何も言わないで、私は気にしてない」
智明の言いたいことはわかる。きっと私を抱いたことを謝ろうとしているんだ。感情に任せて私を抱いてしまったことに罪悪感を持っている。
「いや・・・」
「私は私のしたいようにしただけ。知ってるでしょ? 私がどういう女か」
そう言って瞬間、私は智明に抱き締められた。
「そういう言い方をするな、おまえはめっちゃいい女や」
「智明・・・」
智明は私をそんな風に思ってくれているんだ。いや、そういえば初めから智明はそう言ってくれていた。その言葉だけで十分、私は救われる。
私はうれしくて胸があたたかくなっていくのを感じた。