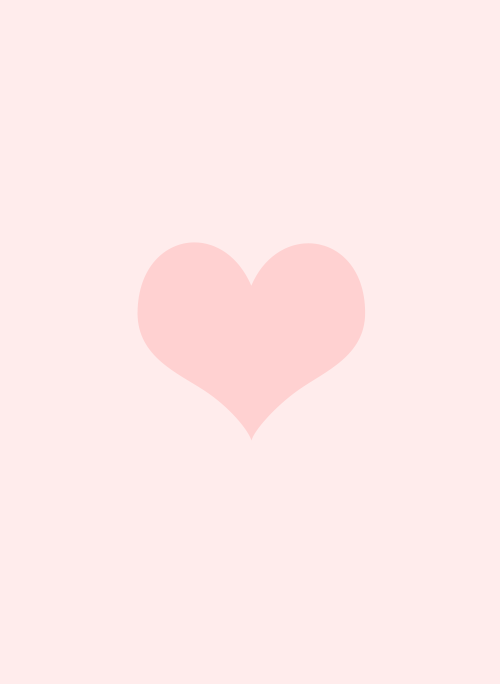あそこで、猫が出てきたんだよな…。
眞紘はそれに稀に見る食いつきを見せたもんだから目を丸くして、アイツが猫好きなのだとあの時に初めて知った。
キュッと口を結ぶ。
私は思い出から逃げるようにしてマンションの中に入っていた。
"思い出"
眞紘はもう、私の思い出になってしまったんだろうか。こんなに人を好きだと思えた初めてのことだって、もう思い出になっちゃうんだろうか。
自動販売機の前で何気なく出くわした時に、何食わぬ顔でイチゴオレを買ってくれることも…もう無くて、ぜんぶ思い出に変わってしまう?
繋いでくれた手だってそう。
あの温かさだって、これから先ずっと────。
油断をするとすぐ視界が歪んでくる。
だから私は駆け込むようにして家の扉を開けた。