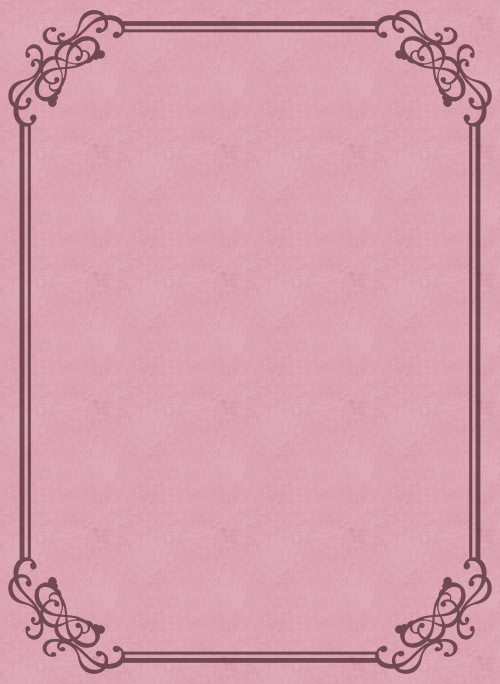……それなのに、何でだろう。少しだけ心が痛むのは。
下を向いていると、小林君がパシッと私の手を掴んだ。
「……幸音は、本当はどう思ってる?」
小林君から真剣に見つめられて思わず目を背ける。
「私は、本当にそう思ってて……。でも……」
「……でも?」
「少しだけ、二人が羨ましいなって、思った。それだけ」
戸惑いながら言う私を見て、小林君はふっと笑った。
「そうか。遥貴、今の幸音の言葉、ちゃんと聞いたか?やっぱり、俺の予想通りだっただろ?……だからもう、幸音にも普通に接してあげていいんじゃねぇの?」
「……分かってる。けど、執事の俺だけがご主人様にタメ口なんて、許されるのか?他の執事やメイドだって、この屋敷にはいるんだ。なのに、俺だけが特別扱いみたいなのは、ちょっと気が引ける」
……普通に考えると、遥貴さんの言う事は正しいのかもしれない。執事とご主人様が、友達みたいに仲良く話せる訳が無い。
遥貴さんは、私のことを気にかけて執事になってくれたはずなのに、そんな事まで望んでしまうのは、我儘だ。
「確かに、世間一般ではそうだと思う。だけど、執事にとって一番大事な事はご主人様の望むことを尊重してあげることなんじゃねぇの?」
小林君の言葉に、遥貴さんは目を見開いた。
……小林君は、すごいな……。
「幸音、遥貴さんに本当はどうしてほしいのか言ってみろ。……きっと、大丈夫だから」
小林君に頷いて、ゆっくりと遥貴さんの前に立ち、ゆっくり深呼吸をした。
「……遥貴さん。私、前みたいに遥貴さんと楽しくお話したい。ふざけあって遊んでた、あの頃みたいに……。完全に戻るのは無理かもしれないけど、でも……また友達みたいに、仲良くしたいって思うの」
下を向きながら、私は精一杯言葉を選んで声にした。そんな私を見て、遥貴さんは優しく笑った。