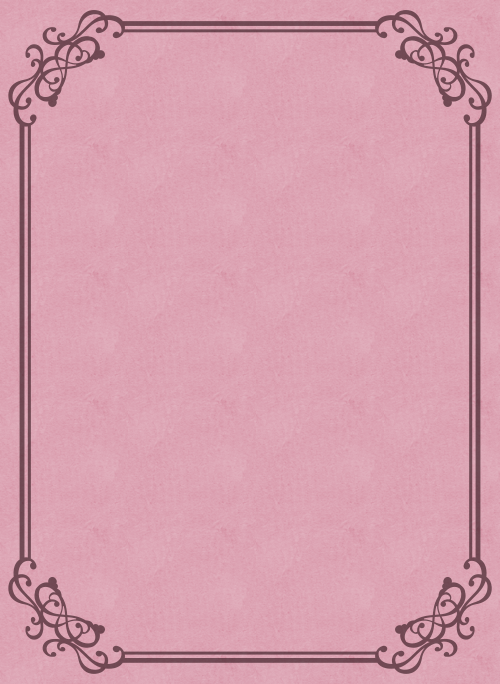「……不器用だな、遥貴さんって」
「……え?」
遥貴さんは驚いて、俺の方を見た。
俺ははぁ、とため息をつき、その場に立ち上がる。
「それが遥貴さんにとって精一杯の助ける、か?」
「……はい。俺には、そのような事しか出来なかったのです」
「……俺は、遥貴さんにとって幸音を助ける行為自体が、幸音をもっと傷つけてると思うんだけど」
「……え?何故ですか……?」
俺は遥貴さんの傍に寄り、視線を合わせた。
「…確かに幸音の様子が変わって近くで支えてあげたいと思う事はいい事だ。だけど、仲良くしていた遥貴さんが急に態度を変えて接した時、本当に幸音は嬉しいと感じたと思うか?」
遥貴さんは目を見開いた。
「逆に、不安がらせたんじゃねぇの?遥貴さんまで私を友達として見てくれなくなった、って。俺だったら、そう思うけどな」
「……」
俺は下を向いている遥貴さんを見ながら話を続ける。
「……ただ幸音は、遥貴さん自身とずっと仲良くしたかっただけだ、きっと。だから辛いことがあっても、幸音は遥貴さんの前では笑ってたんだ。遥貴さんと過ごす時間までも黒く染めたくなかったから」
「……俺は、どうしたらいいのでしょうか?」
「さぁ、知らね。それは、遥貴さんが決めることだろ?まぁ、でも一つ言うとしたら……」
俺は視線を上げた遥貴さんを見てそう言う。
「……前に戻ったら、幸音喜ぶと思うぞ」
「……そうですかね。では、頑張ってみます。夏向様、ありがとうございました」
「いいよ、別にお礼なんて。……それに、遥貴さんに敬語使われんの気持ち悪いんだよな、元々そういうキャラじゃなさそうだし」
俺の言葉に切れたのか、遥貴さんは俺を睨みつけた。
「……誰が気持ち悪いだって……?」