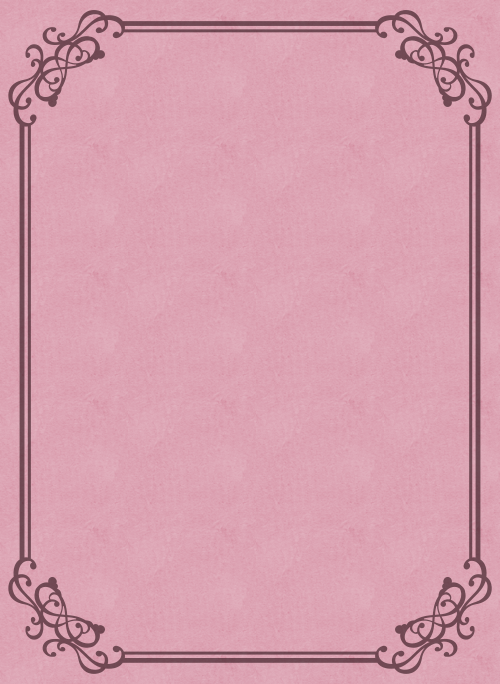「そう、だったんだな……」
遥貴さんも辛い思いしてたんだな。だから幸音も、遥貴さんに心を開きやすかったのかもしれない。
「……でもさ、遥貴さんはなんで幸音の執事になろうと思ったんだ?」
俺の問いかけに、遥貴さんの方がビクッと反応した。
「……それは、お嬢様を助けたかったからです」
「……助ける?」
「はい」
遥貴さんは、視線を俺に向けた。
「……四年前、俺は大学受験に合格し、学生生活を送っていました。学費は自分で払うと決めていたので、あの頃はほとんどお嬢様の傍にいることが出来ませんでした」
しかし、と遥貴さんは話を続ける。
「三年前、お嬢様は壊れてしまったのです」
「壊れた?」
「はい。その時の俺は知らなかったのです。お嬢様が学校で上手くいっていないこと」
俺は、その言葉に視線を落とした。
「お嬢様は、屋敷ではいつも笑っていらっしゃいました。ですが、三年前のお嬢様はいつの間にか心を閉ざされていたのです」
遥貴さんが辛そうに下を向いて言った。
「当時のお嬢様はまるで心のない操り人形のようでした。行うこと全てに対して、お嬢様自身の意思が全く感じられず、俺は俺自身を責めました。何故、こんなにも近くにいながら、お嬢様が苦しんでいることに気づいてあげられなかったのだろうと」
俺は目を見開いた。
遥貴さんは幸音を思うあまりに自分自身までもを犠牲にし、責めてきたのか?
……やっぱり幸音と遥貴さんはどこか似ている。
「だから俺は、大学を辞めてお嬢様のお傍にいることに決意しました。……たとえそれが、自分を捨てることになってしまっても」
……遥貴さんにとって、その決断はとても大きなものだったはずだ。
でも俺はそれがどうしても引っかかった。