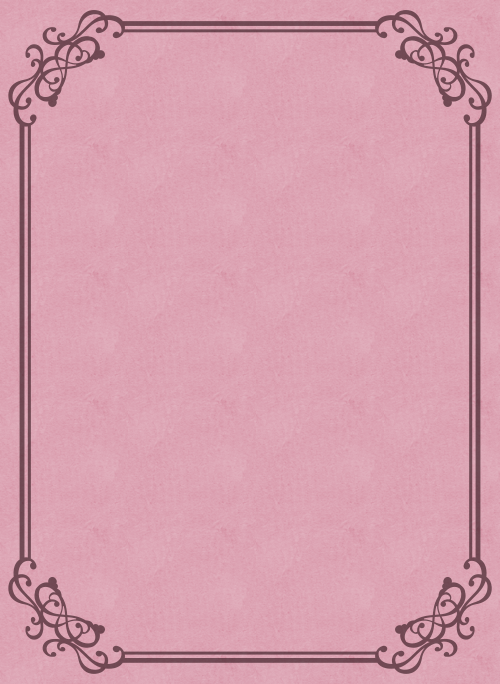~夏向目線~
俺は案内された部屋に入り、ベッドの上に横になった。
”私にはずっと昔から思っている人がいる”
幸音はそれを恋愛感情ではないと言ったが、その時の彼女の表情はまるで誰かに恋をしているようだった。
……その相手が誰なのか俺は知らない。
コンコンコン
ドアをノックする音に、俺はゆっくり身体を起こした。
「失礼いたします」
そう言って入ってきたのは、遥貴さんだった。
「お部屋はいかがですか」
「俺にはもったいないくらい素敵な部屋です。ありがとうございます」
「いえいえ、俺は何も。お礼ならお嬢様に言ってあげて下さい。それと、俺に敬語など使わなくて良いので、気軽に話しかけて下さい」
そう言って遥貴さんは微笑む。
「……じゃあ、お言葉に甘えて。俺にも敬語使わなくていいよ、遥貴さん」
「俺は、幸音みたいに地位の高い人間じゃねぇから」
「……俺は、遠慮しておきます」
その言葉に俺は少し驚いた。
「……なんで?」
「そういう自分は、もう捨てたのです。俺は所詮”執事”でしかないのですから」
遥貴さんの瞳の奥には、深い悲しみが宿っているように見えた。
……幸音と似てる。
遥貴さんも、辛い過去があったのだろうか
「遥貴さんは、幸音と似てるな」
「……それは有り得ません。お嬢様はすごいお方です。何せ俺を、助けてくれた命の恩人なのですから」
「……命の恩人?」
「えぇ」
遥貴さんは窓の方を見る。
「あれは、五年前のことでした……」
そう言って、幸音と出会った時の事を話してくれた。
それはとても残酷で悲しいお話だった。
「そして俺は三年前、お嬢様の執事としてこの屋敷で働き始めたのです」