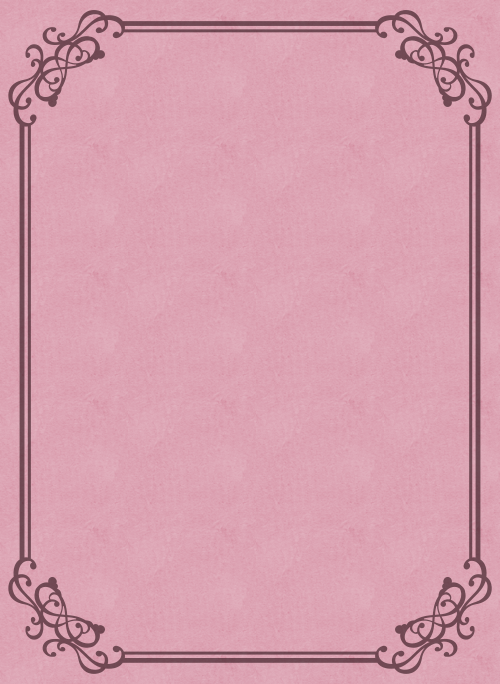「幸音……」
コンコンコン
小林君が何か言いかけた時、ドアをノックする音が聞こえた。
「お嬢様、夏向様、夕食の準備が出来上がりました」
ドア越しに、遥貴さんがそう言った。
「今、行く。……小林君、さっき言いかけたのって何だった?」
「……いや、やっぱりいい。それより、早く行こうぜ」
「……うん」
私達はドアを開け、遥貴さんの後について食事部屋へと向かって歩く。
……その時、小林君の言いかけた言葉が気になって、仕方がなかった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
夕食後、私達は廊下をスタスタと歩く。
「……幸音の家の夕食、毎回あんな感じなのか?」
「そうだよ」
私の家の夕食は、プロのシェフが働いて作ってくれている。
だから、いつも食事は高級レストランで出されるようなものばかりだ。
学校に持っていく昼食は、身分を隠すために、普通の家庭で作られるようなものにしてもらっているけれど。
それと、執事やメイドさん達とは昔から一緒に食べないことになっている。
「……じゃあ、幸音はあんな広い場所で、いつも一人で食べているのか?」
「そうだよ。私は身分や地位なんて気にしないから、執事やメイドの方達に一緒に食べていいと言うのだけれど……皆遠慮して私と食べようとしないから。もう慣れたけど」
一人でいる事は、昔から多かった。
お父様はヴァイオリニストで、お母様はピアニスト。
二人とも、私が産まれた頃には既に有名なプロの音楽家で、私に構う暇なんて少ししかなかった。
小学一年生の時までは、私に一日四時間ほど、付きっきりで二人はピアノとヴァイオリンを教えてくれた。
その時間だけが、私の唯一の楽しみな時間だった。
お父様とお母様が一緒にいてくれる事が、ただただ嬉しかった。