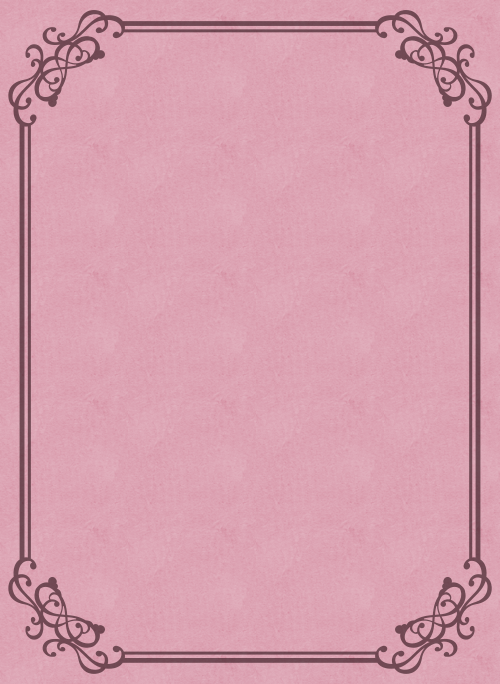「そうだな」
でも……と小林君は話を続ける。
「俺は直接、その人に言おうと思わない」
「……どうして?」
「……そんな事言える権利なんて、俺には無いんだ。だから、俺は今のままでいい……というより、今のままがいいんだ」
何か事情があるのだろう。恋心は、色々と複雑だから、私には理解し難いものだけれど……。
小林君はそういう風に言っているけど、心からそう思っているようには見えなかった。だって彼は今、悲しそうな表情をしているから。
「小林君……」
「この話はもう終わりだ。すごい時間経ってるし、そろそろ俺は帰らないと」
私が言いかけた言葉を遮って、彼は立ち上がる。
もう、ここからは踏み込むなって言われているみたいだった。……気になるけれど、小林君がそう思うなら仕方がない。
「帰らなくて大丈夫だよ。小林君は今日私の家に泊まって。もう、夕食の手配も頼んであるから」
「……はっ?何でそうなってんの?」
小林君はすごく驚いていた。その表情を見て少し笑いそうになってしまった。
「私、思ったの。小林君がいつも授業中に寝てるのは、一人暮らしが大変であまり寝れていないんじゃないかと思って」
「……幸音」
「だから、テスト期間中の時ぐらい、そんな大変なこと忘れて、少しでも小林君の負担が無くなればいいなって思ったの」
下を向いて言う私に、少しして小林君はふっと笑った。
「その言い方だと、二週間幸音の家に泊まれって聞こえるんだけど」
……正直、そこまでは考えていなかった。
でも、小林君の言っていることは間違っている訳では無い。
「小林君が二週間、私の家に居たいならいてもいいよ」
「……そうか。じゃあ、二週間泊まっていく。ありがとな」
その言葉に、私は自然と目を細めた。